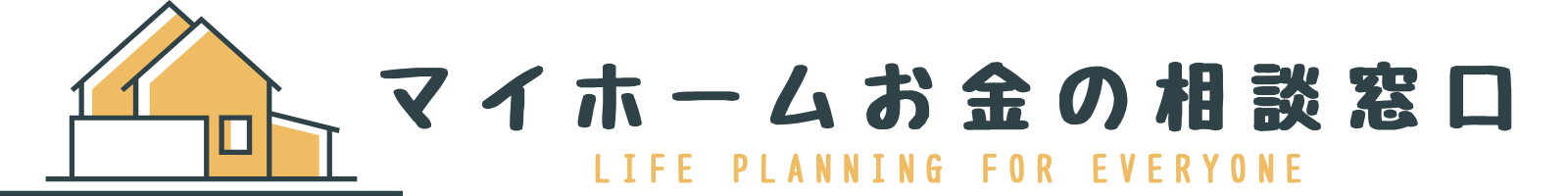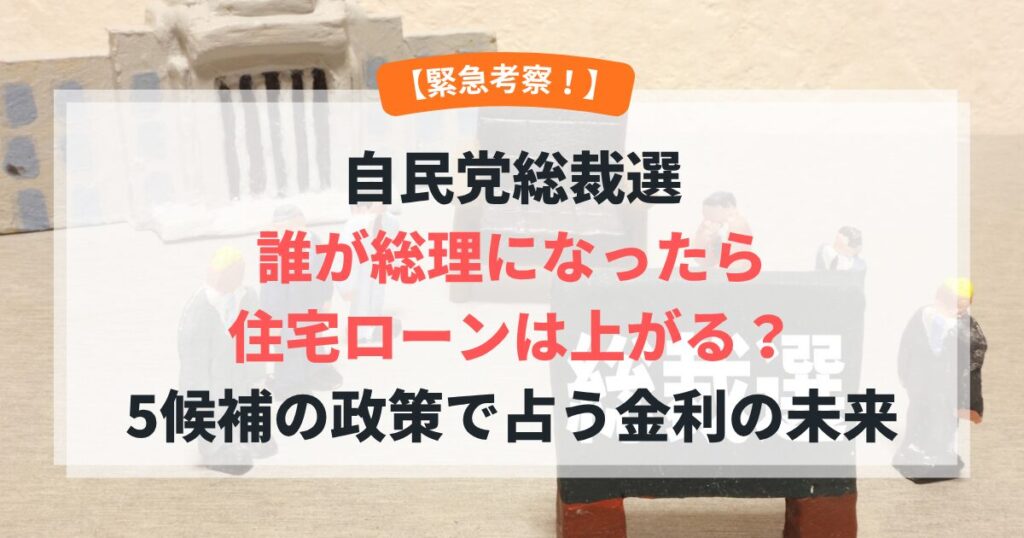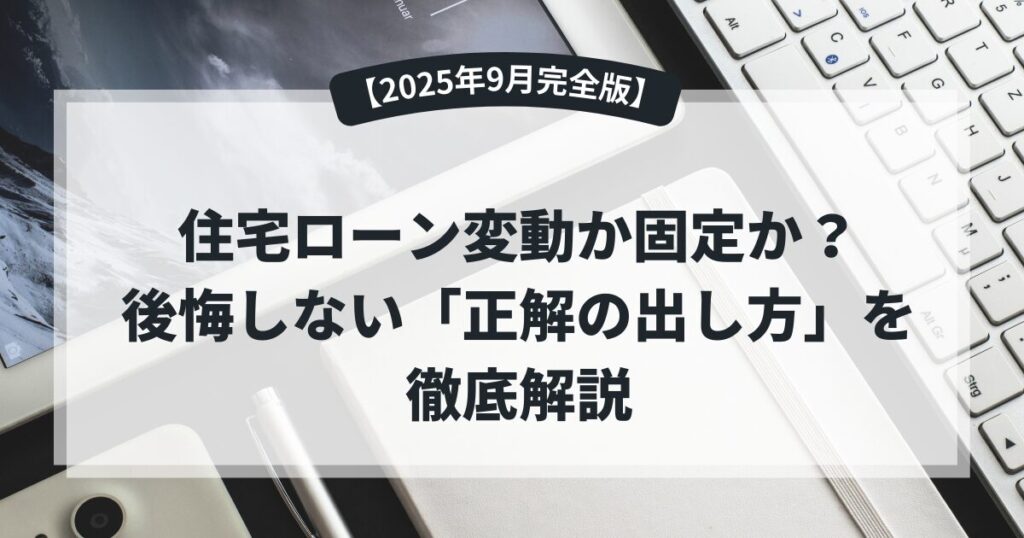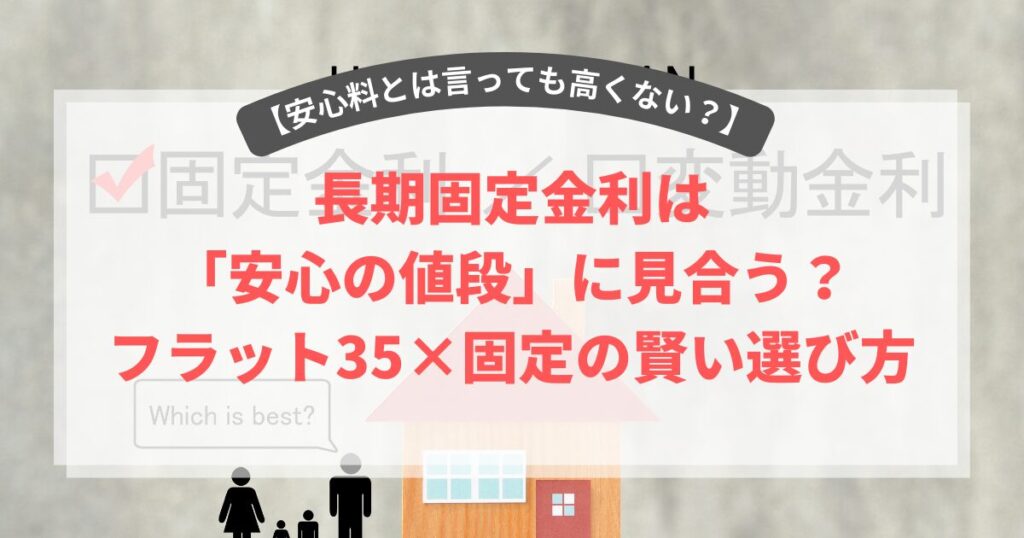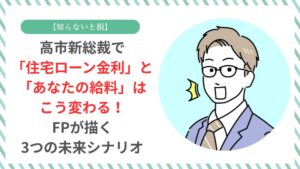【知らないと損】高市新総裁で「住宅ローン金利」と「あなたの給料」はこう変わる!FPが描く3つの未来シナリオ
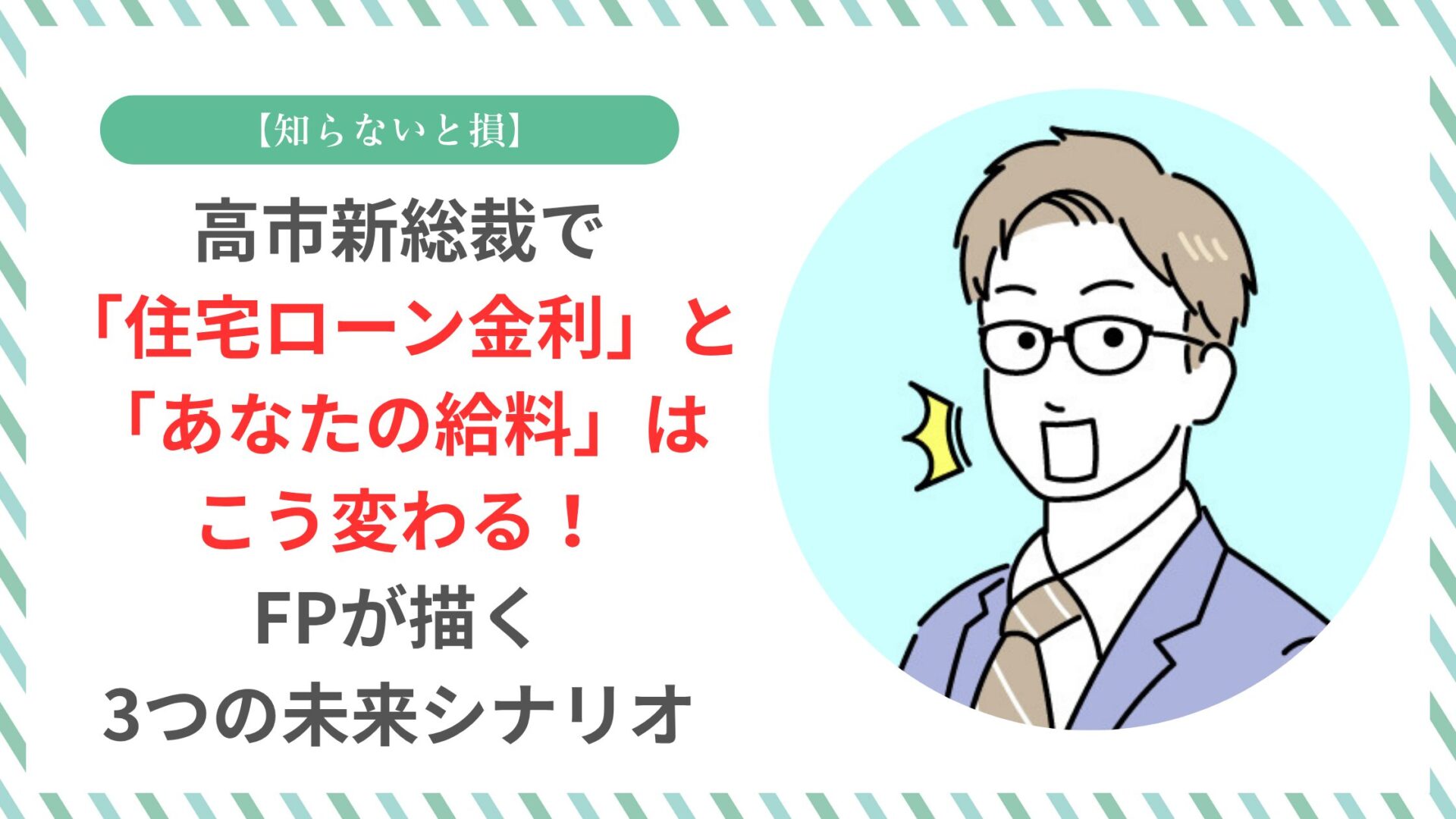
連日流れるニュースを横目に、「へぇ、日本初の女性総理かぁ」
なんて思いつつも、心のどこかで
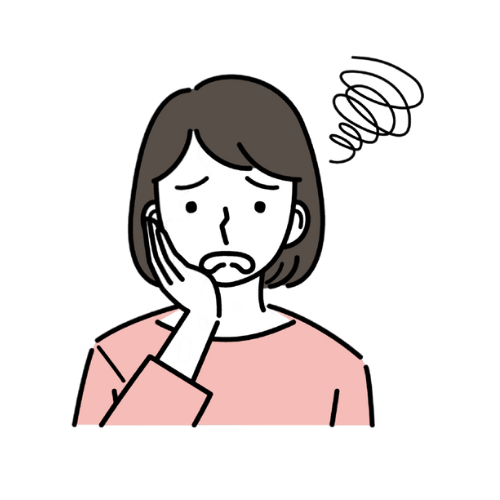
「…で、うちの住宅ローン、どうなっちゃうの?」
という、もっと切実な不安がモクモクと湧き上がってきていませんか?
その感覚、住宅購入を考えるあなたにとって、ものすごく正常で、大切な感覚です。
なぜなら、政治と経済、そして私たちの暮らしは、見えない糸でガッチリと繋がっているから。
まるで会社の新しい社長が「我が社は明日から方針転換だ!」と宣言した時みたいに、現場(=私たち家計)はザワつきますよね。
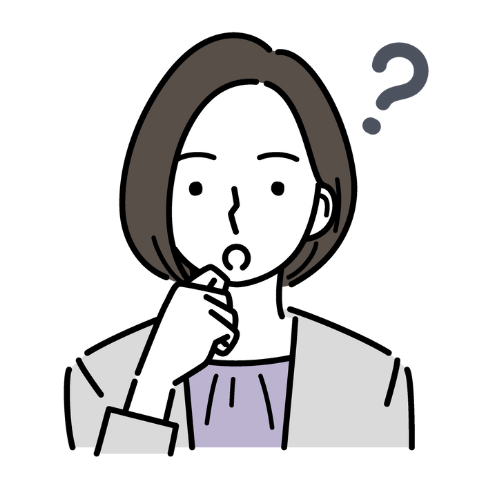
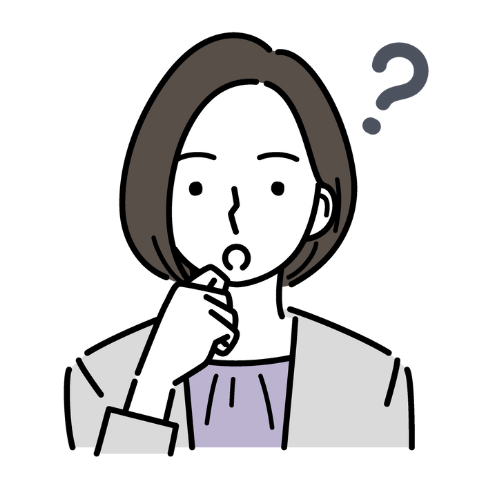
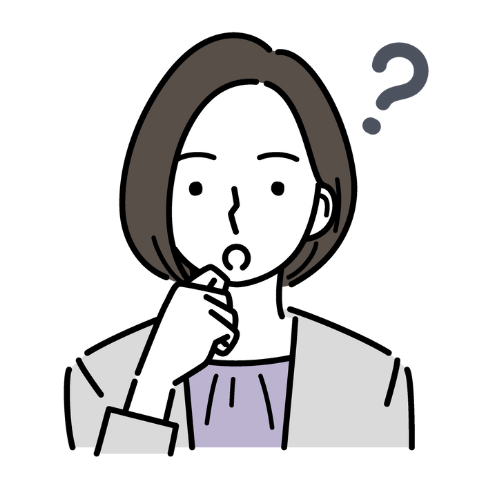
「責任ある積極財政って何?」



「金利は上がるの?下がるの?」
専門用語が飛び交うニュースを見ても、結局我が家がどう動くべきかの答えは見えてきません。
でも、ご安心ください。この記事では、高市新総裁の政策が私たちの住宅ローンに与える影響を、どこよりも分かりやすく「翻訳」してお伝えします。
この記事を読み終える頃には、政治のニュースに一喜一憂することなく、「なるほど、我が家はこの戦略でいこう」と、ドンと構えて未来への一歩を踏み出せるようになっているはずです。
高市新総裁の誕生で、住宅ローン金利はこう動く!


「理屈はいいから、まず結論を教えて!」
きっと多くの方がそう思っていることでしょう。了解いたしました!
高市新総裁の誕生が、私たちの住宅ローン金利に与える影響について、私が考える現時点で最も可能性が高いと予測するシナリオを、変動金利と固定金利に分けてお伝えします。
変動金利への影響:短期的な金利上昇は抑制される可能性
まず、現在多くの方が利用している変動金利についてです。
結論から言うと、高市氏の「責任ある積極財政」という方針は、日銀の利上げペースを緩やかにする方向に作用すると考えられます。
つまり、変動金利が急激に上昇するリスクは、短期的にはむしろ抑制される可能性がある、ということです。
「え、政府がお金をたくさん使うなら、景気が良くなって金利は上がるんじゃないの?」
そう思われるかもしれません。その疑問については、次の章でじっくり解説しますが、今はまず「急激な利上げは起きにくい状況になった」と捉えてください。
固定金利への影響:国債増発懸念で、長期的には上昇圧力も
一方、全期間固定金利やフラット35などの固定金利は、少し違う動きを見せるかもしれません。
固定金利の指標となるのは、主に「長期金利(10年国債利回り)」です。
政府が「積極財政」でお金を使うためには、「国債」をたくさん発行する必要があります。
市場に国債が増えすぎると、その価値が下がり、結果として長期金利が上昇する圧力がかかります。
つまり、「変動金利は当面落ち着きそうだけど、固定金利は将来的にじわじわ上がるかもしれない」というのが、現時点での大きな見立てです。
もちろん、これはあくまで一つのシナリオ。では、なぜこのような予測になるのでしょうか?
次の章で、そのカギを握る高市氏の経済政策の「中身」を、一緒に詳しく見ていきましょう。
【予測】高市新政権下の住宅ローン金利の推移
高市氏の「責任ある積極財政」とは?あなたの給料と金利に直結する3つのポイント


前の章で、「変動金利は抑制、固定金利は上昇圧力」という予測をお伝えしました。
その根拠となるのが、高市氏が掲げる経済政策の柱、「責任ある積極財政」です。
一見すると難しそうな言葉ですが、分解してみると、私たちの家計、特に「お給料」と「住宅ローン金利」にどう影響するのかが見えてきます。
最新の報道を基に、特に重要な3つのポイントに絞って解説します。
ポイント1:目先の物価高対策(ガソリン税減税など)が家計に与える「短期的な恩恵」
まず、高市氏が最優先課題として挙げているのが、国民生活を直撃している物価高への対策です。
具体的には、ガソリン価格を直接引き下げる「トリガー条項の凍結解除」や、電気・ガス代への補助などが公約として議論されています。
【あなたへの影響】
これは、日々の生活で「しんどいな…」と感じている出費が直接的に軽くなることを意味します。スーパーでの買い物や車のガソリン代が少しでも安くなれば、その分家計に余裕が生まれますよね。
住宅ローンを考える上でも、手元に残るお金が増えることは、返済計画を立てる上での安心材料になります。
ポイント2:賃上げ促進策が目指す、経済の「成長の好循環」
次に、物価高に負けないための「賃上げ」の促進です。
物価だけが上がっても、お給料が上がらなければ生活は苦しくなる一方。
そこで、政府が企業の賃上げを税制などで強力に後押しすることで、
「給料が上がる → モノが売れる → 企業の業績が上がる → さらに給料が上がる」
という経済の好循環を生み出すことを目指しています。
【あなたへの影響】
もちろん、すぐに給料が上がるわけではありませんが、国全体として賃上げムードが高まることは、住宅ローンのような長期の返済計画にとって追い風です。
将来の収入増を見込めるのであれば、少し背伸びした物件にも手が届くかもしれませんし、繰り上げ返済の計画も立てやすくなります。
ポイント3:なぜ、この政策が日銀の「利上げ」を牽制することになるのか?そのロジック
ここが最も重要なポイントです。
物価高対策や賃上げには、当然ながら莫大な予算(財源)が必要です。そのために政府は国債を追加で発行するなどして、市場にお金を供給します。
一方、日本銀行(日銀)はこれまで、過度な物価上昇を抑えるために「利上げ(金融引き締め)」のタイミングを慎重に探ってきました。
しかし、政府が「これから経済を良くするためにお金を使いますよ!」という時に、
日銀が「いや、景気が過熱するので金利を上げます!」とブレーキを踏んでしまっては、
アクセルとブレーキを同時に踏むようなもので、政策の効果が打ち消し合ってしまいます。
そのため、高市新総裁の「責任ある積極財政」という強いメッセージは、
と分析できるのです。
これが、変動金利の急騰リスクが短期的には抑制されると予測する最大の理由です。
【参考】高市早苗氏の主要経済政策発言(2025年自民党総裁選)
| 政策分野 | 発言内容・引用 | 文脈・日時 |
| 財政スタンス | 「官民が連携して投資を拡大する、責任ある積極財政へと移行」 | 2025年9月19日、総裁選公約発表会見 |
| 成長戦略 | 「様々なリスクを最小化して先端技術を開花させるための戦略的な財政出動」 | 2025年9月19日、総裁選公約発表会見 |
| 物価高対策 | 「ガソリンと経由の暫定税率を廃止していく」 | 2025年9月19日、総裁選公約発表会見 |
| 財政健全化 | 「財政の健全化が必要ではないといったことは一度もございません」 | 2025年10月4日、総裁就任後記者会見 |
| 金融政策 | 「財政・金融政策の方向性を決めるのは政府だ」 | 2025年9月23日、候補者合同記者会見 |
【シナリオ別】あなたのローンはどうなる?金利タイプごとの影響を徹底予測


高市新総裁の経済政策が、金利の全体像にどう影響するかが見えてきましたね。
では、これを踏まえて、私たち一人ひとりが選ぶ住宅ローンの金利タイプごとに、どのような影響が考えられるのか。
そして、どう向き合っていけばいいのかを、具体的なシナリオとして見ていきましょう。
変動金利で借りる(借りている)あなたへ:当面は低金利の恩恵が続く?ただし「将来の利上げ」への備えは必須
変動金利を選んでいる、あるいは検討しているあなたにとっては、短期的にはポジティブな状況が続く可能性が高いです。
前述の通り、政府の積極財政が日銀の利上げを牽制するため、変動金利の基準となる短期金利は、急激には上がりにくいと考えられます。
これは、毎月の返済額が当面は低く抑えられることを意味し、家計にとっては大きなメリットです。
ただし、「低金利が永遠に続くわけではない」という点は、肝に銘じておく必要があります。
物価高や賃上げが定着し、経済の好循環が生まれれば、いずれ日銀は金利の正常化(=利上げ)に踏み切ります。
その「いつか来る日」に備えて、金利が低い今のうちに「つもり貯金」(もし金利が1%上がったら…と仮定して、その差額分を貯蓄に回すこと)や、余裕資金での繰り上げ返済を計画的に進めておくことが、未来の自分を助ける最強の防衛策になります。
固定金利で借りる(検討中の)あなたへ:今のうちに借りるのが得?長期金利の動向に注目
一方、これから固定金利での借り入れを検討している方は、少しスピード感が求められるかもしれません。
積極財政のための国債増発は、固定金利の指標となる長期金利の上昇圧力となります。
つまり、今後、固定金利は段階的に引き上げられていく可能性が十分にあるということです。
もしあなたが、「将来の金利上昇を心配することなく、返済額を確定させて安心して暮らしたい」と考えるタイプなら、金利がまだ低水準にある今のうちに借り入れを実行し、金利を確定(ロック)させてしまうのが賢明な判断と言えるかもしれません。
まさに、「安心を買う」という固定金利のメリットを最大限に活かすタイミングとも言えます。
「フラット35」はどうなる?国の政策が金利に与える影響


住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の「フラット35」も、基本的には長期金利の動向に連動します。
そのため、民間銀行の固定金利と同様に、将来的には金利が上昇していく可能性があります。
ただし、フラット35は国の政策と密接に関わっており、「子育てプラス」のような政策的な金利引き下げ制度が拡充される可能性もゼロではありません。
高市新総裁が子育て支援にも力を入れると公言しているため、今後の制度改正のニュースにはアンテナを張っておくと良いでしょう。
不透明な時代に、私たちが今すぐ取るべき3つのアクション


政治がどう動くか、金利がどうなるか…。
未来を正確に予測することは誰にもできません。
しかし、どんな未来が来ても慌てないように「備える」ことは、私たち自身の手で今すぐ始められます。
情報に振り回されて不安になるだけで終わらせないために、FPとして強くお勧めする3つの具体的なアクションをご紹介します。
アクション1:まずは「我が家の家計体力」を正確に把握する
新しい総裁の政策や金利のニュースを見て不安になるのは、「我が家がその変化に耐えられるのか」が分からないからです。
お化けと一緒、相手の正体が分からないと、恐怖はどんどん大きくなりますよね。
まずは、現在の家計を「見える化」し、自分たちの体力を正確に把握することから始めましょう。
- 毎月の収入はいくらか?(手取り額で)
- 毎月の支出はいくらか?(固定費と変動費に分けて)
- 毎月いくら貯蓄できているか?
- 現在の貯蓄総額はいくらか?
面倒に感じるかもしれませんが、一度これをやっておくだけで、



「うちは毎月〇万円までなら返済額が増えても大丈夫」
「あと〇年で貯蓄が〇〇万円になるな」
という具体的な基準が手に入ります。
これが、あらゆる判断の土台となる最も重要なステップです。
アクション2:変動・固定の両方のパターンでシミュレーションしてみる
家計の体力が分かったら、次は金融機関のウェブサイトなどで公開されている住宅ローンシミュレーターを使ってみましょう。
▶▶マイホームお金の相談窓口の公式LINE登録で高性能住宅ローンツールもプレゼントしています!今すぐ登録!
ここで大切なのは、「変動金利で借りた場合」と「固定金利で借りた場合」の両方のパターンを試してみることです。
この作業をすることで、



「金利が〇%までなら変動の方が得だな」
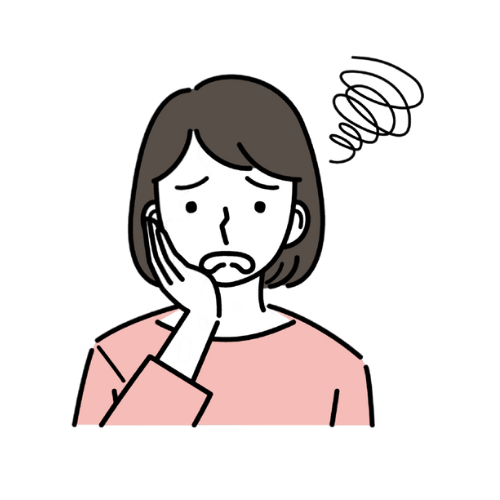
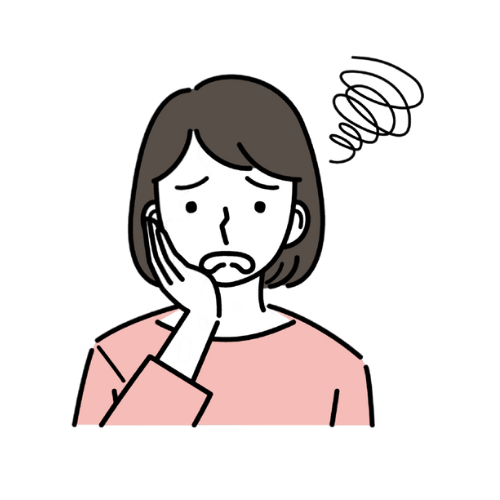
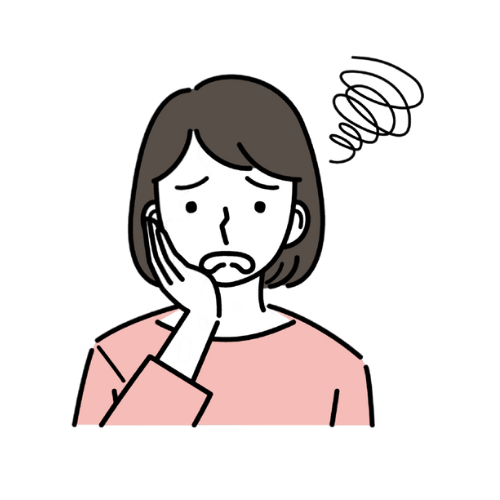
「このくらいの安心料なら、固定にした方が精神的に楽かも」
といった、自分たちの価値観に基づいた判断軸が明確になります。
アクション3:信頼できるプロ(FPや金融機関)に相談し、最新情報を得る
家計を把握し、自分たちなりのシミュレーションを終えたら、最後は専門家の客観的な視点を取り入れましょう。
特に、特定の金融機関に属していない独立系のFPは、中立的な立場であなたに最適なプランを一緒に考えてくれます。
自分たちだけでは気づかなかったリスクや、もっと有利なローンの選択肢を提示してくれることもあります。
また、刻一刻と変わる政治や経済の最新情報を踏まえた上で、
「あなたの家庭の場合は、こう動くのがベストですよ」
と、具体的なアドバイスで背中を押してくれます。
不透明な時代だからこそ、一人で抱え込まず、信頼できるプロを味方につけることが、後悔しないための最も賢い選択と言えるでしょう。
【シミュレーション】金利上昇による毎月の返済額の変化
※前提条件:借入額3,500万円、返済期間35年、元利均等返済
ライフプランニングからまずは学びたい方はこちらん記事がおススメ
-


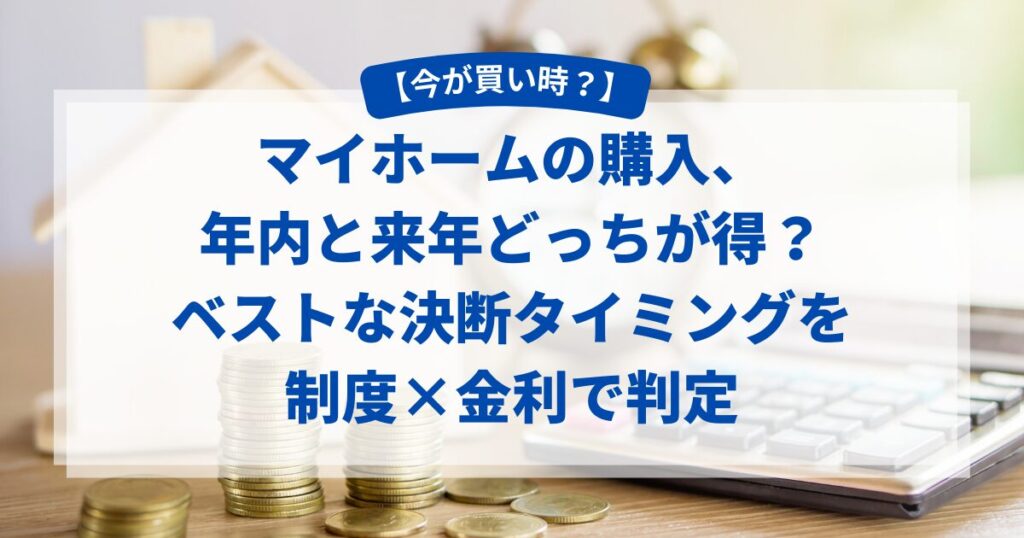
【今が買い時?】マイホームの購入、年内と来年どっちが得?ベストな決断タイミングを制度×金利で判定
「そろそろマイホームが欲しいな…」と、スマホで物件情報を見るのが日課になってきた今日この頃。 素敵な間取りに胸を躍らせる一方で、ふと目に入る「住宅ローン金利、上がるかも?」「控除制度、2025年までがお得?」といったニュースに、急に心がかき乱… -


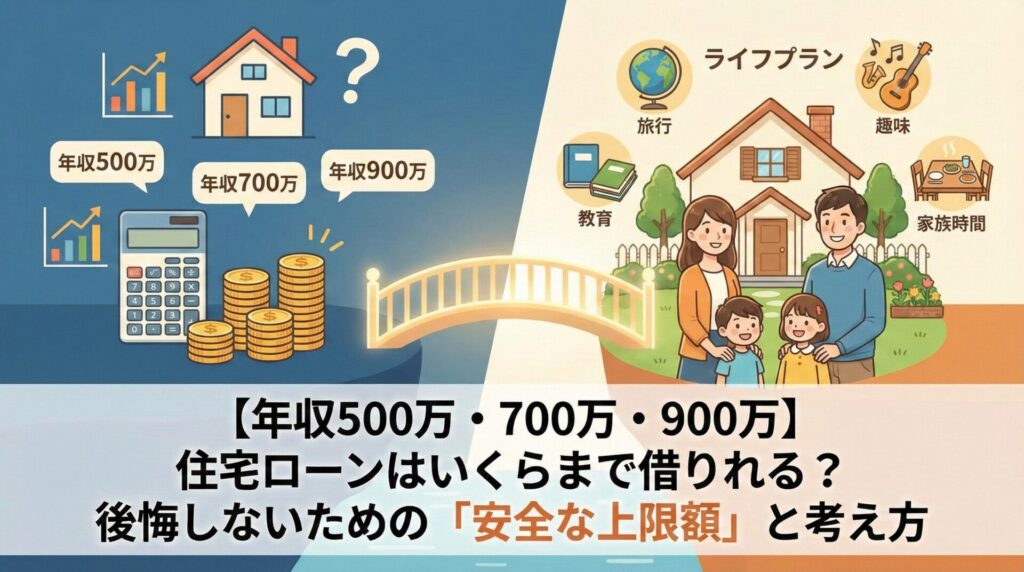
【年収500万・700万・900万】住宅ローンはいくらまで借りていい?後悔しないための「安全な上限額」と考え方
「そろそろマイホームが欲しいな…」 そう思って色々調べ始めると、必ず目にするのが 「年収の〇倍までOK」 「返済負担率は25%以内で」 といった、もっともらしい数字の数々。 でも、心の中でこう思いませんか? 「その数字、本当にうちの家族に当て… -


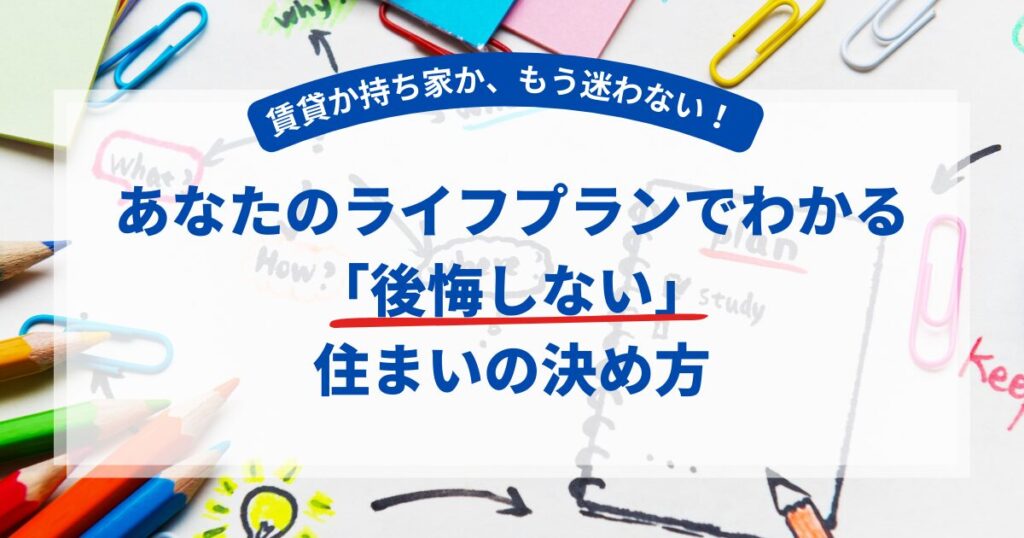
【FP解説】賃貸か持ち家か、もう迷わない!あなたのライフプランでわかる「後悔しない」住まいの決め方
「そろそろ家、どうする?」 夫婦の会話、友人との雑談、ふとした瞬間に頭をよぎるこの言葉。 家賃を払い続けるのは何だかもったいない気がするけど、いきなり何千万円ものローンを背負うなんて、想像しただけで足がすくむ…。 周りを見ればマイホームを買…
忘れてはいけないリスクシナリオと、私たちの「守りの戦略」


さて、ここまで高市新総裁の政策がもたらすであろう、メインシナリオについて解説してきました。
しかし、計画というものは常に「最悪の事態」を想定しておくことで、より強固なものになります。
いわば、RPGで回復アイテムを満タンにしてからボスに挑むようなものですね。
ここでは、私たちが考えておくべきリスクシナリオと、どんな状況でも家計を守り抜くための「守りの戦略」についてお伝えします。
もし、急激な円安や物価高が続いたら?
まず考えられるのが、政府の積極財政が市場の信認を失い、想定以上の円安や物価高(インフレ)を招いてしまうシナリオです。
こうなると、輸入品の価格がさらに高騰し、日々の生活コストが上昇。実質的にお給料の価値が目減りしてしまい、住宅ローンの返済がじわじわと家計を圧迫し始めます。
また、この状況では日銀も物価を抑えるために、想定より早く、そして高い利上げに踏み切る可能性が出てきます。
これは特に、変動金利でローンを組んでいる方にとっては直接的な脅威となります。
どんな状況でも後悔しないための「家計の防衛ライン」の作り方
こうしたリスクシナリオに直面しても、慌てず、そして家計を破綻させないために、私たちは「守りの戦略」として「家計の防衛ライン」を築いておく必要があります。
その要は、以下の3つです。
- 生活防衛資金を確保する:
まず何よりも優先すべきは、万が一の事態に備える現金です。会社の給料が下がったり、病気で働けなくなったりしても、最低半年~1年間は生活できるだけの「生活防衛資金」を、住宅ローンや投資とは別の口座に確保しておきましょう。
これがあるだけで、精神的な安心感が全く違います。 - 借入額は「上げられる年収」ではなく「下がっても返せる額」で決める:
住宅ローンを組む際、ついつい「今の年収ならこれくらい借りられる」と上限額で考えがちです。
しかし、守りの戦略では発想を逆転させます。「将来、年収が100万円下がっても、無理なく返済を続けられるのはいくらか?」という視点で借入額を設定するのです。この一手間が、未来の家計を救います。 - インフレに強い資産を育てる:
物価が上がり続けるということは、現金の価値が下がり続けるということです。
生活防衛資金を超える余裕資金については、新NISAなどを活用して、株式や不動産といったインフレに強い資産に少しずつ振り分け、育てていく視点も重要です。
これは守りであると同時に、資産を増やしていく「攻めの戦略」にも繋がります。
政治や経済がどう動こうと、この「防衛ライン」さえしっかり固めておけば、あなたの家族はどっしりと構えていることができます。
よくある質問
- Q1. 高市新総裁の政策で、住宅ローン減税は拡充されますか?
-
減税の拡充は公約の柱ではなく、現時点では不透明です。ただし、経済対策の一環として、子育て世帯向けの支援などが拡充される可能性はあります。年末の税制改正大綱のニュースは必ずチェックしましょう。
- Q2. 今から家探しを始める場合、何に一番気をつけるべきですか?
-
政治の動向に一喜一憂しすぎないことです。金利や制度も重要ですが、ご家族のライフプラン(子供の進学など)に合ったタイミングが最優先です。まずは冷静に、自分たちの計画を立てることから始めましょう。
- Q3. 政治が不安定な時期は、頭金を多く入れた方が安全ですか?
-
一概には言えません。頭金を多く入れれば返済は楽になりますが、手元の現金が減り、急な物価高に対応できなくなるリスクも。万一に備える「生活防衛資金」を最優先で確保し、残りの余裕資金で判断しましょう。
- Q4. 賃貸と持ち家、この状況だとどちらが有利ですか?
-
どちらが有利かは、個々の価値観とライフプラン次第です。ただし、インフレが進むと現金の価値が目減りするため、「不動産」という資産を持つ持ち家の有利性が相対的に高まる、という考え方もできます。
- Q5. ニュースで見る「長期金利」の数字はどう見ればいいですか?
-
長期金利が上昇傾向なら「固定金利も上がりそう」、低下傾向なら「固定金利も下がりそう」と捉えておけばOKです。住宅ローン選びでは、この長期金利のトレンドを意識すると、大きな流れを掴みやすくなります。
まとめ
高市氏の積極財政は日銀の利上げを牽制するため、変動金利が急騰するリスクは短期的には低いと予測されます。ただし、将来の利上げに備えた「つもり貯金」や繰り上げ返済の計画は必須です。
積極財政のための国債増発懸念から、固定金利の指標となる長期金利には上昇圧力がかかります。将来の返済額を確定させたい方は、金利が低いうちに借り入れを実行するのが賢明かもしれません。
物価高対策や賃上げ促進といった政策が、なぜ金利に影響するのか。そのロジックを理解することで、ニュースに振り回されず、冷静に我が家の戦略を立てることができます。表面的な情報に踊らされないようにしましょう。
どんなに政治や経済が動いても、全ての判断の土台は「我が家の家計体力」と「ライフプラン」です。まずは現状を把握し、シミュレーションを行い、自分たちの価値観に基づいた判断軸を持つことが最も重要です。
未来のことは誰にも分かりません。急な円安や物価高といったリスクに備え、「生活防衛資金の確保」と「無理のない借入額設定」という家計の防衛ラインを築いておくことが、後悔しないための最大の保険となります。