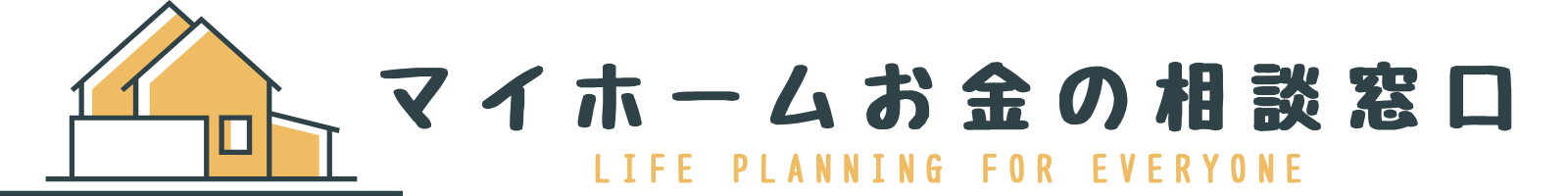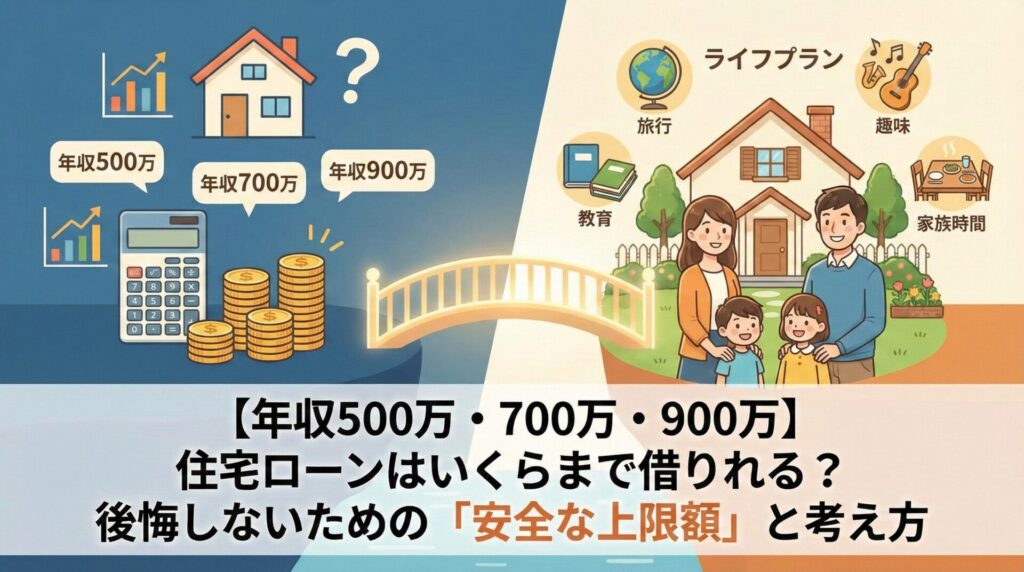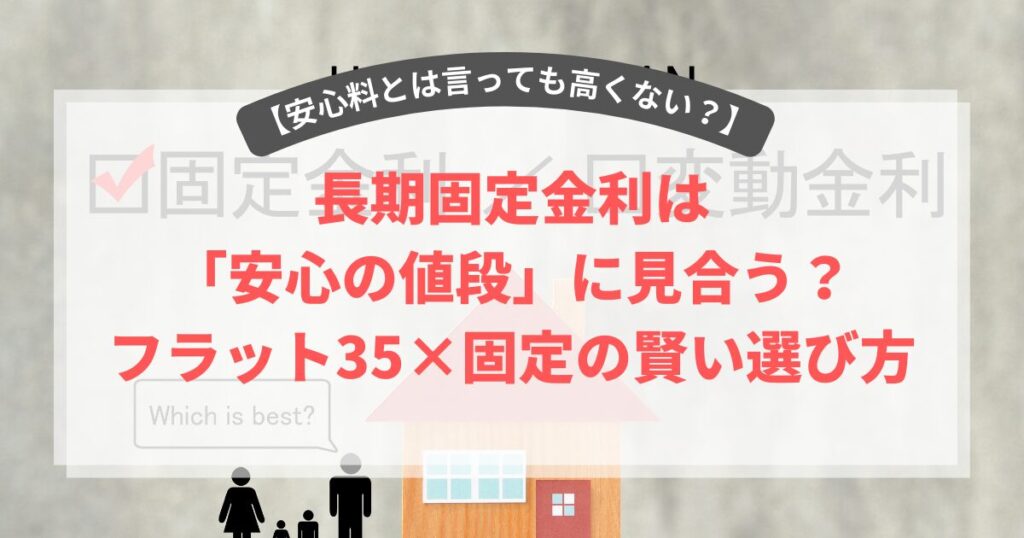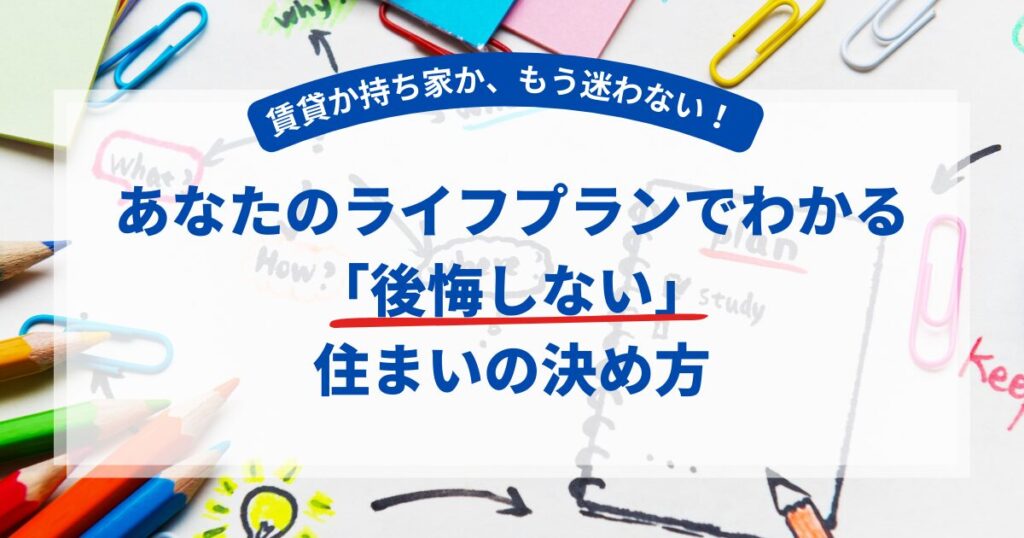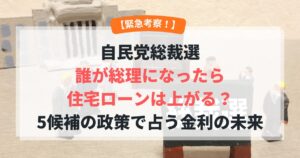【緊急考察!】自民党総裁選、誰が総理になったら住宅ローンは上がる?5候補の政策で占う金利の未来
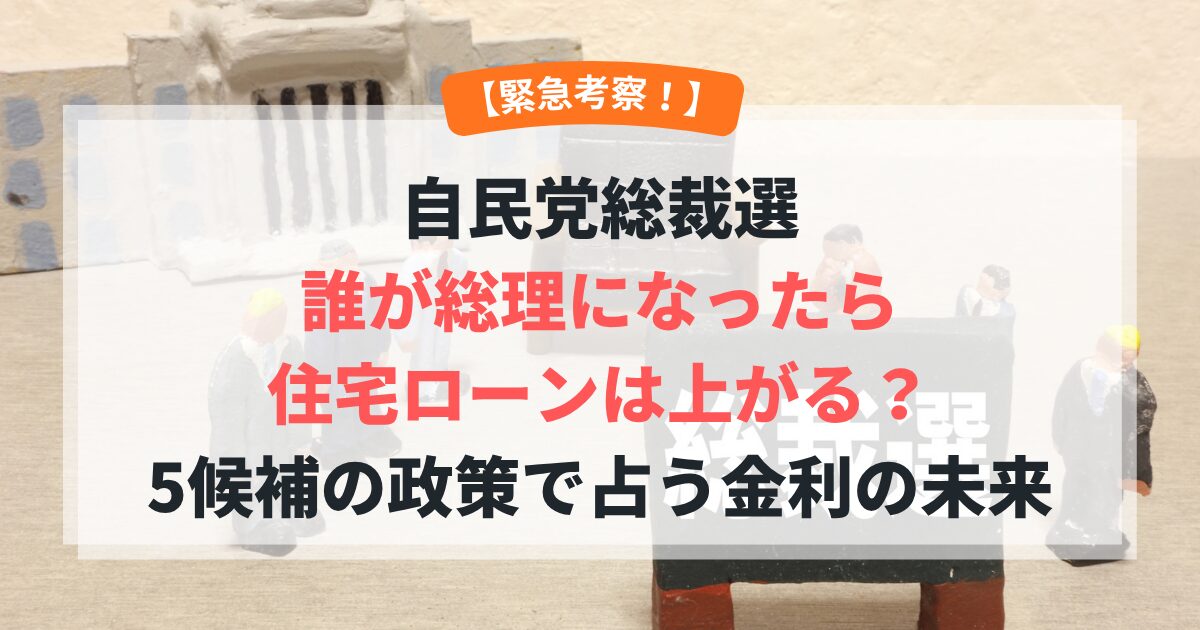
ニュースで連日報道される「自民党総裁選」。
いよいよ明日ですね!
5人の候補者の顔ぶれを見て、「正直、誰がなっても私たちの生活なんて変わらないでしょ…」なんて、少し冷めた気持ちで見ていませんか?
その気持ち、痛いほどよく分かります。
難しい政治や経済の話は、なんだか自分とは遠い世界のことのように感じますよね。
ちなみに候補者は以下の5名の方々です。
- 小林鷹之元経済安全保障相
- 茂木敏充前幹事長
- 林芳正官房長官
- 高市早苗前経済安保相
- 小泉進次郎農相
でも、もし。
次の総理大臣が誰になるかで、あなたがこれから35年間払い続ける住宅ローンの「毎月の返済額」が、数千円、いや数万円も変わってしまうかもしれないとしたら・・・??
ご安心ください。この記事は、難しい専門用語や政策論争は一切なし!
私はマイホーム購入サポートを行うFPなので次の一点に全集中してお伝えします。
5人の候補者があなたのマイホーム計画にどう影響するのか、最も重要な「住宅ローン金利」という一点に絞って、世界一わかりやすく解説します。
総理大臣が変わることは、いわば家計の「天気予報」が大きく変わるようなもの。
「晴れ(低金利・好景気)」が続くのか、それとも「傘(家計の防衛策)」の準備が必要な「雨模様(金利上昇)」になるのか。
事前に予報をチェックして、どんな天候になっても慌てないように備えておきたいですよね。
住宅購入に精通したファイナンシャルプランナー(FP)として、不確定な未来に振り回されず、あなたとご家族が心から納得してマイホーム計画を進めるための「羅針盤」となる情報だけを、丁寧にお届けしますね。
【結論ファースト】5人の候補者を2つのタイプにざっくり分類!金利への影響は?

「候補者が5人もいて、それぞれの政策なんて覚えられない!」
ご安心ください。まず、住宅ローン金利への影響という視点で見れば、5人の候補者はたった2つのタイプにざっくりと分けることができます。
それは、金利を上げることに対して「ブレーキをかけたい派」と「アクセルを踏む準備がある派」です。
専門家の間では少し難しい言葉で呼ばれますが、ここでは分かりやすく以下のように名付けますね。
- タイプA: 金利上昇にブレーキをかけたい「リフレ派」候補
- タイプB: 経済の状況次第で金利上昇を容認する「正統派」候補
あなたが住宅ローンを変動金利で借りている、あるいはこれから借りる予定なら、特に注目すべきは「リフレ派」の候補者が総理になるかどうか、という点です。
なぜなら、このタイプの候補者は「金利を低く抑えること」を非常に重視する傾向があるからです。
逆に「正統派」の候補者は、経済全体のバランスを重視するため、景気が良くなってきたと判断すれば、金利を上げる(正常化する)という選択肢も当然あり得ると考えています。
今回の総裁選では、5人の候補者は以下のように分類できます。
まずは「金利を上げたくないのが高市さん、それ以外の4人は状況次第で上げる可能性があるんだな」という、この大きな違いだけを頭に入れておけばOKです。
次の章からは、なぜ総理大臣が変わると金利が動くのか、そして各候補者が具体的にどのような影響を与えそうなのかを、さらに詳しく見ていきましょう。
「リフレ派」ってなに?
ニュース解説などでよく聞く「リフレ派」。
これは「リフレーション政策」を支持する人たちのことを指します。なんだか難しそうですが、要するに「世の中の景気が良くなるまで、国や日本銀行が市場にお金をどんどん供給して(金融緩和)、ちょっとしたインフレ(物価上昇)を起こすべきだ!」と考える人たちのことです。
物価が上がれば、企業の売上も、私たちの給料も上がるはず。そのためには、金利を低く抑えて、企業がお金を借りやすくしたり、私たちが住宅ローンを組みやすくしたりすることが重要だと考えているのです。
そもそも、なぜ総理大臣が変わると住宅ローン金利が動く可能性があるの?

「新しい総理大臣が決まること」と「我が家の住宅ローン金利」。
一見、何の関係もなさそうに思えますよね。しかし、実はこの二つ、目には見えない太いパイプで繋がっているのです。
その繋がりを、ものすごくシンプルに表現すると以下のようになります。
新しい総理大臣の「考え方」
日本銀行(日銀)への「態度」が変わる
世の中のお金の流れを調整する「金融政策」が変わる
銀行が私たちに貸し出す「住宅ローン金利」が変わる
これだけだと、まだ少し難しいかもしれませんね。
そこで、「家庭」にたとえて考えてみましょう。

- お父さん(政府・総理大臣):
「子どもの教育費もかかるし、将来のために投資もしたい!そのために、どんどんお金を使っていこう!」と考える「積極財政タイプ」。家計の成長を第一に考えます。 - お母さん(日本銀行):
「気持ちは分かるけど、使いすぎると将来の借金が大変よ。まずは無駄遣いをなくして、家計を安定させましょう」と考える「堅実タイプ」。家計全体のバランスと安定を重視します。
この家庭では、お母さん(日銀)が家計のお財布(金融政策)を握っています。
お父さん(総理大臣)がどんなに「お金を使いたい!」と言っても、最終的にお財布のヒモを緩めるかどうかは、お母さん(日銀)の判断次第。
これを「日銀の独立性」と言います。
しかし、新しい総理大臣が「お母さんのやり方は尊重するよ」というスタンスなのか、それとも「いや、もっとお父さんの言うことを聞いて、どんどんお金を使ってほしい!」とプレッシャーをかけるタイプなのかで、お母さん(日銀)の判断に影響が出ないとは言い切れません。

皆さんのご家庭の夫婦の関係性はどんな感じですか?
総理大臣の経済に対する考え方が、日銀のトップ人事や、政府が発信するメッセージを通じて、間接的に金融政策の方向性を左右する可能性があるのです。
そして、その金融政策の大きな柱の一つが「金利」のコントロール。
日銀が「金利を上げる」と決めれば、銀行は高い金利でお金を調達することになるため、私たちが借りる住宅ローンの金利も上がります。
逆に「金利を下げる」と決めれば、住宅ローン金利も下がる、というわけです。
このように、総理大臣の交代は、巡り巡って私たちの住宅ローン金利にまで影響を及ぼす可能性があるのです。
【ひとこと解説】「日本銀行(日銀)」ってどんなところ?
日本銀行、通称「日銀(にちぎん)」は、日本で唯一「お札(日本銀行券)」を発行できる銀行であり、日本の経済全体の安定を担う「銀行のなかの銀行」です。主な役割は2つ。
一つは、モノの値段が上がりすぎたり下がりすぎたりしないように見張る「物価の安定」。
もう一つは、銀行同士のお金のやり取りがスムーズにいくように全体を整える「金融システムの安定」。
住宅ローン金利を左右する「政策金利」を決めるのは、この日銀の最も重要な仕事の一つなのです。
【候補者別】あなたの住宅ローンへの影響は?政策スタンスを徹底比較!


さて、ここからはいよいよ、5人の候補者それぞれが総理大臣になった場合、あなたの住宅ローンにどのような影響が考えられるのか、一人ひとり見ていきましょう。
先ほど分類した「リフレ派」と「正統派」という大きな枠組みを思い出しながら読み進めてみてください。
【リフレ派】高市早苗 氏:「とにかく金利を上げたくない」強い意志
今回の候補者の中で、唯一の「リフレ派」である高市早苗氏。
高市氏の金融政策における最大の特徴は、「金融緩和を継続し、金利を低く抑えるべき」という非常に強い意志を持っている点です。
これは、現在変動金利で住宅ローンを借りている、あるいはこれから借りようとしている方にとっては、最も心強いメッセージと言えるかもしれません。
- もし高市総理になったら…
- 変動金利への影響:
政府から日銀に対し、金融緩和を維持するよう強いメッセージが発信される可能性が高まります。これにより、日銀は利上げに対して極めて慎重になり、変動金利の基準となる短期金利は、当面の間、現在の低い水準で維持される可能性が高いでしょう。 - 固定金利への影響:
一方で、注意も必要です。市場が「高市総理のもとでは、国の借金(国債)がさらに増えるかもしれない」と判断した場合、将来の財政を懸念して長期金利が上昇する可能性があります。長期金利は固定金利の基準となるため、「変動は低いままでも、固定は上がる」という現象が起こるかもしれません。
- 変動金利への影響:
【正統派・財政規律重視】小泉進次郎 氏・林芳正 氏:「経済の体調次第で利上げもやむなし」
次に、正統派の中でも「財政規律」を重視するお二人です。
たとえるなら、「家計の将来を考えて、無駄な借金は少しずつでも返していきましょう」という考え方に近いスタンスです。
そのため、日銀の独立性を尊重し、日本経済が十分に回復したと判断すれば、金利を正常な状態に戻す(利上げする)ことを容認すると考えられます。
- もし小泉総理・林総理になったら…
- 変動金利への影響:
急激な利上げで経済を冷やすことは考えにくいため、利上げのペースは非常に緩やかになるでしょう。市場との対話を重視し、予測可能な形で少しずつ金利が上昇していく展開が想定されます。 - 固定金利への影響:
財政規律を重視する姿勢は、市場からの信認につながりやすいため、長期金利は比較的安定しやすいと考えられます。つまり、金利の先行きが読みやすく、安定した経済運営が期待されるのがこのタイプの特徴です。
- 変動金利への影響:
【正統派・成長重視】茂木敏充 氏・小林鷹之 氏:「経済成長を優先しつつ、利上げは慎重に」
最後に、同じ正統派の中でも「経済成長」をより重視するお二人です。
こちらは「まずは家計の収入(給料)を増やすことが最優先。借金返済はそのあとだ」という考え方に近いスタンスです。
利上げを容認する点では先の二人と同じですが、経済成長への影響をより慎重に見極めるため、利上げのタイミングはさらに遅くなる可能性があります。
- もし茂木総理・小林総理になったら…
- 変動金利への影響:
景気の腰折れを非常に警戒するため、日銀が利上げを判断するハードルは少し高くなるかもしれません。小泉氏・林氏のケースよりも、金利上昇のペースはさらに緩やかになる可能性があります。 - 固定金利への影響:
経済成長を重視する政策は、市場から「将来的に景気が良くなる」と受け取られれば長期金利は緩やかに上昇しますが、一方で「財政は大丈夫か?」と見られると金利が不安定になる側面も。金利の方向性は、その時々の経済状況や政策の具体的内容によって左右されやすいと言えるでしょう。
- 変動金利への影響:
【ひとこと解説】「財政規律」ってどういう意味?
ニュースでよく聞く「財政規律(ざいせいきりつ)」。これも家庭にたとえると分かりやすいです。これは「収入の範囲内でやりくりして、無駄な借金を増やさないようにしましょうね」という考え方のこと。
国の収入(税収など)と支出(公共事業や社会保障など)のバランスを健全に保とう、という姿勢を指します。財政規律を重視する、ということは、国の借金(国債)をこれ以上増やさないように、補助金や減税といった「大盤振る舞い」には慎重になる、というメッセージでもあるのです。
住宅ローン控除や補助金の行方は?各候補者の「お財布事情」に関する考え方
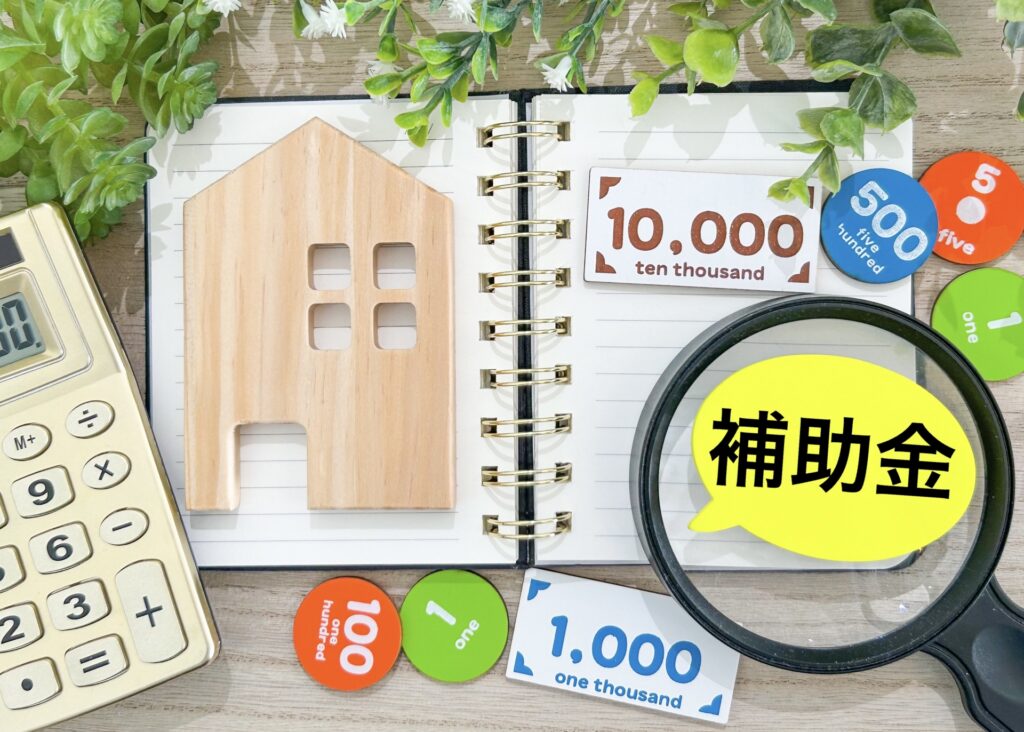
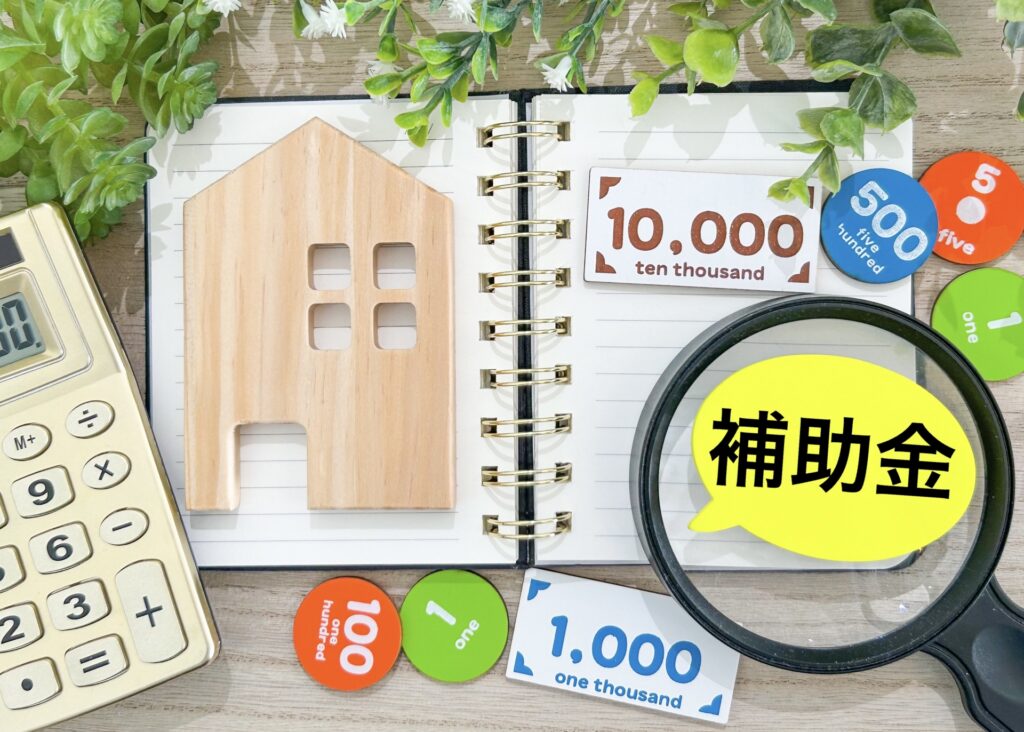
住宅ローン金利と並んで、マイホーム計画の資金繰りで大きな助けとなるのが「住宅ローン控除」や「子育てエコホーム支援事業」といった、国からの補助金・減税制度ですよね。
新しい総理大臣の「国のお財布(財政)」に対する考え方によって、これらの制度が今後も続くのか、それとも見直されてしまうのか、その方向性が大きく変わる可能性があります。
ここでも、候補者を2つのタイプに分けて見ていきましょう。
- タイプA:「未来のために、今お金を使おう!」積極財政(せっきょくざいせい)派
- タイプB:「まずは借金返済を考えよう」財政規律(ざいせいきりつ)派
家庭にたとえるなら、「子どもの将来の可能性を広げるためなら、教育ローンを組んででも塾や習い事に投資したい」と考えるのがAタイプ。
「いや、まずは今ある家のローンをしっかり返していくことが、家族の将来の安心につながる」と考えるのがBタイプです。
【積極財政派】高市早苗 氏
高市氏は、国の経済を成長させるためには、政府が積極的にお金を使うべきだという「積極財政」の考え方を明確に打ち出しています。
- もし高市総理になったら…
- 景気対策や国民の生活支援を重視するため、住宅ローン控除や各種補助金は、現状維持、あるいは拡充される可能性が十分に考えられます。特に、子育て支援に繋がるような住宅取得支援策は、手厚くなることが期待できるかもしれません。
【財政規律派】小泉進次郎 氏・林芳正 氏・茂木敏充 氏・小林鷹之 氏
一方、他の4人の候補者は、国の借金が膨らみ続けている現状に危機感を持っており、無駄な支出は抑えるべきだという「財政規律」を重視する点で共通しています。
もちろん、経済成長や国民生活の安定も重要だと考えていますが、そのための財源はきちんと確保すべき、というスタンスです。
- もしこの4氏のいずれかが総理になったら…
- 現在のような大規模な補助金や手厚い減税制度は、将来的に見直される可能性があります。「いつまでも続けられる制度ではない」という議論が活発になり、控除額が縮小されたり、補助金を受け取るための所得制限が今よりも厳しくなったり、といった変更が考えられます。
- ただし、国民の支持を失うような急激な制度変更は考えにくく、仮に見直す場合でも、数年間の猶予期間を設けるなど、ソフトランディングを目指すでしょう。
- 現在のような大規模な補助金や手厚い減税制度は、将来的に見直される可能性があります。「いつまでも続けられる制度ではない」という議論が活発になり、控除額が縮小されたり、補助金を受け取るための所得制限が今よりも厳しくなったり、といった変更が考えられます。
このように、誰が総理になるかで、数年後の私たちの家計を支えてくれる制度のあり方が、大きく変わってくる可能性があるのです。
【FPからの提言】誰が総理になっても後悔しない!今すぐやるべき3つの資金計画
ここまで、各候補者の政策が私たちの住宅ローンに与える影響について見てきました。
「〇〇さんが総理になったら金利が上がりそう…」「△△さんなら補助金が続きそう…」など、色々と考えてしまいますよね。
しかし、最も重要なことをお伝えします。
それは、「誰が総理大臣になっても、あなたの家計が揺らがないような『守りの戦略』を立てておくこと」です。
政治の未来を正確に予測することは誰にもできません。
だからこそ、どんな未来が来ても「我が家は大丈夫」と心から思える、具体的な3つの自己防衛策を今すぐ始めましょう。
対策①:金利が2%上がっても耐えられる「安全な借入額」を再確認する
最も重要なのが、この「安全な借入額」の確認です。
銀行が「ここまで貸せますよ」という上限額と、あなたが「無理なく返せる額」は全く違います。
特に、どの候補者が総理になっても、日本の金利が今後「上がる方向」にあることは専門家の間でも共通認識となっています。
そこで、一つの目安として「もし今の変動金利が2%上昇しても、毎月の返済を続けられるか?」というストレステストを必ず行いましょう。
「年収の〇倍」といった一般的な基準ではなく、ご自身の家族構成や大切にしたいライフイベント(旅行、教育、趣味など)から逆算して、未来の金利上昇分をあらかじめ見込んだ、本当の意味で安全な借入額を把握しておくこと。
これこそが、最強の防衛策です。
▼より詳しく知りたい方はこちらの記事へ
ご自身の年収やライフプランに合わせた、より具体的な「安全な借入額」の計算方法や考え方については、こちらの記事でステップごとに徹底解説しています。
対策②:変動金利だけでなく「固定金利(フラット35)」も選択肢に入れて比較検討する
「変動金利の低さは魅力的だけど、やっぱり将来が不安…」
今回の総裁選のニュースを見て、そう感じた方も多いのではないでしょうか。
金利上昇の可能性がある不透明な時代には、「将来35年間の返済額がずっと変わらない」という固定金利の安心感は、以前にも増して大きな価値を持ちます。
特に、国の制度である「フラット35」は、民間の銀行ローンにはない独自の基準や、子育て世帯への優遇制度(フラット35子育てプラス)など、知っておくべきメリットがたくさんあります。
「変動金利ありき」で考えるのではなく、一度は固定金利、特にフラット35も選択肢のテーブルに乗せて、冷静に比較検討してみることを強くお勧めします。
▼より詳しく知りたい方はこちらの記事へ
「固定金利の安心料っていくら?」「フラット35と銀行の固定ローンは何が違うの?」といった疑問にお答えする詳細な比較解説は、こちらの記事をご覧ください。
対策③:最新の情報は信頼できる専門家(FPなど)に相談する
政治や経済の状況は、日々刻々と変化しています。
インターネットで得られる情報は手軽ですが、中には古かったり、あなたのご家庭の状況には当てはまらなかったりするものも少なくありません。
特に、今回のような大きな政治イベントを控えたタイミングでは、客観的で、かつ最新の情報をもとにした専門家のアドバイスが非常に重要になります。
私たちファイナンシャルプランナー(FP)は、特定の金融商品を売るのが仕事ではありません。
あなたのライフプラン全体を俯瞰し、数ある選択肢の中から、あなたにとって本当にベストな住宅ローンの組み方を一緒に考えるパートナーです。
一人で悩まず、ぜひ専門家を頼ってください。
▼より詳しく知りたい方はこちらの記事へ
「FPに相談すると、具体的に何が解決できるの?」という疑問や、後悔しない住まいの決め方の全体像については、こちらの記事が参考になります。
よくある質問とその回答(FAQ)
- Q1. 決選投票になったら、どうなりますか?
-
1回目の投票で過半数を獲る候補者がいない場合、上位2名による決選投票が行われます。その際は国会議員の票の比重が大きくなるため、議員間の派閥力学が結果を左右します。
どちらの候補者を支持するか、各派閥の動きに注目すると、より深く情勢を理解できます。 - Q2. 総理が変わったら、すぐに金利も変わるのですか?
-
いいえ、すぐに変わるわけではありません。金利を決めるのはあくまで日本銀行であり、その独立性は尊重されます。
新しい総理大臣の考え方は、日銀の総裁人事や政府からのメッセージを通じて、中長期的な金融政策の「空気感」を作るものであり、影響は徐々に現れます。 - Q3. 結局、家を買うのは「今」と「総裁選後」、どっちがいいの?
-
政治の動向だけで最適な購入タイミングを計るのは非常に困難です。それよりも、ご自身のライフプランや資金計画が整い、かつ「これだ!」と思える理想の物件に出会えた時が、あなたにとってのベストタイミングです。
どんな結果になっても対応できる準備こそが重要です。 - Q4. 候補者の言っていることって、本当に全部実現されるの?
-
公約が100%実現されるとは限りません。総理大臣になった後、党内での意見調整や、その時々の経済状況によって、政策の軌道修正は頻繁に行われます。そのため、公約は「その候補者が目指す大まかな方向性」として捉えておくと良いでしょう。
- Q5. 政治のニュース、これだけは見とけ!っていうポイントは?
-
総裁選後は、新しい総理大臣が誰を「財務大臣」に任命するかに注目してみてください。財務大臣は国の予算編成に大きな影響力を持つため、その人選を見ることで、新政権が「積極財政」と「財政規律」のどちらを重視しているのか、その本気度を読み解くヒントになります。
まとめ:未来は誰にも分からない。だからこそ「我が家の正解」を持つことが最強の武器になる
最後に、この記事でお伝えした最も重要なポイントを5つにまとめました。これからのマイホーム計画のお守りとして、ぜひ心に留めておいてください。
今回の総裁選は、金利上昇に慎重な「リフレ派」の高市氏と、経済次第で利上げを容認する「正統派」のその他4氏、という大きな構図で捉えると、ニュースがぐっと分かりやすくなります。
総理大臣が直接金利を決めるわけではありません。しかし、その経済に対するスタンスが、日本銀行の金融政策の方向性に間接的な影響を与え、巡り巡って私たちの住宅ローン金利に関わってきます。
住宅ローン控除などの支援策の行方は、候補者が「積極財政」と「財政規律」のどちらを重視しているかで未来が変わります。国の借金に対する考え方が、私たちの家計にも影響を与えるのです。
誰が総理になるかを当てるゲームに参加するのではなく、誰がなっても家計が揺らがない万全の資金計画を立てること。特に「安全な借入額の把握」は、何よりも優先すべき最強の防衛策です。
政治や金利の動向を理解することは大切ですが、それに振り回されすぎてはいけません。あなたとご家族がどんな暮らしをしたいか、というライフプランこそが、後悔しない家づくりの最も重要な羅針盤です。