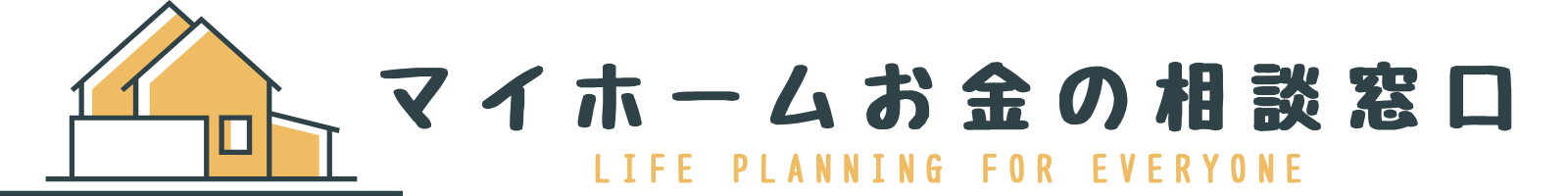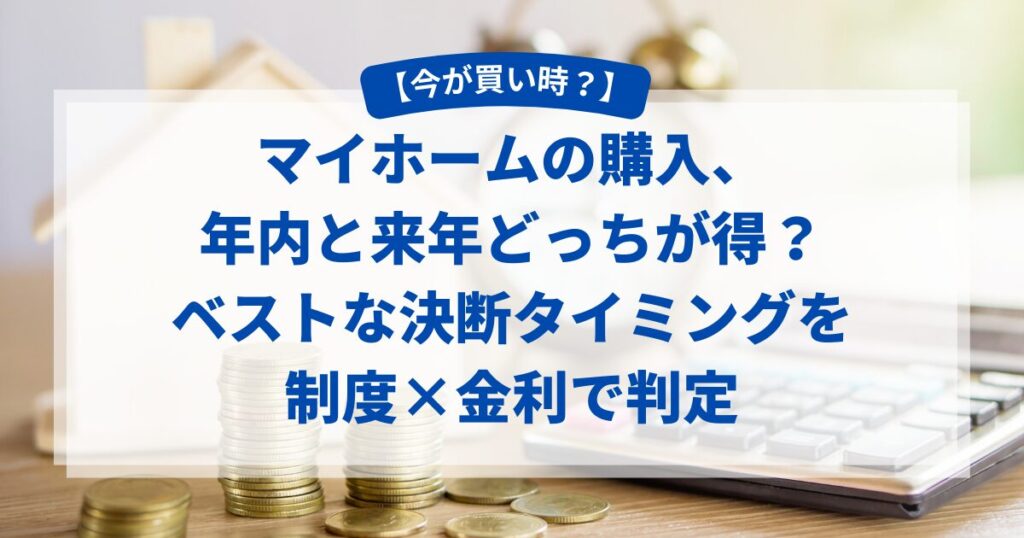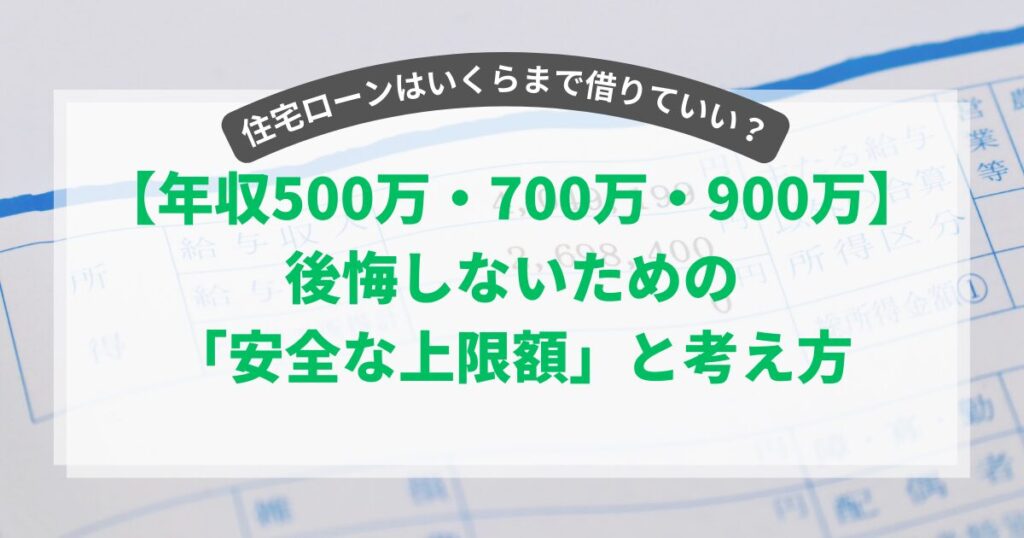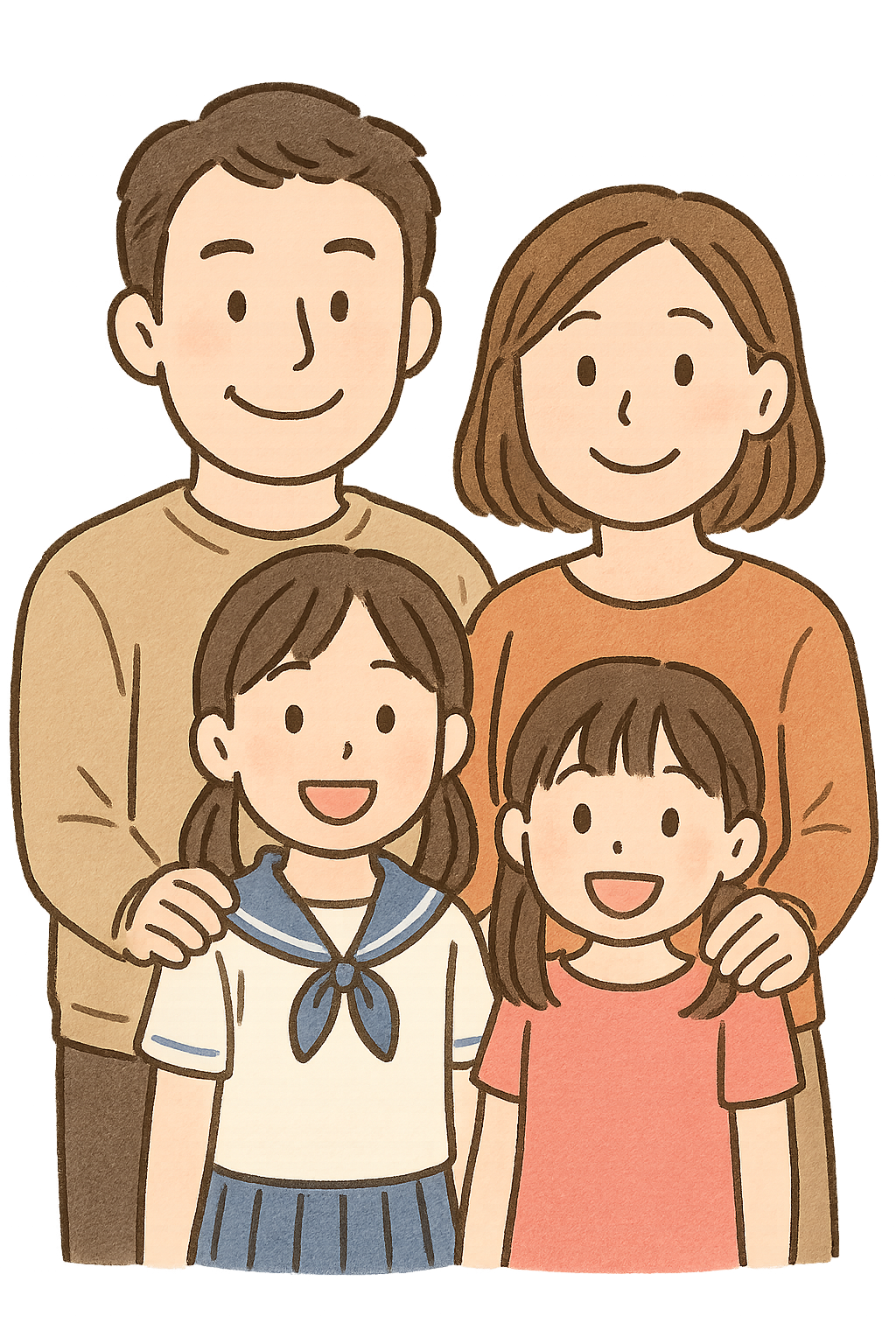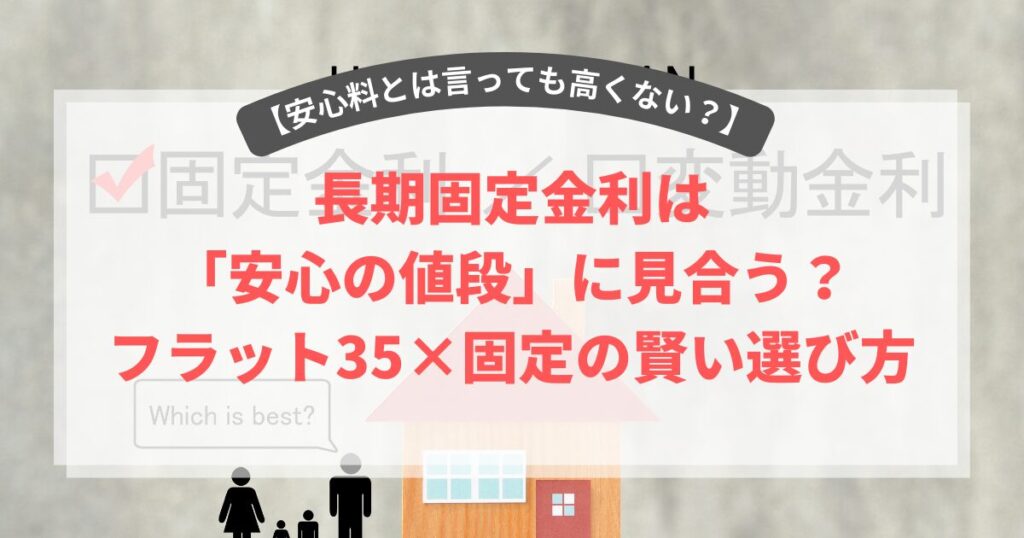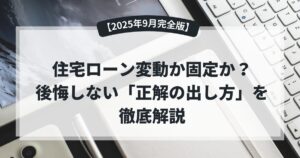【2025年9月完全版】住宅ローン変動か固定か?後悔しない「正解の出し方」を徹底解説
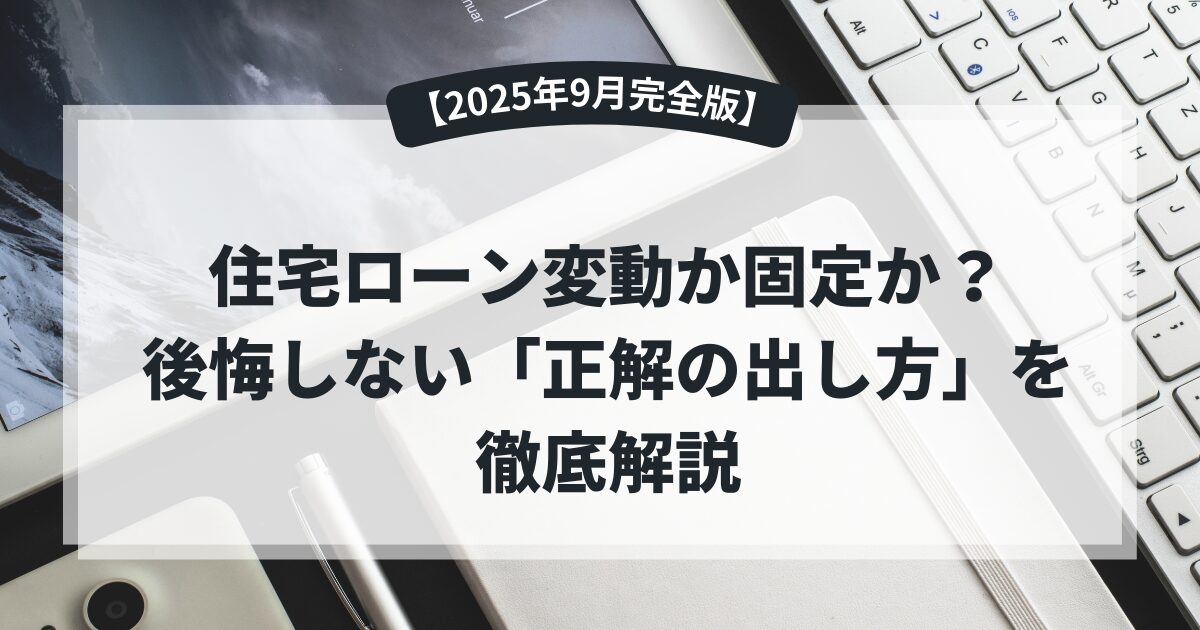
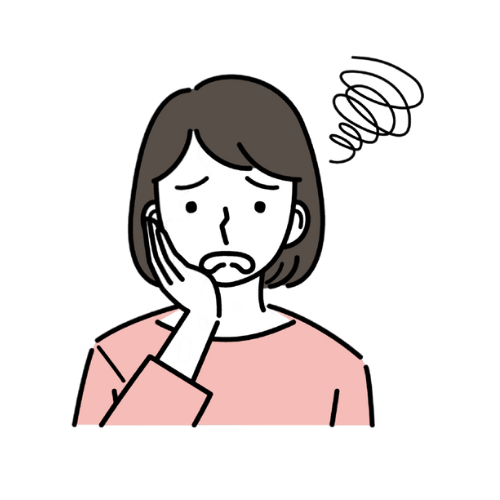
「そろそろマイホームが欲しいな…」
そう思って情報収集を始めたものの、住宅ローンの「変動金利か、固定金利か」という大きな壁にぶつかって、思考停止していませんか?
ニュースでは「日銀が追加利上げを検討…?」なんて不穏な言葉が飛び交い、「え、今借りたら損するの?」「じゃあ、いつがベストなの?」と、まるで出口のない迷路に迷い込んだような気分になりますよね。
そのお気持ち、痛いほど分かります。マイホームは人生で一番大きな買い物。
子どもの頃、意見が分かれた時にやったみたいに「せーので指さす!」で決められるわけもありません。
でも、ご安心ください。この記事は、単なる専門用語の解説書ではなく、あなたとご家族が10年後、20年後に「あの時、この記事を読んで、この選択をして本当に良かった」と心から思える未来を手に入れるための、具体的な「羅針盤」です。
15年のFPとしての経験と、実際に家を買った先輩たちのリアルな声を基に、あなたにとっての「後悔しない正解」を導き出すため、全力でナビゲートします。
一緒に未来の安心へと続く最適な答えを見つけにいきましょう。
【本題の前に】まずはあなたの現在地を知ろう!5分でわかる住宅ローン簡易診断


本格的な情報収集の前に、まずは簡単な診断で「あなたの心の方向性」を探ってみませんか?
まるで性格診断のように、直感でサクサク答えてみてください。この診断が、あなたにとっての「正解」を見つけるためのコンパスになりますよ。
Q1. ニュースで「金利、0.25%上昇!」と聞くと、気になって仕事が手につかなくなりそう?
Q2. 多少、総返済額が高くなったとしても、「毎月の返済額が変わらない」という絶対的な安心感が欲しい?
- YES ⇒ あなたは【安定志向の固定金利タイプ】かも!将来の計画をカッチリ立てたい堅実派ですね。
- NO ⇒ Q4へ
Q3. 今の家計には比較的余裕があり、月々の返済額が1万円くらい増えても「まあ、大丈夫かな」と思える?
- YES ⇒ あなたは【合理性重視の変動金利タイプ】かも!リスクを理解した上で、メリットを追求できる戦略家タイプです。
- NO ⇒ Q4へ
Q4. 現在子育て中で省エネ性能の高い住宅を検討している、またはその予定がある?
- YES ⇒ あなたは【優遇制度フル活用の固定金利(フラット35)タイプ】が有力候補!国の制度をお得に使える可能性があります。
- NO ⇒ あなたは【専門家と要相談!ハイブリッドタイプ】かも!変動と固定のミックスなど、あなただけのオーダーメイドな選択肢を探る価値がありそうです。
いかがでしたか? あくまで簡易診断ですが、ご自身のタイプが少し見えてきたのではないでしょうか。
この診断結果を頭の片隅に置きながら、この先の詳しい解説を読み進めてみてください。
きっと、あなたにピッタリな「正解の出し方」が見つかるはずです。
2025年秋、金利はどうなる?日銀の追加利上げと返済額へのリアルな影響
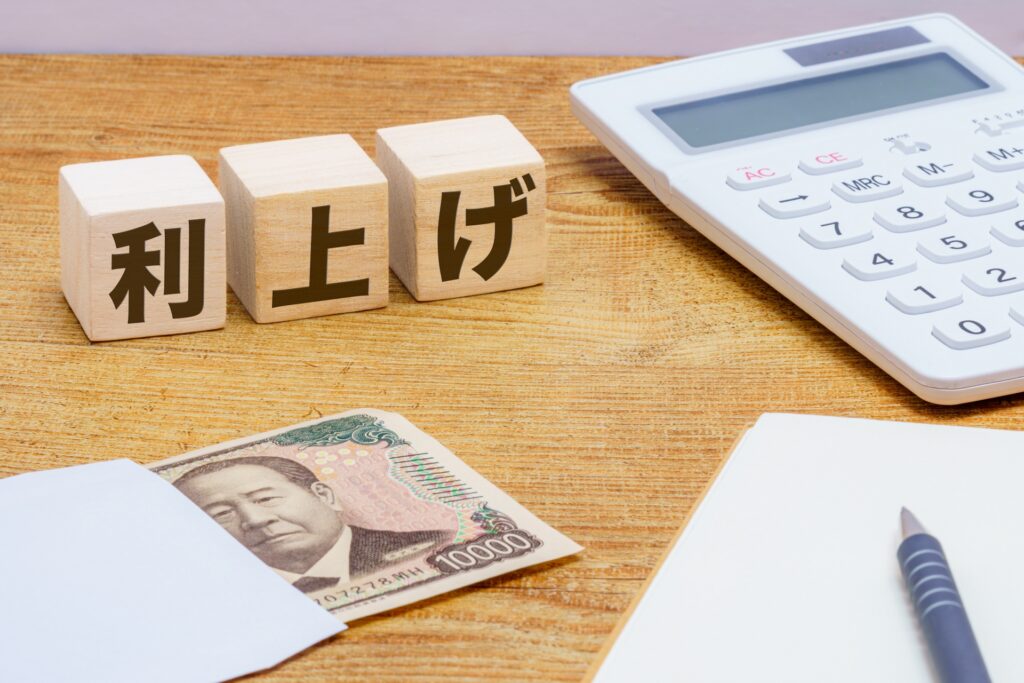
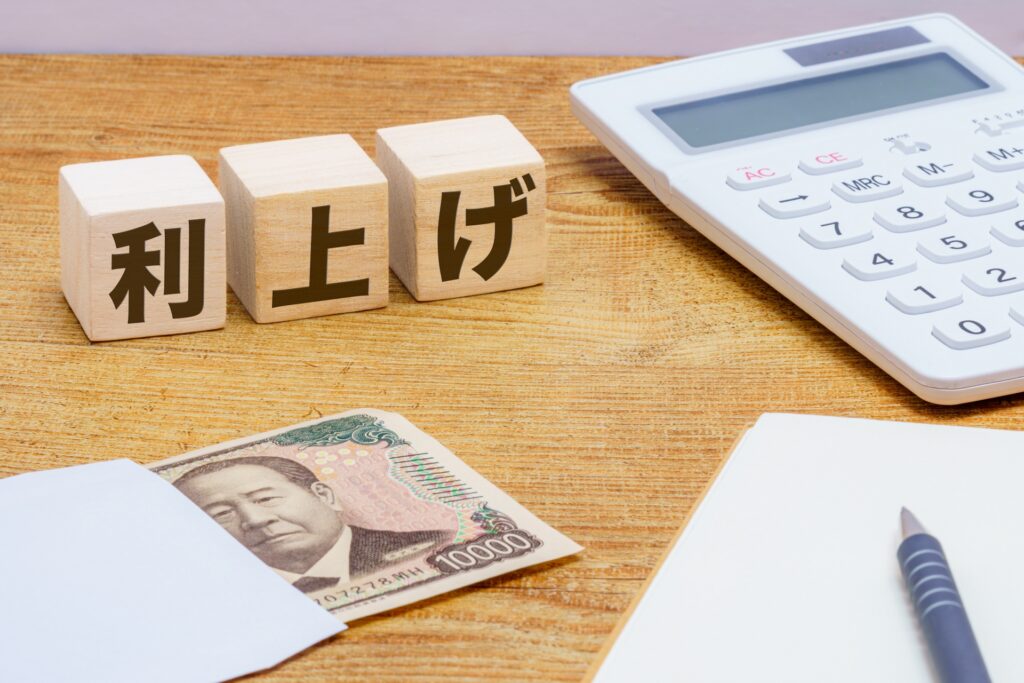
さて、ここからはいよいよ本題の核心、2025年現在の住宅ローン金利の動向です。
「結局、金利は上がるの?下がるの?」という疑問に、結論からお答えします。
多くの専門家が予測しているのは、「固定金利は緩やかな上昇圧力、一方で変動金利はすぐには急上昇しにくい」という状況です。
なんだか歯切れが悪いな、と感じましたか?
まるで「監督の采配次第ですが、たぶん今日は勝ちます!」くらい、どっちつかずな予報に聞こえるかもしれません。しかし、これには明確な理由があるのです。
なぜ金利タイプによって見通しが違うのか?
現在の状況は、日本経済が長年のデフレから脱却し、いわば「体質改善」を目指している時期です。
2024年のマイナス金利解除を皮切りに、日銀は金融の正常化を進めており、これが各金利に異なる影響を与えています。
- 固定金利が上昇しやすい理由
固定金利は、主に10年物国債の金利(長期金利)を指標にしています。市場が「これから景気は上向くだろう」と判断すると、長期金利は上昇する傾向にあります。
現在の金融政策の流れを受け、長期金利は緩やかに上昇しているため、住宅ローンの固定金利もそれに連動して、これ以上の大幅な低下は考えにくい状況です。 - 変動金利が急上昇しにくい理由
一方、変動金利は、日銀の政策金利に影響される「短期プライムレート」を基準にしています。日銀が追加の利上げに踏み切れば、理論上は変動金利も上昇します。
しかし、ここがポイントです。各銀行は住宅ローン市場で熾烈な顧客獲得競争を繰り広げています。もし一行だけが金利を上げてしまえば、顧客が他行に流れてしまうため、各行とも利上げには非常に慎重なのです。そのため、日銀の利上げが即座に、そして同じ幅で私たちの変動金利に反映される可能性は低いと考えられています。
「0.25%利上げ」であなたの返済額はいくら増える?
では、仮に日銀の利上げの影響で、あなたの変動金利が0.25%上昇したと仮定して、具体的な影響額をシミュレーションしてみましょう。〈条件:35年元利均等返済、金利0.8% ⇒ 1.05%の場合〉
| 借入額 | 金利 | 月々返済 | 上昇後の返済 | 差額 |
| 3,000万円 | 0.8% | 81,918円 | 85,386円 | 3,468円 |
| 4,000万円 | 0.8% | 109,224円 | 113,848円 | 4,624円 |
※実際の返済額は5年ルール・125%ルール等で変動します。
金利が0.25%上昇した場合の月々の返済額シミュレーション
いかがでしょうか。月々3,400円~4,600円程度の負担増。
これは、動画や音楽のサブスクを2〜3個見直せば捻出できる金額かもしれません。
この数字を「許容範囲だ」と捉えるか、「将来もっと上がると考えると怖い」と感じるか。
それが、あなたが変動か固定かどっちを選ぶべきかを判断する、重要なヒントになります。
今、住宅ローンを組むのは「待ち」か「進む」か?
金利の「底」を狙って住宅購入のタイミングを計るのは、投資のプロでも至難の業です。
大切なのは、2025年現在も歴史的に見れば十分に低金利であるという事実です。
ご自身のライフプラン(お子様の進学、転勤など)を考えた上で「今が買い時」なのであれば、金利動向を過度に恐れる必要はありません。
ただし、将来的な金利上昇の可能性を念頭に、少し余裕を持った資金計画を立てておくことが、後悔しないための最大の防御策と言えるでしょう。
金利動向と住宅ローン控除の期限を踏まえた、年内と来年どっちが得かという「ベストな決断タイミング」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください
変動か固定か?決断の前に!「我が家の予算」を正確に知る3ステップ


金利の動向をにらみつつ、「変動と固定、どっちがお得か?」と考える前に、実はもっと大切なステップがあります。
それは、「そもそも、我が家はいくらまでなら安全に借りられるのか?」という予算を正確に知ることです。
これは、体重計に乗らずにダイエットを始めるようなもの。今の自分の実力を知らずして、35年という長いマラソンは走りきれません。
どんなに有利な金利タイプを選んでも、借入額そのものに無理があれば、家計はあっという間に火の車になってしまいます。
少し耳の痛い話に聞こえるかもしれませんが、このステップを丁寧に行うことが、10年後の家族の笑顔を守る最大の秘訣です。一緒に確認していきましょう。
住宅ローンは「借りられる額」ではなく「無理なく返せる額」で決めるのが鉄則です。年収別の安全な上限額と考え方をさらに詳しく知りたい方はこちら>>>
ステップ1:家計簿アプリでOK!まずは現状のキャッシュフローを「見える化」する
最初のステップは、現状把握です。最低でも1〜2ヶ月、家計簿アプリなどを活用して、ご家庭の収入と支出を正確に記録してみましょう。
ポイントは、支出を「固定費」「変動費」「特別費」の3つに分けて考えることです。
- 固定費:家賃、保険料、通信費など、毎月ほぼ同額の支出
- 変動費:食費、水道光熱費、日用品費など、月によって変動する支出
- 特別費:旅行、家電購入、冠婚葬祭など、年間で不定期に発生する大きな支出
これにより、「毎月、自由に使えるお金がいくらあるのか」「貯蓄に回せているのはいくらか」という、ご家庭のリアルな「家計体力」が明らかになります。
ステップ2:「借りられる額」は罠?「無理なく返せる額」の黄金比率とは
家計を把握したら、次に「無理なく返せる額」を算出します。ここで絶対に注意してほしいのが、不動産会社や銀行が提示する「借りられる額(借入可能額)」を鵜呑みにしないことです。
彼らが提示する額は、あくまで「貸せる上限」であり、「あなたが安心して返せる額」ではありません。
これは、「こちらの高級車、お客様の年収ならローンは通りますよ!」と言われても、その後の維持費や税金を考えたらとても買えない、という状況とよく似ています。
そこで目安にしたいのが「返済負担率」という指標です。これは年収に占める年間返済額の割合のことで、一般的に「手取り年収の20〜25%以内」が安全圏とされています。(※家族構成や子供の人数、家計管理状況により一概に安全圏とは言えません)
【例:世帯の額面年収が800万円のご家庭の場合】
会社員の方であれば、源泉徴収票に記載されている「支払金額」が額面年収にあたります。
例えば、世帯の額面年収が800万円の場合、家族構成や各種控除によって変動しますが、手取り年収はおよそ600万〜640万円ほどになります。
この手取り額を基準に、安全な返済額を計算してみましょう。(ここでは仮に手取り620万円として計算します)
- 年間返済額の目安:620万円 × 20〜25% = 124万〜155万円
- 月々返済額の目安:約10.3万円 〜 12.9万円
このように、まずはご自身の「額面年収」からおおよその「手取り年収」を把握し、そこから返済額の予算を立てることが、無理のない計画の第一歩です。
もちろん住宅ローンだけではなく住居費全体として、です。固定資産税や火災保険、将来的な修繕費用も含めてこの金額におさめることが理想です。
ステップ3:将来のライフイベント(教育費・老後)も費用に織り込む
住宅ローンは35年という長期戦。その間には、お子様の進学、車の買い替え、家の修繕、そして自分たちの老後といった、様々なライフイベントが待ち構えています。
「子どもが大学に進学するのは何年後?」「その時、自分たちは何歳で、住宅ローンの残りはあと何年?」
このように、簡単な「ライフイベント表」を作成し、将来の大きな支出を予測してみましょう。特に、大学費用は一人あたり数百万円という大きな金額になります。
これらの将来費用を貯蓄しながら、無理なく返済し続けられるかをシミュレーションすることが、長期的な家計の安定に繋がるのです。
【徹底比較】変動金利 vs 固定金利、メリットと「見落としがちな罠」


ご自身の「予算」という土台が固まったところで、いよいよ変動金利と固定金利、2つの金利タイプを徹底比較していきます。
どちらも一長一短あり、まるでタイプの違う2人の主人公のようです。
片方は少し危なっかしいけれど魅力的なチャレンジャー、もう片方は安心感抜群の頼れるパートナー。あなたに合うのはどちらのタイプか、じっくり見極めていきましょう。
変動金利: 低金利の裏にあるリスクと賢い付き合い方
変動金利の最大の魅力は、なんといっても金利の低さです。当初の返済額をグッと抑えられるため、毎月の家計にゆとりが生まれます。金利が低い分、返済初期の元金の減りが早いのも嬉しいポイントです。
【見落としがちな罠:安心ルールの裏側】
変動金利には、金利が急上昇しても返済額が急に上がらないように「5年ルール(返済額は5年間変わらない)」と「125%ルール(再設定後の返済額は前回の1.25倍まで)」というセーフティネットがあります。
しかし、これが落とし穴になることも。もし金利が大幅に上昇した場合、毎月の返済額だけでは利息分すら払いきれず、「未払い利息」が発生する可能性があるのです。
この未払い利息は、あなたのローン元金に上乗せされてしまいます。つまり、「返済額は変わらないのに、借金だけが裏で膨らんでいた…」なんて、ホラー映画のような事態になりかねないのです。
固定金利: 「安心」の対価とは?
固定金利の最大のメリットは、完済まで金利と返済額が変わらない絶対的な安心感です。将来の金利動向に一喜一憂することなく、教育費や老後資金といった長期的なライフプランを非常に立てやすくなります。
まさに「備えあれば憂いなし」を地でいく選択肢です。
【見落としがちな罠:動けないもどかしさ】
固定金利のデメリットは、変動金利に比べて当初の金利が高いことです。そして、もう一つの「罠」は、世の中の金利が下がり続けても、自分だけが高い金利を払い続けるという「機会損失」のリスクです。
「みんなは返済が楽になっているのに、我が家だけ…」と、将来もどかしい思いをする可能性もゼロではありません。
【FPコラム】団信をどう考える?実はこんなに違う、金利以外の比較ポイント
住宅ローン選びは金利だけで判断してはいけません。万が一の際にローンがゼロになる保険「団体信用生命保険(団信)」も重要な比較ポイントです。
一般的に、変動金利を扱う民間の銀行は、がんや3大疾病、8大疾病や就労保障、要介護状態までカバーする手厚い団信を用意しています。
金利が0.1〜0.3%程度上乗せになりますが、自分で同等の生命保険に加入するより割安な場合も。
一方、固定金利の代表格であるフラット35の基本団信は死亡・高度障害、三疾病保障のみです。家族構成や健康への考え方も、金利タイプ選びの重要な判断材料になるのです。(※保証型といわれる金融機関主導のフラット35にはがん団信やワイド団信(持病がある方向け)なども選択可能な金融機関もあります)
【重要】今、固定金利を選ぶなら「フラット35」が最有力な理由


「固定金利の安心感は魅力だけど、やっぱり金利が高いのがネック…」 そう感じた方も多いのではないでしょうか。
事実、民間の銀行が独自に提供している全期間固定金利は、2025年現在、金利が高めに設定されており、なかなか選びにくいのが実情です。
しかし、そこで輝きを放つのが、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供する「フラット35」です。
国の政策と連動した強力な金利引き下げ制度があるため、今の時代に固定金利を選ぶなら、まず検討すべき最有力候補と言えます。そのお得な仕組みを、3つのポイントで解説します。
フラット35が今、一般的な変動金利よりも当初の金利が安くなる可能性がある理由や、民間固定ローンとの徹底比較について、深く解説しています>>>
2025年最新!「子育てプラス」等の金利優遇をフル活用しよう


現在のフラット35で最大の目玉といえるのが「子育てプラス」制度です。
これは、子育て世帯や若い夫婦世帯に対して、ポイントに応じて金利を大幅に引き下げてくれるという、まさに“子育て応援”のための制度。
- お子様の人数
- 夫婦の年齢(どちらかが40歳未満など)
- 住宅の性能
これらの条件に応じてポイントが加算され、最大で当初5年間、年▲1.0%という驚異的な金利優遇が受けられます。
これはまるで、国から子育て世代へ贈られる、期間限定のスペシャルクーポンです。この制度を使わない手はありません。
「当初の利息負担」から考える損得勘定|優遇金利で変動と比較
「でも、1%安くなっても、元の金利が高いんじゃ…?」と思いますよね。ここで、少し専門的な視点を取り入れてみましょう。
住宅ローンは、返済が始まったばかりの「当初10年程度」が最も利息の負担が大きい仕組みになっています。
この一番負担が大きい時期に、優遇金利が適用されるメリットは絶大なのです。
例えば、基準金利が1.8%のフラット35で、子育てプラスにより▲1.0%の優遇を受けられたとします。
すると、当初の適用金利は0.8%。 一方で、最近の変動金利の最下限が0.6%程度だとすると、その差はわずか0.2%です。
地銀などの変動金利との比較では場合によってはフラット35の当初優遇の方が低いケースも出てきています。
「0.2%の金利差で、35年間の安心が手に入る」。そう考えると、変動か固定かどっちか、という天秤のバランスが、少し変わって見えてきませんか?
高性能住宅ならさらに優遇!知らなきゃ損する金利引き下げ制度
フラット35の優遇は、子育て世帯だけではありません。省エネ性能や耐震性など、質の高い住宅を取得する場合に金利を引き下げる「フラット35S」という制度もあります。
子育て世帯以外でも、長期優良住宅やZEH(ゼッチ)水準の省エネ住宅などを選べば、当初の金利が年▲1.0%引き下げられることも。
つまり、幅広い年齢層や家族構成に対応した金利優遇制度があり、これからの金利上昇に不安を抱え、ある程度高性能な住宅を検討している方にとっては魅力的な選択肢の一つとなっています。
もう迷わない!家族構成・年収別「我が家の最適解」ケーススタディ
理論は分かったけれど、じゃあ具体的に「我が家の場合は?」となりますよね。
ここでは、よくある3つの家族モデルを例に、それぞれに最適な住宅ローンの「正解の出し方」をシミュレーションしてみます。ご自身の家族構成や価値観と近いケースを参考に、考えてみてください。
ケーススタディ①:30代共働き・子どもなし「パワーカップル」
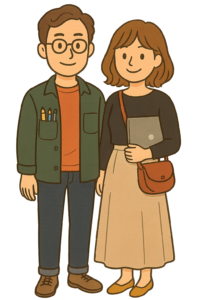
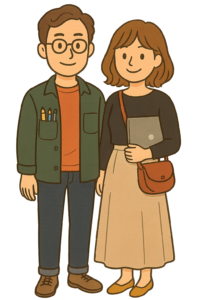
- プロフィール:夫32歳(IT)、妻31歳(メーカー勤務)。子どもは1〜2年後に検討中。
- 世帯年収:1,200万円
- 価値観:資産形成に積極的。合理性を重視し、許容できるリスクは取るべきと考える。
- 最適解:変動金利
- 理由: 世帯収入に十分な余裕があり、将来の金利上昇に対する「体力」があるのが最大の理由です。万が一金利が上がっても、繰り上げ返済を積極的に行うなど、柔軟な対応が可能。
金利の低さを最大限に活かして総返済額を圧縮し、余剰資金を投資に回すなど、戦略的かつ合理的な選択がこのカップルの価値観にマッチしています。
ケーススタディ②:30代後半・子ども2人の堅実ファミリー


- プロフィール:夫38歳(公務員)、妻37歳(パート)。小学生の子どもが2人。
- 世帯年収:750万円
- 価値観:家計の安定が最優先。子どもの教育費を計画的に貯蓄していきたい。
- 最適解:固定金利(フラット35)
- 理由: これから10年、まさに教育費の負担がピークを迎えるこのご家庭にとって、住宅ローンの返済額が上昇するリスクは絶対に避けたいところ。
フラット35の「子育てプラス」を活用すれば、当初の金利を大幅に引き下げることができ、変動金利との差も縮まります。目先の金利の低さよりも、35年後まで返済額が変わらないという絶対的な安心感を優先することが、家族の将来設計を守る賢明な選択と言えるでしょう。
ケーススタディ③:40代・自営業「収入変動に備えたい」
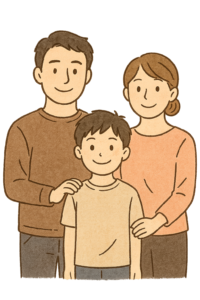
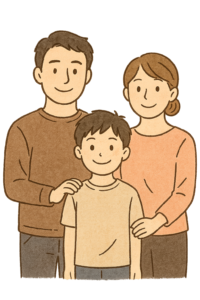
- プロフィール:夫42歳(個人事業主のデザイナー)。中学生の子どもが1人。
- 世帯年収:平均900万円(ただし年によって変動あり)
- 価値観:収入が不安定な分、固定費である住居費は完全に安定させたい。
- 最適解:固定金利(フラット35)
- 理由: 自営業やフリーランスの方は、収入が景気や仕事量に左右されがちです。収入が少ない時期に、変動金利の上昇が重なるという最悪の事態を避けるため、返済額が固定されていることは大きな精神的支えになります。
また、フラット35は収入の安定性を多角的に見てくれるため、民間のローン審査に不安がある方にとっても心強い味方。事業が好調な時に繰り上げ返済をすることで、効率的に返済を進めることも可能です。
【未来に備える】組んだ後も安心!金利上昇リスクへの対策と「出口戦略」


住宅ローンの契約書にサインをすることは、ゴールではなく新たなスタートです。35年という長い期間には、景気の変動やご自身のライフプランの変化など、様々なことが起こり得ます。
しかし、事前に「もしも」の時の打ち手を知っておけば、過度に恐れる必要はありません。ここでは、あなたの未来を守るための具体的なリスク対策と、状況に応じてローンを見直す「出口戦略」について解説します。
もし変動金利が上がったら?5つの具体的な打ち手
変動金利を選んだ場合に、最も気になるのが金利上昇リスクですよね。もし実際に金利が上昇局面に入ったら、慌てず騒がず、以下のカードを切る準備をしておきましょう。
- 家計を見直して支出を削減する
まずは基本の「守り」です。家計簿を再度チェックし、通信費やサブスクなど、削減できる固定費がないか探してみましょう。上昇した返済額分を、他の支出を削ることで吸収する最も手軽な方法です。 - 繰り上げ返済で元金を減らす
ボーナスなどまとまった資金ができたら、積極的に繰り上げ返済を行いましょう。
支払った分はすべて元金の返済に充てられるため、その後の利息を大きく減らす効果があります。利息軽減効果がより高い「期間短縮型」が特におすすめです。 - 「金利上昇対策用」の貯金&資産運用をしておく
変動金利の低金利のメリットを活かし、固定金利との差額分を毎月貯金か資産運用しておく、という proactive(攻め)の守り方です。
例えば、「もし金利が1.5%だったら」と想定した返済額との差額を貯めておけば、いざ金利が上がった時のための強力な緩衝材になります。 - 固定金利への借り換えを検討する
金利の上昇トレンドが続くと判断した場合、より金利が低い固定金利のローンに乗り換える「借り換え」も有力な選択肢です。
ただし、固定金利の指標となる長期金利は変動より先に上昇するケースが多いですし、借り換えには手数料などの諸費用がかかるため、タイミングが重要になります。 - 収入を増やす努力をする
支出を減らすだけでなく、収入を増やすという視点も大切です。共働きの場合はパートナーの働き方を調整したり、副業を検討したりと、返済力の土台そのものを強くする根本的な対策です。
ライフプランが変わった時の「借り換え」ベストタイミング
ローンの見直しである「借り換え」は、変動金利のリスク対策だけでなく、あらゆる方にとっての有効な出口戦略です。では、そのベストタイミングはいつなのでしょうか。
一般的に、以下の3つの条件が揃うと、諸費用を払っても借り換えのメリットが出やすいと言われています。
- ローン残高が1,000万円以上
- 残りの返済期間が10年以上
- 借り換え前後の金利差が0.5%〜1%以上
以前は「金利差1%以上」が目安でしたが、昨今の低金利下では0.5%程度の差でもメリットが出るケースが増えています。
また、借り換えは単に金利を下げるためだけのものではありません。
「子どもが生まれたから、もっと手厚い団信のローンに乗り換えたい」
「収入が増えたので、返済期間が短いローンに借り換えて早く完済したい」
など、ご自身のライフプランの変化に合わせて、ローンを最適化するための戦略的なツールなのです。
10年後の自分に感謝される決断をするために
変動金利か、固定金利か。ここまで読み進めてくださったあなたなら、この問いに「絶対的な正解はない」こと、そして「自分たち家族にとっての納得解を見つけることがゴール」だということが、もうお分かりのはずです。
情報を武器に、そして何よりも家族のこれからの笑顔を想像しながら、後悔のない決断をしてください。
変動金利・固定金利、最終的にこんな人におすすめ
- 変動金利が向いている人
金利上昇リスクを理解し、それに対応できる資金的・精神的な余裕がある人。総返済額を少しでも抑えたい合理的な思考の人。 - 固定金利(フラット35)が向いている人
将来の金利動向に一喜一憂したくない、安心感を最優先したい人。子育て中で、計画的に教育費を準備したい人。国の優遇制度を最大限活用したい人。
【明日からやることリスト】あなたの具体的な次のステップ
この記事を閉じた瞬間が、あなたのスタートラインです。さあ、未来のために今日から動き出しましょう!
- 我が家の予算を計算してみる
まずはこの記事を参考に、「無理なく返せる額」はいくらか、家族で作戦会議を開いてみましょう。 - 気になる金融機関を3つリストアップする
ネット銀行、地元の銀行、フラット35のサイトなど、タイプを分けて比較検討の土台を作りましょう。 - FPや金融機関への無料相談を予約する
最後はプロの力を借りるのが一番の近道。客観的なアドバイスをもらい、決断の背中を押してもらいましょう。
よくある質問とその回答
- Q1. ネット銀行とメガバンク、住宅ローンはどちらで借りるのがおすすめですか?
-
以前はネット銀行の金利が低い傾向にありましたが、2025年9月現在、その常識は変わりつつあります。金利上昇期を迎え、豊富な預金量を背景に体力のあるメガバンクが、キャンペーン等でネット銀行より低い金利を提示するケースも出てきました。
金利、手続きの手軽さ、対面相談の有無といった各々の良さを踏まえ、先入観なく比較検討することが重要です。 - Q2. 頭金はどれくらい準備すればよいのでしょうか?ゼロでも大丈夫ですか?
-
一般的に物件価格の1〜2割が目安とされますが、必須ではありません。超低金利の現在では、頭金を貯める時間で金利が上昇するリスクを考え、早めに借りる選択も有効です。
ただし、頭金が多いほど審査は有利になり、総返済額も減ります。 - Q3. 「ペアローン」と「収入合算」、共働きの場合どちらがお得ですか?
-
共働きで借入額を増やす方法は主に「収入合算」「ペアローン」「連帯債務」の3つです。住宅ローン控除は収入合算が1人分ですが、ペアローンと連帯債務は持分に応じ2人分使えます。
ただし、ペアローンはローン契約が2本になるため諸費用も高めです。税金のメリットと初期費用のバランスで検討しましょう。 - Q4. 繰り上げ返済は、いつやるのが一番効果的ですか?
-
原則は利息軽減効果が高い「返済初期」が効果的です。ただし、住宅ローン減税の適用期間中は注意が必要。繰り上げ返済で年末のローン残高が減ると、税金の控除額も減ってしまいます。
ご自身のローンの支払利息額と減税額を天秤にかけ、どちらのメリットが大きいか判断しましょう。 - Q5. もし住宅ローンの審査に落ちてしまったら、もう家は買えませんか?
-
一度審査に落ちても諦める必要はありません。まずは原因(個人の信用情報、健康状態、物件の評価など)を確認しましょう。金融機関によって審査基準は異なるため、借入額を調整したり、別の銀行やフラット35で再挑戦したりする道は十分にあります。
まとめ
2025年秋の金利は、固定金利に緩やかな上昇圧力がある一方、変動金利は急騰しにくい見通しです。ただし、将来の金利上昇への備えは必須と考えましょう。
金利タイプを選ぶ前に、まずは手取り年収の20〜25%を目安に「無理なく返せる額」を算出しましょう。正確な予算決めが後悔しないための最重要ポイントです。
変動金利は低金利が魅力ですが、金利上昇リスクが伴います。固定金利は返済額が変わらない安心感が強みですが、金利は変動より高めに設定されています。
今、固定金利を選ぶなら「子育てプラス」等の優遇制度が強力なフラット35が最有力候補です。条件次第では、変動金利と遜色ない金利で安心が手に入ります。
ローン選びに絶対的な正解はありません。ご家庭の価値観やライフプランを最優先し、専門家にも相談しながら、家族全員が納得できる「我が家の正解」を見つけましょう。