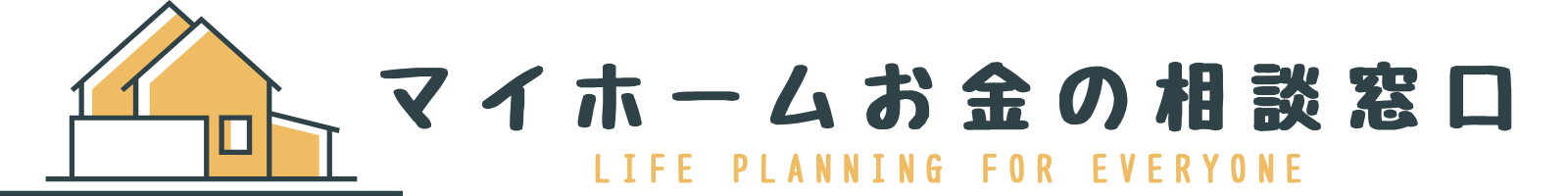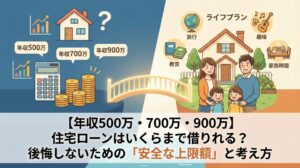【年収500万・700万・900万】住宅ローンはいくらまで借りていい?後悔しないための「安全な上限額」と考え方
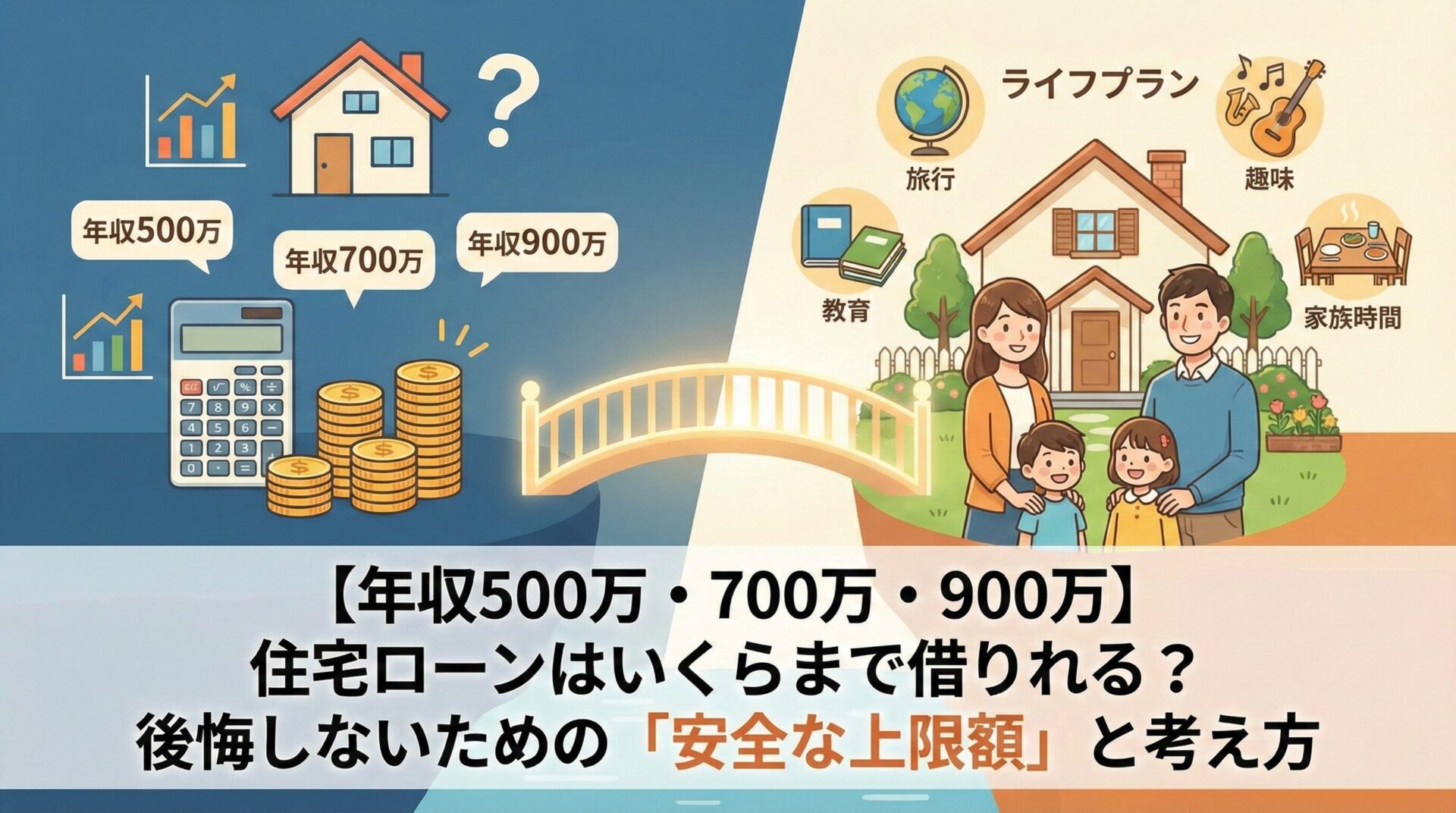
「そろそろマイホームが欲しいな…」
そう思って色々調べ始めると、必ず目にするのが
「年収の〇倍までOK」
「返済負担率は25%以内で」
といった、もっともらしい数字の数々。
でも、心の中でこう思いませんか?
「その数字、本当にうちの家族に当てはまるの?」と。
年に一度の家族旅行、子供の習い事、たまの夫婦での外食…
大切にしたいものは家庭によって全然違うはず。それなのに、画一的な数字に自分たちの人生を当てはめて、本当に後悔しないのでしょうか。
まるでサイズの合わない服を無理やり着るように、窮屈な思いをするのは目に見えています。
ご安心ください。この記事は、よくある「年収別の借入額シミュレーション」を最初に提示するようなことはしません。
なぜなら、住宅ローンで最も大切なのは、年収や数字ではなく、あなたと家族の「ライフプラン(人生の優先順位)」だからです。
この記事を読めば、世間の常識や数字に振り回されることなく、あなた自身の価値観に基づいた、後悔しない住宅ローンの目安がわかります。
「我が家が本当に大切にしたい暮らし」から逆算して考える、まったく新しいアプローチです。
早速一緒に理想のマイホーム計画を始めましょう!
年収別の借入額目安はあくまで参考。鵜呑みにすると危険です!
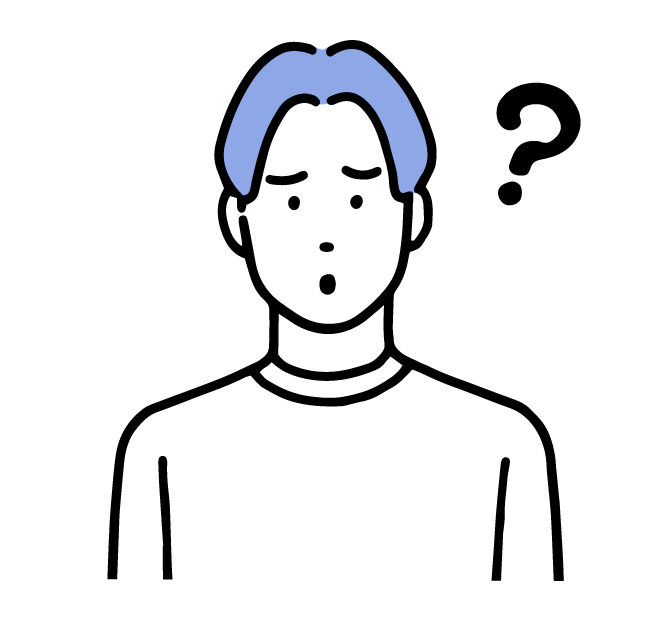
「で、結局のところ、自分の年収だといくらまで借りられるの?」
まず、皆さんが一番気になっているであろう、一般的な年収別の住宅ローン借入額の目安から見ていきましょう。
あくまで、多くの金融機関や不動産情報サイトで提示されている参考値です。
【一般的な住宅ローン借入額の目安(参考)】
年収別・一般的な住宅ローン借入額の目安
- 年収500万円 の場合:2,500万円 〜 3,500万円
- 年収700万円 の場合:3,500万円 〜 4,900万円
- 年収900万円 の場合:4,500万円 〜 6,300万円
※返済負担率20~25%、金利1.5%、35年返済などでシミュレーションした場合の一般的な金額
「なるほど、うちは大体このくらいか…」と、なんとなくの相場観は掴めたかもしれません。
ですが、ここからが非常に重要なポイントです。



この数字を鵜呑みにして住宅ローンを組むのは、非常に危険です。
なぜなら、この数字はあなたの「家族構成」や「価値観」、「将来の夢」といった、人生で最も大切な要素を一切考慮していないからです。
これは言ってみれば、国民の平均身長や平均体重のようなもの。あなたにピッタリ合う服のサイズが、平均値とイコールではないのと同じです。
特に、銀行が審査で出してくれる「あなたに貸せる上限額(借入可能額)」と、あなたが「将来にわたって無理なく、幸せに返していける額(安全な返済額)」は全くの別物です。
銀行の「お貸しできますよ」という言葉は、憧れのブランドショップで店員さんが「こちらの素敵なコート、お客様ならお買い求めいただけますよ」と優しく勧めてくれるようなもの。
確かに魅力的で、袖を通せば最高の気分になれるかもしれません。ですが、そのコートを着ていく場所(=ライフスタイル)や、手持ちの他の服(=生活費や教育費)とのバランスを考えずに買ってしまっては、結局クローゼットに眠らせたまま…なんてことになりかねませんよね。
同じ年収700万円でも、「夫婦二人で、趣味のアウトドアや旅行にお金をかけたい家庭」と、「お子さんが二人いて、将来の教育費をしっかり準備したい家庭」では、毎月住宅ローンに回せるお金は全く変わってきますよね。
安易に「借りられるだけ借りて、立派な家を建てよう」と決めてしまうと、後から「こんなはずじゃなかった…」と、返済のために他のすべてを我慢する生活になりかねません。
だからこそ、まずはこの一般的な目安を「ふーん、そんなもんか」と頭の片隅に置く程度にして、「自分たちだけの答え」を探しに行く必要があるのです。
【最重要】最初にやるべきはシミュレーションじゃない!人生の優先順位を決めることです


さて、ここからが本題です。もしかしたら、あなたは「早くうちのケースのシミュレーション結果が知りたいんだけど…」と感じているかもしれません。
ですが、その電卓を叩く手を一度だけ止めて、もう少しだけお付き合いください。
なぜなら、幸せなマイホーム計画の第一歩は「計算」ではなく「対話」だからです。
結論から言います。住宅ローンを考える上で最初にやるべきことは、
「私たち家族は、この先の人生で何を大切にし、何にお金を使い、どんな瞬間に幸せを感じたいか」という人生の優先順位を、夫婦(パートナー)ですり合わせることです。
なぜ、そんな遠回りのようなことが必要なのでしょうか?
それは、住宅ローンが「目的」ではなく、豊かな人生を送るための「手段」に過ぎないからです。
私たちは家を買うために生きているわけではありません。美味しいものを食べたり、子供の成長を見守ったり、趣味に没頭したり、友人と笑い合ったり…。
そうした日々の暮らしを、より豊かにするために「マイホーム」という選択肢があるはずです。
もし、この優先順位が曖昧なまま「借りられるだけ借りて、立派な家を建てよう!」と突き進んでしまうと、どうなるでしょうか。
ローンの返済が人生の最優先事項になってしまい、本来大切にしたかったはずの
「年に1回の家族旅行」
「子供がやりたがっている習い事」
「たまの夫婦水入らずの外食」
などを、「ローンのために…」と我慢せざるを得ない生活に陥ってしまう危険性があります。これこそが、いわゆる「ローン貧乏」の状態です。
そうならないために、まずは夫婦でこんな対話をしてみてはいかがでしょうか。
- もし、毎月自由に使えるお金が3万円増えたら、何に使いたい?
- 子供の教育については、どこまでを望む?(公立?私立?)
- 車は必要?もし必要なら、どんなクラスの車に乗りたい?
- 自分たちの趣味や自己投資には、どれくらいお金をかけたい?
- 何歳くらいで、どんなリタイア生活を送りたい?
まるで、家計のこんまりさんになったつもりで、「ときめく支出」は何かを考えてみるのです。難しく考える必要はありません。お互いの価値観を知る、絶好の機会になります。
「じゃあ、よく聞く返済負担率って考えなくていいの?」
と思った方もいるでしょう。もちろん、返済負担率は重要な指標です。
しかし、それはあくまで「決めたライフプランが、家計的に無理のない範囲に収まっているか?」を確認するための「ものさし」や「体温計」のような役割です。
先にものさしの目盛りに自分たちの人生を無理やり合わせるのではなく、まず自分たちの理想の暮らしを描き、それが健全な範囲(体温で言えば平熱)に収まっているかを確認するために使うのが、正しい順番なのです。
【実践編】たった10分で不安解消!ライフプランから逆算する「本当の安全ライン」算出3ステップ


ここがこの記事の心臓部です!前の章で「ライフプランが大事」と聞いて、「なんだか難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。でも、ご安心ください。ここからの3ステップは、誰でも簡単に、たった10分で実践できます。
少し面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が将来の数百万円、いえ、数千万円の安心に繋がります。
ぜひ、コーヒーでも片手に、夫婦で宝くじの使い道を相談するような楽しい気持ちでやってみてください!
STEP1:「未来の家計簿」を作ってみよう!
まずは、現状と未来の家計を「見える化」することから始めましょう。難しく考える必要はありません。ノートやExcelに、ざっくりと書き出すだけでOKです。
【収入の部】
- 毎月の手取り収入: 夫 ○○万円 + 妻 ○○万円 = 合計 ○○万円
- 年間のボーナス手取り: 夫 ○○万円 + 妻 ○○万円 = 合計 ○○万円
【支出の部(現在)】
- 固定費: 家賃、保険料、通信費、サブスクなど
- 変動費: 食費、水道光熱費、日用品、おこづかいなど
- 貯金: 毎月の貯金額
【支出の部(未来の特別費)】 ← ココが重要! これから10年〜15年の間に起こりそうなライフイベントと、それに掛かる費用を予測して書き出します。
- (例1)5年後: 長男が中学校入学(入学準備金などで30万円)
- (例2)8年後: 車の買い替え(250万円)
- (例3)10年後: 家族で沖縄旅行(40万円)
- (例4)12年後: 長男が大学入学(入学金・初年度学費で150万円)
ポイントは完璧を目指さないこと。「こんな感じかな?」という、ざっくりとした予測で全く問題ありません。
STEP2:譲れない支出を引いて、我が家が「住居費にかけられる上限額」を把握する
次に、STEP1で作った家計簿をもとに、「これだけは絶対に譲れない!」という支出を確保し、住宅ローンに回せる上限額を計算します。
例えば、毎月の手取り収入が40万円のご家庭の場合…
- 現在の生活費が25万円かかっているとします。
- 前の章で話し合った「譲れないこと」(=ときめく支出)が、
- 子供の習い事代:3万円
- 未来のための貯金(学費や老後資金):3万円 だったとします。
- すると、40万円 – (25万円 + 3万円 + 3万円) = 残りは9万円です。
- さらに、病気や急な出費に備えるための予備費(バッファ)として2万円を確保しておきましょう。
- 結果、9万円 – 2万円 = 7万円。
この「月々7万円」が、このご家庭にとって、今の暮らしや将来の夢を犠牲にすることなく、無理なく住宅にかけられるお金の上限額ということになります。
STEP3:算出した「上限返済額」から、安全な借入額をシミュレーションする
いよいよ最終ステップです。STEP2で算出した「我が家の上限返済額」をもとに、実際にいくらまで借り入れができるのかを計算します。
年収からではなく、ライフプランから導き出したこの数字こそが、あなたの「本当の安全ライン」です。
ここでは、より慎重に検討を進めるために、2つの段階に分けて考えていきましょう。
【第1段階】まずは「長期固定金利」で、最も安全なラインを知る
最初に、将来の金利変動リスクを一切心配する必要がない、長期固定金利の代表格「フラット35」で試算してみましょう。
これが、今のライフプランを維持しながら返済できる、最も堅実で安全な借入額になります。
先ほどの例、「月々7万円」を返済していく場合でシミュレーションします。
- 月々の返済額:7万円
- 返済期間:35年
- 金利:1.89% (※1:2025年9月現在のフラット35の標準的な金利)
この条件で借り入れできる金額は、約2,150万円となります。
【第2段階】希望額に届かない場合の「変動金利」という選択肢
もし、第1段階で算出した借入額では希望の物件に少し届かない…という場合、次の選択肢として変動金利を検討します。
変動金利は固定金利より金利が低いため、同じ返済額でもより多くの金額を借り入れることが可能です。
ただし、これには絶対に守るべき必須条件があります。そ
れは、STEP2で確保した『予備費(バッファ)』を、将来の金利上昇への備えとして、決して他の目的で使わないことです。この予備費があるからこそ、万が一金利が上昇しても家計が耐えられるのです。
この条件を守れるという前提で、シミュレーションしてみましょう。
- 月々の返済額:7万円
- 返済期間:35年
- 金利:0.7% (※2:変動金利の例)
この場合、借入可能額は約2,650万円まで広がります。
金利タイプ別・借入可能額シミュレーション比較
(毎月の返済額7万円・35年ローンの場合)
さあ、あなたならどちらを選びますか?
どちらが正解ということはありません。これは、ご自身の性格やライフプランと向き合い、「自分たち家族にとっては、どちらがより幸せか」を判断する問題です。
この2つのリアルな数字をもとに、ぜひご夫婦でじっくり話し合ってみてください。
【モデルケース別】うちの場合はどうなる?ライフプランで考える住宅ローンのリアルな目安
これまでの考え方や計算方法を踏まえ、「マイホーム」という大きな目標のために、それぞれの家族がどのように家計の優先順位を見直したか、という視点で3つのモデルケースを見ていきましょう。
きっと「うちもこうすれば実現できるかも!」というヒントが見つかるはずです。
※ここでの「世帯年収」は額面年収、「手取り月収」はボーナスも含めて12で割った平均額として計算しています。
※各ケースの借入額は、まず安全な長期固定金利(フラット35 / 1.89%)で算出し、参考として変動金利(1%)の場合も併記します。
モデルケース別・ライフプランから考える安全な借入額
Case1:【世帯年収900万円 / 32歳 / 子供なし夫婦】
「趣味も旅行も楽しみつつ、現実的なラインで家を買う」
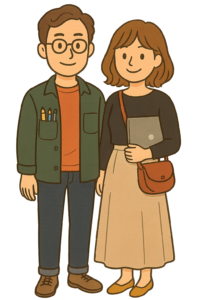
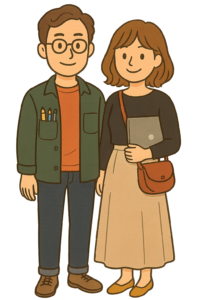
- 家族構成と価値観
夫(32歳・年収600万)、妻(32歳・年収300万)の夫婦二人暮らし。子供の予定は当面なし。最大の価値は「夫婦二人の時間」。
年1回の海外旅行(予算50万円)と、それぞれの趣味(月合計5万円)は絶対に譲れないが、マイホームのために日々の生活費を少しスリム化することに。 - 家計の見直しと上限返済額
世帯の手取り月収は約55万円。
ここから、見直し後の生活費(28万円)、趣味代(5万円)、旅行積立(月4万円)、将来のための貯蓄(6万円)を確保。
さらに予備費2万円を取った結果、住宅ローンに回せる上限額は「月々10万円」と設定できました。 - 安全な借入額の目安
【堅実プラン(固定1.89%)】約3,070万円
【参考(変動1%)】約3,530万円 (これは手取り年収の約4.6倍〜5.3倍。変動金利なら選択肢がさらに広がります) - ポイント
「何となく」使っていた日々の支出を見直すことで、一番大切にしたい趣味や旅行を我慢することなく、都心郊外のマンションや地方の戸建てが十分に視野に入る借入額を実現しました。
Case2:【世帯年収700万円 / 35歳 / 子1人】
「教育費を聖域とし、他の費用の優先順位を見直してマイホームを実現」
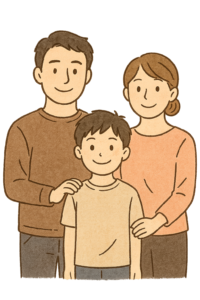
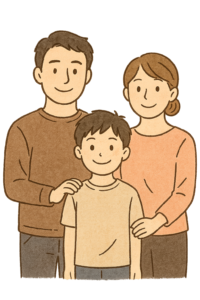
- 家族構成と価値観
夫(35歳・年収600万)、妻(パート年収100万)、長男(5歳)。最優先は「息子の教育費」。
ここには一切手をつけず、レジャー費や自分たちのための貯蓄のペースを少し調整することで、住宅購入の予算を捻出。 - 家計の見直しと上限返済額
世帯の手取り月収は約42万円。聖域である教育費貯金(月4万円)は死守。その上で、生活費(25万円)、車積立(月2万円)、レジャー費(月1万円)、老後貯金(月1万円)を確保。予備費2万円を取り、住宅ローンに回せる上限額は「月々7万円」となりました。 - 安全な借入額の目安
【堅実プラン(固定1.89%)】約2,150万円
【参考(変動1%)】約2,470万円 (これは手取り年収の約4.2倍〜4.9倍。エリアや物件の種類を工夫すれば十分検討可能です) - ポイント
「すべてを完璧に」ではなく、「絶対に譲れないもの」を守るために他の部分で調整する、という現実的な判断が良い結果に繋がりました。
変動金利も視野に入れれば、より希望に近い物件に出会える可能性が高まります。
Case3:【世帯年収500万円 / 30歳 / 子2人】
「夫婦の協力プランで予算アップ!未来を織り込んだマイホーム計画」


- 家族構成と価値観
夫(30歳・年収500万)、妻(専業主婦)、長女(6歳)、次女(4歳)。
子供が小さいうちに資産となるマイホームを手に入れたい。当初は夫の収入だけで計画していたが、希望の物件には少し届かないことが判明。 - 家計の見直しと「協力プラン」
夫の収入だけだと、捻出できる返済額は「月々5万円」が上限でした(借入額目安:1,530万円〜)。しかし、この家族はここで諦めませんでした。
家族会議の結果、「下の子供が幼稚園に入る1年後から、妻がパート(年収100万円程度)を始める」という未来を、当初の計画に織り込むことにしたのです。 妻の収入(手取り月7〜8万円)のうち3万円を返済額に上乗せすることで、世帯としての返済上限額を「月々8万円」に設定しました。 - 安全な借入額の目安
【堅実プラン(固定1.89%)】約2,460万円
【参考(変動1%)】約2,820万円 - ポイント
当初の計画から、借入可能額が約1,000万円もアップし、物件の選択肢が大幅に広がりました。もちろん、これは「1年後に妻が働き始める」という夫婦の協力が前提です。
当初の1年間は少し家計が引き締まりますが、それを乗り越えれば、希望のエリアでのマイホームも現実的な目標に変わります。
このように、将来のライフプランの変更を前向きに計画に組み込むことで、当初の予算の壁を乗り越えることも可能です。家族で協力して未来を作る、これもまた素晴らしいマイホーム計画の形と言えるでしょう。
よくある質問とその回答(FAQ)
- Q1. ライフプランなんて、将来変わるかもしれないのに考える意味はありますか?
-
はい、大きな意味があります。ライフプランニングは計画通りに進めること自体が目的ではありません。将来、予期せぬ変化(転職、病気など)が起きた時に、慌てずに判断するための「揺るぎない判断軸(羅針盤)」を持つことが本当の目的なのです。
一度立てたプランも、年に一度は見直すことで、より現実的で精度の高いものに進化させていくことができます。 - Q2. 自営業で収入が不安定な場合、どう考えればいいですか?
-
会社員以上に慎重な計画が必要です。まず、年収を計算する際は、過去3年間の平均所得など、最も低い年の収入を基準に考えるのが安全です。
また、収入の波に備えるため、住宅ローンとは別に、生活費の1年分程度の「生活防衛資金」を厚めに確保しておくことを強くお勧めします。これにより、不況時でも安心してローン返済を続けることができます。 - Q3. 頭金はライフプランにどう影響しますか?
-
頭金には、総返済額を減らし、月々の返済を楽にするメリットがあります。しかし、その一方で手元の現金が減り、急な出費への対応力が落ちるというデメリットも。
特に、近い将来にお子さんの進学などで大きな出費が確定している場合は、無理に頭金を多く入れるよりも、手元に現金を残しておく方が賢明なケースもあります。ライフプランと照らし合わせ、バランスを取ることが重要です。 - Q4. 金利タイプの選び方もライフプランによって変わりますか?
-
はい、大きく変わります。例えば、「今後、教育費がどんどん増えていくので、将来の返済額が確定している方が安心」というご家庭や、金利のニュースを気にしたくない性格の方は「固定金利」が向いています。
逆に、「共働きで収入に余裕があり、金利上昇にも対応できる」「リスクを取ってでも総返済額を抑えたい」と考えるご家庭は「変動金利」も有力な選択肢となるでしょう。 - Q5. 住宅ローン控除も考慮に入れて計算すべきですか?
-
住宅ローン控除(減税)は、年末のローン残高に応じて所得税や住民税が戻ってくる非常にありがたい制度です。しかし、これはあくまで期間限定の「ボーナス」のようなもの。控除があるからといって、当初の借入額を増やすのは本末転倒です。
まずは控除を抜きにして無理のない返済計画を立て、戻ってきたお金は繰り上げ返済や将来のための貯蓄に回す、と考えるのが最も健全です。
まとめ
ネットや銀行が提示する借入可能額は、あなたのライフプランを一切考慮していません。その数字を鵜呑みにせず、あくまで「世間の相場観」を知るための出発点として捉え、自分たちの状況とは切り離して考えましょう。
住宅ローン計画で最初にやるべきは、シミュレーションではありません。「家族でどんな暮らしがしたいか」「何にお金をかけたいか」を話し合うことです。家は目的ではなく、幸せな人生を送るための手段に過ぎません。
年収から借りられる額を考えるのではなく、ライフプランを踏まえて「毎月、無理なく払える上限額」を先に決めましょう。その上限返済額から逆算することで、あなたと家族にとって本当に安全な借入額が見えてきます。
当初の予算では希望に届かない場合でも、諦める必要はありません。家計の優先順位を見直したり、将来の収入アップを計画に織り込んだりすることで、借入可能額を現実的に増やすことは十分に可能です。
最終的に、住宅ローンの正解は一つではありません。周りと比べるのではなく、この記事で紹介した考え方やステップを参考に、あなたと家族だけの「幸せの物差し」を見つけ、後悔のないマイホーム計画を進めてください。