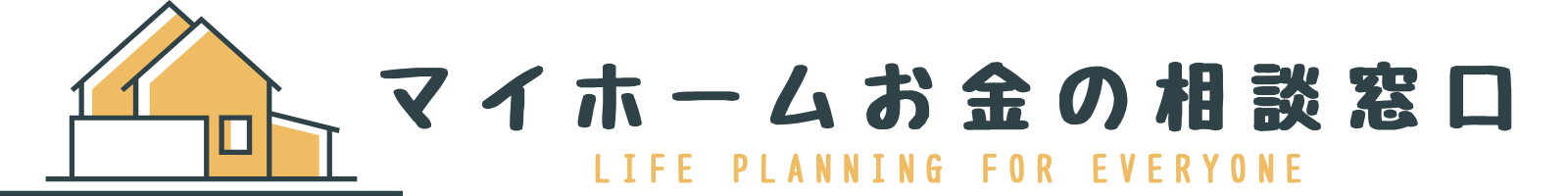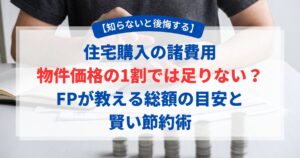【知らないと後悔する】住宅購入の諸費用、物件価格の1割では足りない?FPが教える総額の目安と賢い節約術
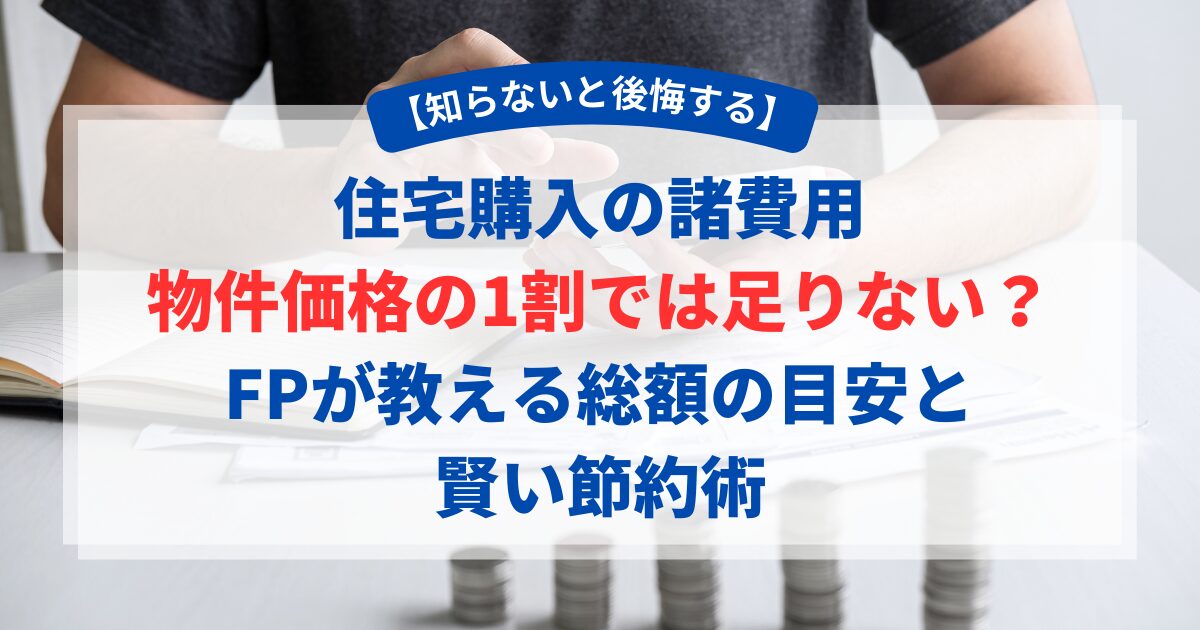
「この物件、素敵…!よし、住宅ローンはこれくらいで…」
夢のマイホームを前に、胸をときめかせながら資金計画を立て始めたあなた。でも、その計算に「物件価格以外のお金」は入っていますか?
「あれ?そういえば“諸費用”っていくら必要なんだっけ?」と、急に目の前が霧に包まれるような感覚、ありませんか?
不動産情報サイトには「物件価格の7〜10%」なんて書いてあるけど、それだけを信じて大丈夫だろうか…。
夫婦で家計簿を広げてはみるものの、「で、結局いくらあれば安心なの?」と、答えの出ない問いに溜め息がこぼれる…。
そのお気持ち、痛いほど分かります。
でも、ご安心ください。この記事は、そんな漠然としたお金の不安を解消し、ご家族が安心してマイホーム計画を進めるための「信頼できる地図」となるものです。
住宅購入に精通したFPの視点から、最新の相場観はもちろん、知らないと後悔しかねない節約の知識まで、どこよりも丁寧に解説します。
読み終わる頃には、諸費用への不安が「よし、これなら大丈夫!」という確かな自信に変わっているはずです。さあ、一緒に未来の我が家への第一歩を踏み出しましょう。
住宅購入の諸費用、「物件価格の1割」はもう古い?

最初に、皆さんが最も気になっている結論からお伝えします。
かつて不動産業界の常識とされた「諸費用は、物件価格の1割を用意すればOK」という考え方は、残念ながら、現在の市場には当てはまらないケースが増えています。
もちろん、目安として完全に間違いではありません。しかし、この言葉だけを信じて資金計画を立てると、「想定より現金が数十万円も多く必要になった…」と、契約直前で慌てることになりかねません。
なぜ「1割」という目安が過去のものになったのか
昔の常識が通用しなくなった主な理由は、住宅ローンの手数料体系の多様化にあります。
一昔前は、どの銀行でローンを組んでも手数料は横並びで、物件種別による費用の差も少ない時代でした。
しかし、近年はネット銀行の台頭により、保証料を無料にする代わりに「借入額の2.2%」といった定率の事務手数料がかかるプランが主流になっています。
例えば、SBI新生銀行やauじぶん銀行、PayPay銀行など多くのネット銀行では、この「保証料0円+定率の事務手数料」というプランを採用しています。
4,000万円のローンを組んだ場合、事務手数料だけで88万円(税別)にもなり、これだけで物件価格の2%を超えてしまいます。
こうした新しい手数料体系の登場により、従来の「1割」という大雑把な括りでは、実態とズレが生じてしまうのです。
【一覧表】新築/中古/マンション別・諸費用の最新目安
では、今の時代、どれくらいを目安に考えれば良いのでしょうか。
最新情報として、物件の種類ごとの目安を以下にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせて、大まかな金額をイメージしてみてください。
| 物件の種類 | 諸費用の目安(物件価格に対して) |
| 新築マンション・注文住宅 | 3~6% |
| 新築戸建て(建売) | 6~9% |
| 中古マンション・中古戸建て | 6~10% |
物件の種類別・諸費用の目安
「え、中古の方が高いの?」と意外に思われたかもしれませんね。
中古物件は、売主と買主の間を取り持つ「仲介手数料」がかかるため、その分、諸費用が割高になる傾向があります。
このように、物件の種類によって目安は大きく異なります。次の章からは、これらの諸費用の具体的な内訳を一つひとつ、詳しく解説していきます。
購入時にかかる諸費用の全貌|見落としがちな7つの内訳
それでは、諸費用の具体的な中身を見ていきましょう。「え、こんなものまで?」と思うような費用も含まれているので、一つひとつ着実にチェックして、抜け漏れがないように準備を進めましょう。
① 税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税)
まずは、国や自治体に納める税金です。これらは必ず必要になる費用で、節約が難しい項目です。
- 印紙税:不動産の売買契約書や住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)に貼る印紙代です。契約金額によって異なり、例えば4,000万円の物件なら売買契約書に1万円、ローン契約書に2万円の印紙が必要です。
- 登録免許税:購入した土地や建物を「これは自分のものです」と法的に登録(登記)するためにかかる税金。土地の所有権移転や、建物の所有権保存、住宅ローンを借りる際の抵当権設定など、手続きごとに発生します。
税額は固定資産税評価額やローン借入額に一定の税率をかけて計算されますが、2027年3月31日までは軽減措置が適用され、税負担が軽くなっています。 - 不動産取得税:不動産を取得したことに対して、一度だけかかる税金です。忘れた頃(入居後半年~1年後)に都道府県から納税通知書が届くので驚かれる方も多いですが、これも諸費用の一部。一定の要件を満たす新築や中古住宅は大幅な軽減措置があり、支払いがゼロになるケースも少なくありません。
② 住宅ローン関連費用(事務手数料、保証料)
住宅ローンを組む際に、金融機関に支払う費用です。前の章で解説した通り、ここの金額が諸費用の総額を大きく左右します。
- 事務手数料:ローン契約の手続きに対する手数料です。数万円の「定額型」と、借入額の2.2%といった「定率型」があります。ネット銀行は定率型が多い傾向にあります。
- 保証料:万が一あなたがローンを返済できなくなった場合に、保証会社に代わりに返済してもらうための費用です。数十万円を一括で前払いする「一括前払い型」と、金利に0.2%程度上乗せして支払う「金利上乗せ型」があります。
③ 不動産会社に支払う仲介手数料
中古物件や一部の新築戸建て(建売)を購入する際に、不動産会社へ支払う成功報酬です。
諸費用の中でも特に大きなウェイトを占めます。法律で上限額が決められており、「(物件価格 × 3% + 6万円) + 消費税」が一般的な計算式です。
④ 登記を依頼する司法書士への報酬
自分で登記手続きをすることも不可能ではありませんが、手続きが非常に複雑なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。その際に支払う報酬で、相場は10万円~15万円程度です。
⑤ 必ず加入する火災保険・地震保険料
住宅ローンを組む際には、火災保険への加入が必須条件となります。
ここ数年、大規模な自然災害の増加や物価上昇の影響で保険料は歴史的な値上げが続いており、家計への影響も大きくなっています。
具体的には、2023年にかけての契約では全国平均で10.9%という大幅な値上げが実施されました。
さらに、2024年10月以降の契約・更新からは、過去最大となる全国平均13.0%もの引き上げが適用される見込みです。
保険料は、建物の構造(木造か鉄筋か)、所在地(都道府県)、補償内容、保険金額によって大きく変動します。特に、洪水や土砂災害のリスクを補償する「水災補償」の有無は保険料に大きく影響します。
あくまで目安ですが、東京都の木造一戸建て(保険金額2,000万円)の場合、地震保険を付帯し、基本的な補償(水災補償あり)を付けた場合の保険料は、5年契約で20万円~35万円程度がひとつの相場感となります。
ハザードマップを確認し、水災リスクが低いと判断できれば、水災補償を外すことで保険料を抑えることも可能です。
⑥ 引っ越し費用や家具・家電購入費
厳密な意味での諸費用とは少し異なりますが、住宅購入と同時に必ず発生するのがこれらの費用です。
特に、新居に合わせて家具や家電を新調すると、50万円~100万円以上かかることも。資金計画を立てる際には、忘れずに予算に組み込んでおきましょう。
⑦ その他(固定資産税清算金、水道加入金など)
- 固定資産税清算金:固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、年の途中で物件の引き渡しがあった場合、引き渡し日以降の税額を日割りで計算し、買主が売主へ支払うのが慣例です。
- 水道加入金:主に新築の注文住宅などで、新たに水道を利用する際に自治体へ支払う費用です。
【要注意】入居後にずっと続く「維持費」という名のランニングコスト

マイホームの購入は、ゴールではなく新たなスタートです。賃貸の家賃がなくなる代わりに、今度は「家を維持していくための費用」が継続的に発生します。これらを想定せずに住宅ローンを組んでしまうと、数年後に「こんなはずじゃなかった…」と家計が圧迫されかねません。
ここでは、特に重要な4つの維持費について解説します。
毎年かかる「固定資産税・都市計画税」
住宅を所有している限り、毎年必ず支払い続けるのが固定資産税と都市計画税です。
毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、4月~6月頃に自治体から納税通知書が届きます。
税額は、土地や建物の公的な評価額である「固定資産税評価額」を基に計算されますが、新築住宅や認定長期優良住宅などでは、一定期間、税金が減額される特例があります。
あくまで目安ですが、一般的な住宅の場合、年間で10万円~20万円程度の支払いを見込んでおくと良いでしょう。
マンションの宿命「管理費・修繕積立金」
マンションを購入した場合、上記の税金に加えて、毎月「管理費」と「修繕積立金」の支払いが発生します。
- 管理費:共用部分の清掃や電気代、エレベーターの保守点検など、マンションの日常的な維持管理に使われる費用です。
- 修繕積立金:十数年ごとに行われる外壁の塗り替えや防水工事、給排水管の交換といった大規模な修繕工事に備えて、住民全員で積み立てていくお金です。
つまり、この2つの合計額の平均は月額で約24,700円となります。住宅ローン返済とは別に、毎月この金額がかかり続けることになります。
また、同調査では、修繕積立金は築年数が経過するにつれて段階的に値上がりしていく傾向も明らかになっています。将来的な値上がりも想定しておくことが非常に重要です。
戸建てで見落とす「将来の修繕費」の積立
「戸建てなら管理費や修繕積立金がなくて楽だ」と考えるのは早計です。
戸建ての場合は、マンションのように強制的に徴収されないだけで、修繕が必要なタイミングで数百万円単位の出費が一度に発生します。
例えば、10年~15年後には外壁や屋根のメンテナンス(塗装・補修)で100万円~200万円、20年~30年後には水回りの設備交換で50万円~100万円といった費用がかかります。これらの将来の出費に備えて、ご自身で計画的に毎月1万円~2万円程度を貯蓄していく意識が非常に重要です。
火災保険料の更新とその他メンテナンス費用
購入時に支払った火災保険料は、契約期間(最長5年)が終われば、再度支払う必要があります。
先ほどもお伝えしましたが、近年は自然災害の増加で保険料は値上がり傾向にあります。そのため、更新時には以前より高くなっている可能性も十分にあります。
その他にも、
- シロアリ対策の費用(5年ごと)
- 庭の手入れ費用
- 固定資産税以外の自治会費
- ゴミステーションの運営費用
など、細かな出費も積み重なります。これらの費用も念頭に置き、余裕を持った資金計画を立てることが、安心してマイホームに住み続けるための秘訣です。
知っているだけで差がつく、諸費用の節約応用テクニック

基本的な節約術では満足できない、本気で諸費用と向き合いたいあなたへ。ここからは、私がお客様へのコンサルティングで、条件が合う方にだけこっそりお伝えしている、極めて効果の高い節約術を特別に公開します。これらは、あなたの行動次第で、将来にわたって大きな差を生む可能性を秘めています。
節約術①:固定資産税の「家屋調査」に必ず立ち会い、質問にだけ答える
この調査には必ず立ち会い、「聞かれたことにだけ、正直に答える」という姿勢を徹底してください。
例えば、職員から「この壁紙、素敵ですね」などと雑談を振られても、「ありがとうございます」と返すに留めます。「これはイタリア製の高級なもので…」などと自ら付加価値をアピールする必要は一切ありません。
なぜなら、設備のグレードが高いと判断されれば、その分、評価額が上がり、税金が高くなるからです。 過小に申告するのは脱税ですが、必要以上にアピールして、自ら税金を高くする必要はありません。この意識を持つだけで、長期的に見て大きな節約につながるのです。
節約術②:「つなぎ融資」の高金利を回避する、2つの裏ワザ
注文住宅を建てる際に発生する、高金利な「つなぎ融資」。これを回避、もしくは使わずに済む方法を知っているかどうかで、諸費用は数十万円単位で変わります。
時間はかかりますが、最も効果が高い方法です。金融機関の中には、住宅ローン本体を、土地代金や着工金、上棟金といった支払いのタイミングに合わせて分割で融資してくれるところがあります。
この方法なら、金利の低い住宅ローンを最初から利用できるため、つなぎ融資にかかる高額な利息や手数料(10万円~30万円以上)を丸ごとカットできます。
ネット銀行などは分割融資も使えず、つなぎ融資を用意していないケースも多いので注意が必要です。
もし分割実行できる銀行が見つからない場合、次に検討したいのが「親から一時的にお金を借りる」という選択肢です。
つなぎ融資が必要な期間は、長くても半年~1年程度。この期間だけ親御さんから無利息(もしくは低利息)でお金を借り、建物が完成して住宅ローンが実行されたら、そのお金で一括返済します。
ただし、ここで非常に重要なのが、必ず「金銭消費貸借契約書」を作成することです。
契約書がないと、税務署から「贈与」とみなされ、高額な贈与税がかかるリスクがあります。親子間でも必ず書面を交わし、「借りたお金であり、返済する意思がある」ことを明確にしておきましょう。
節約術③:司法書士は不動産会社の「紹介」を使わない
仲介手数料の交渉はハードルが高いですが、司法書士の選定は買主の自由です。不動産会社から「提携の司法書士がおりますので」と当たり前のように紹介されますが、その見積もりが最安値である保証はどこにもありません。(逆に司法書士から紹介料もらい割高になっているケースも)
ご自身でインターネットなどを使い、2~3社の司法書士事務所から見積もりを取ってみてください。
不動産会社の提携司法書士よりも2万円~5万円ほど安くなるケースは珍しくありません。 「登記手続きの見積もりをお願いしたいのですが」と電話やメールで連絡し、物件情報やローン借入額を伝えれば簡単に見積もりを出してくれます。
手間はわずかですが、確実な節約につながるポイントです。
節約術④:火災保険の「個人賠償責任保険」の重複をなくす
火災保険に加入する際、「個人賠償責任保険」という特約を勧められることがあります。これは、自転車で他人にケガをさせてしまったり、子どもがお店の物を壊してしまったりした際に補償してくれる、非常に重要な保険です。
しかし、この補償、実はあなたが加入している他の保険に付帯している可能性が非常に高いのです。
代表的なのは自動車保険やクレジットカードの付帯保険です。もし他の保険でカバーできているなら、火災保険で追加加入する必要は全くありません。
一度、ご自身の自動車保険の契約内容などを確認してみてください。この重複をなくすことで、年間の保険料を数千円~1万円程度節約できます。
節約術⑤:仲介手数料「半額」や「定額」の不動産会社も検討する
これは特に中古物件を探している場合に有効な手段です。近年、従来の「物件価格×3%+6万円」という上限額いっぱいの手数料を取る仲介会社だけでなく、「手数料半額」や「定額制」を掲げる新しいタイプの不動産会社が増えています。
もちろん、手数料が安い分、サービス内容が限定的(物件案内はセルフサービスなど)な場合もあります。
しかし、ご自身で積極的に物件を探せる方や、サポートは最低限で良いと考える方にとっては、100万円近い仲介手数料を数十万円に圧縮できる、非常にインパクトの大きい選択肢となり得ます。
サービス内容と手数料のバランスをよく見極め、選択肢の一つとして検討する価値は十分にあります。
【価格別】我が家の諸費用はいくら?簡単シミュレーション
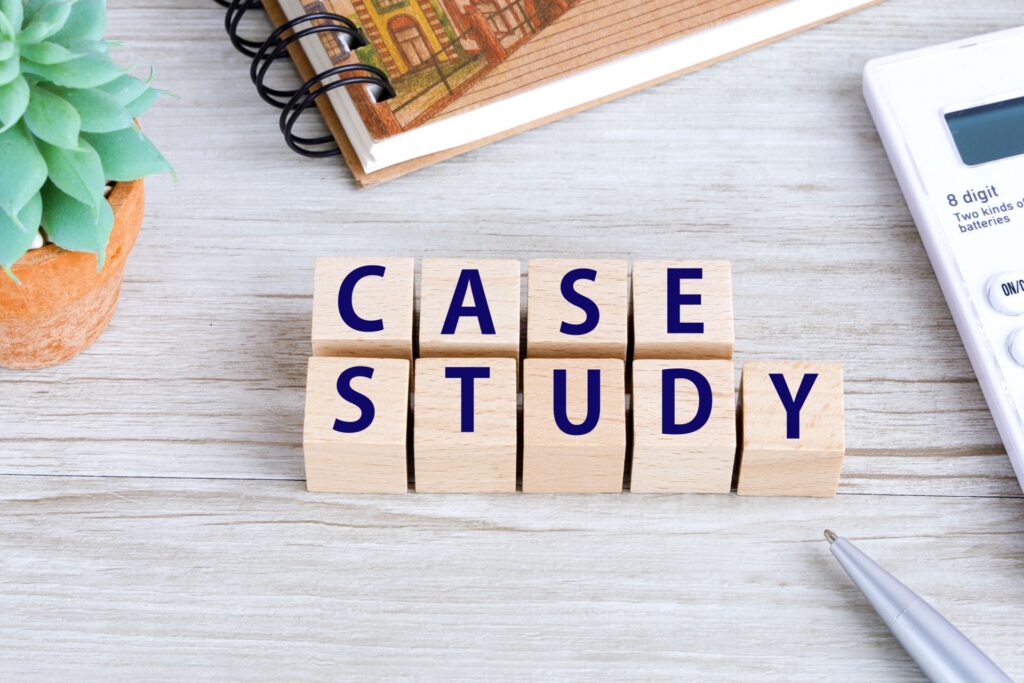
ここまでの解説で、諸費用の内訳や節約術についてはご理解いただけたかと思います。最後のセクションでは、「で、結局うちの場合は総額でいくらくらい準備すればいいの?」という疑問にお答えするために、具体的な2つのモデルケースでシミュレーションをしてみましょう。
ご自身の状況と近いケースを参考に、必要な現金の全体像をイメージしてみてください。
※以下のシミュレーションは、一般的な諸費用率や税率(2025年9月時点)を基にした概算です。実際の金額は、物件の評価額や利用する金融機関、保険の契約内容によって変動します。
ケース1:4,000万円の新築戸建て(建売)を購入した場合
30代のご夫婦が、初めてのマイホームとして4,000万円の新築建売住宅を購入。住宅ローンは物件価格と同額の4,000万円を、ネット銀行の「事務手数料型(借入額の2.2%)」で借り入れるケースです。
| 費用の内訳 | 金額の目安 | 備考 |
| 仲介手数料 | 0円~約139万円 | 売主(不動産会社)から直接購入すれば0円。仲介会社を介すと発生。 |
| 印紙税 | 3万円 | 売買契約書(1万円)+ローン契約書(2万円) |
| 登録免許税 | 約23万円 | 土地・建物の登記、抵当権設定登記にかかる税金(軽減措置適用後) |
| ローン事務手数料 | 約97万円 | 4,000万円 × 2.2% + 消費税 |
| ローン保証料 | 0円 | 事務手数料型のため |
| 司法書士報酬 | 約12万円 | 登記手続きの代行費用 |
| 火災保険料 | 約25万円 | 地震保険付き・5年契約の場合 |
| 不動産取得税 | 0円~数万円 | 軽減措置により0円になることが多い |
| その他 | 約10万円 | 固定資産税清算金など |
| 合計(仲介手数料0円の場合) | 約170万円 | (物件価格の約4.3%) |
| 合計(仲介手数料ありの場合) | 約309万円 | (物件価格の約7.7%) |
ケース1:4,000万円の新築戸建て(仲介手数料あり)の諸費用内訳
ケース2:5,000万円の中古マンションを購入した場合
40代のファミリーが、都心部で5,000万円の中古マンションを購入して住み替えるケース。住宅ローンは4,500万円を、同じくネット銀行の「事務手数料型」で借り入れると想定します。
| 費用の内訳 | 金額の目安 | 備考 |
| 仲介手数料 | 約172万円 | (5,000万円×3%+6万円)+消費税 |
| 印紙税 | 3万円 | 売買契約書(1万円)+ローン契約書(2万円) |
| 登録免許税 | 約20万円 | 土地・建物の登記、抵当権設定登記にかかる税金(軽減措置適用後) |
| ローン事務手数料 | 約109万円 | 4,500万円 × 2.2% + 消費税 |
| ローン保証料 | 0円 | 事務手数料型のため |
| 司法書士報酬 | 約12万円 | 登記手続きの代行費用 |
| 火災保険料 | 約15万円 | 鉄筋コンクリート造のため、戸建てより割安 |
| 不動産取得税 | 約5万円 | 築年数によっては軽減措置が使えない場合も |
| その他 | 約15万円 | 固定資産税清算金など |
| 合計 | 約351万円 | (物件価格の約7.0%) |
ケース2:5,000万円の中古マンションの諸費用内訳
よくある質問とその回答(FAQ)
- Q1. 貯金がギリギリです。「諸費用ローン」を使っても大丈夫でしょうか?
-
金融機関によっては諸費用も住宅ローンに含めて借りられる商品を扱っています。手元の現金を残せるメリットはありますが、借入額が増える分、毎月の返済額や総支払利息が増加します。将来の教育費などを考慮し、安易に利用せず慎重に判断することが重要です。
- Q2. 諸費用はいつ、どのタイミングで支払うのが一般的ですか?
-
費用によって支払うタイミングは異なります。例えば、印紙税は売買契約時に、仲介手数料は契約時と引き渡し時に半金ずつ、登録免許税や司法書士報酬などは物件の引き渡し日に支払うのが一般的です。不動産取得税は入居後、半年ほど経ってから納税通知書が届きます。
- Q3. 今回のシミュレーションにない、中古物件のリノベーション費用はどう考えればいいですか?
-
リノベーション費用は物件価格とは別に考える必要があります。住宅ローンと一体で借りられる「リフォーム一体型ローン」を利用すれば、別途ローンを組むより金利を抑えられます。ただし、その分、借入額が大きくなるため、諸費用も変動することを念頭に置いておきましょう。
- Q4. 頭金がゼロでも本当に家は買えますか?
-
はい、物件価格の100%をローンで借りる「フルローン」を利用すれば購入は可能です。しかし、借入額が大きくなるため審査のハードルは上がります。また、将来不動産価格が下落した際に、家の価値がローン残高を下回る「担保割れ」のリスクが高まる点には注意が必要です。
- Q5. 夫婦でペアローンを組む場合、諸費用は高くなりますか?
-
はい、高くなる可能性があります。ペアローンは夫婦それぞれが1本ずつ、合計2本のローン契約を結ぶ形になります。そのため、ローン契約書に貼る印紙税がそれぞれに必要になったり、登記手続きが複雑になることで司法書士報酬が割高になったりする場合があります。
まとめ:お金の不安を解消し、後悔のないマイホーム購入を
新築か中古か、仲介手数料の有無で金額は大きく変動します。まずはご自身のケースで、最新の相場観を把握することが最初のステップです。
住宅ローン返済に加え、固定資産税や将来の修繕費も必ず予算に組み込みましょう。特に戸建ては、自主的な積み立て計画が必須です。
住宅ローン、火災保険、司法書士、引っ越し業者。不動産会社のおすすめを鵜呑みにせず、必ず相見積もりを取る一手間が数十万円の差を生みます。
固定資産税の家屋調査への立ち会い、「つなぎ融資」の回避策など、知っている人だけが得をする節約術も。正しい知識で、支払う必要のないお金はしっかり守りましょう。
シミュレーションで具体的な金額をイメージすることが、漠然としたお金の不安を「これなら大丈夫」という自信に変えてくれます。