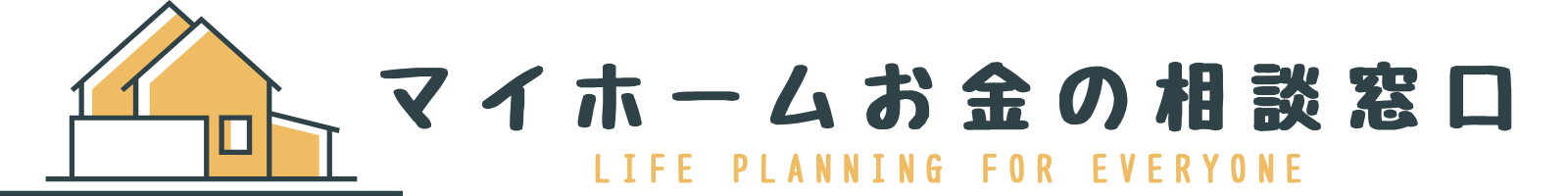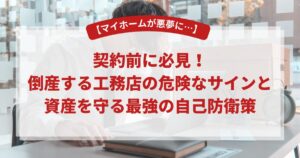【マイホームが悪夢に…】契約前に必見!倒産する工務店の危険なサインと資産を守る最強の自己防衛策
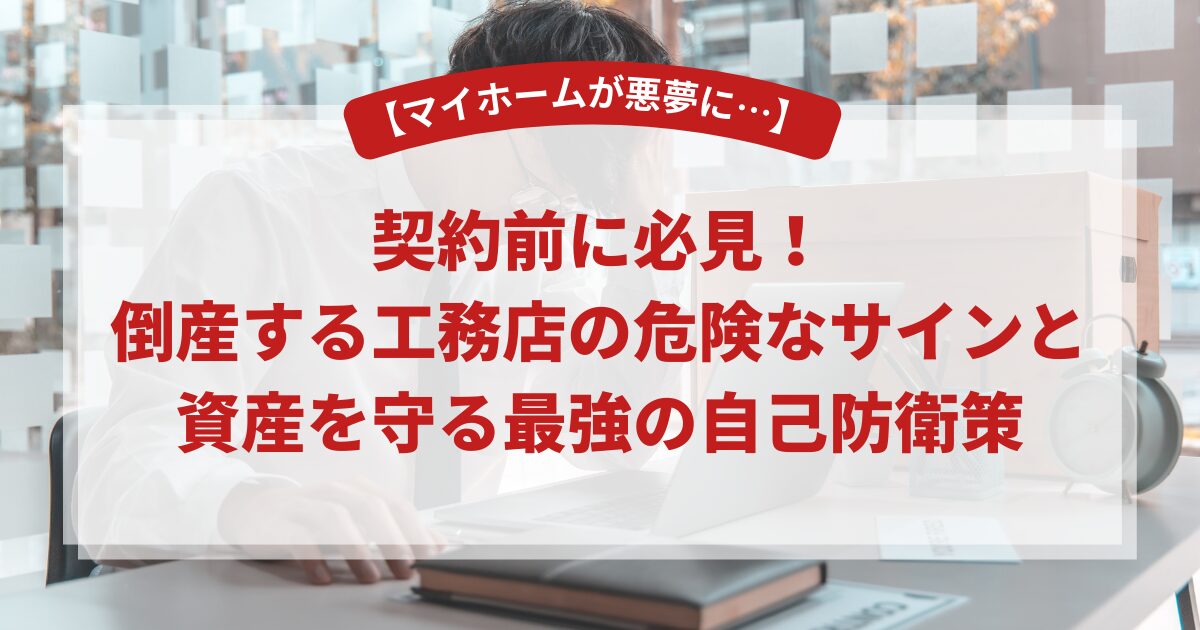
夢のマイホーム計画、順調に進んでいますか?
デザインも間取りもこだわり抜いて、信頼できる工務店も見つかった。「この担当者さん、本当にいい人だな…」なんて、家づりのパートナーとの出会いに胸を躍らせている頃かもしれませんね。
でも、その一方で、心のどこかで「この会社、本当に大丈夫かな…?」なんて、ふと不安がよぎることはありませんか?
その直感、実はものすごく大切なんです。なぜなら今、建設業界は資材高騰や人手不足の影響で、過去最多の倒産ラッシュに見舞われているから。
帝国データバンクの調査(※2025年7月発表)によると、2025年上半期(1〜6月)の建設業の倒産件数は986件。これは、なんと過去10年で最多のペースです。
実際に「2000万円を失い、更地に35年ローンだけが残った…」なんて、
悪夢のような事態に陥ってしまった施主も後を絶ちません。
でも、安心してください。この記事では、数多くの住宅購入相談に乗ってきたFPの視点から、契約前に「危ない工務店の危険なサイン」を見抜き、あなたの大切な資産と家族の未来を守るための『最強の自己防衛策』を、どこよりも分かりやすく解説します。
専門知識は一切不要です。 正しい知識で武装すれば、工務店倒産は決して怖くありません。さあ、最高の家づくりのために、最後の知識チェックを始めましょう!
なぜ今、工務店の倒産が急増しているのか?知られざる3つの背景、さらに・・・

「うちの担当さんは誠実だし、きっと大丈夫」
そう思いたい気持ち、痛いほどわかります。しかし今、多くの工務店が、一社の努力だけではどうにもならないほどの逆風に晒されているのが現実です。
結論から言うと、工務店の倒産は、単なる経営努力の不足ではなく、
「資材高騰」「人手不足(2024年問題)」「多重下請け構造」という、業界全体を揺るがす3つの構造的な問題が複雑に絡み合って急増しています。
なぜ、あなたの家づくりをお願いしようとしている、あの工務店も例外ではないのか。その恐ろしい背景を一つずつ見ていきましょう。
① 止まらない「資材高騰」の波
建設資材価格指数の推移
まず一つ目の大きな要因が、終わりの見えない「資材高騰」です。
数年前のウッドショックは記憶に新しいですが、その後も世界的なインフレや円安の影響で、木材だけでなく、窓や断熱材、金属製品といったあらゆる建材の価格が高止まりしています。
帝国データバンクの最新調査によれば、建設業の倒産理由で最も多いのが「販売不振」ですが、その背景には、この資材高騰分を工事価格にうまく転嫁できず、利益を圧迫されている実態があります。
工務店にとって地獄なのは、「施主と契約した時点」から「実際に資材を発注する時点」までにタイムラグがあることです。
例えば、半年前の材料費で見積もりを出して契約したのに、いざ着工しようとしたら材料費が2割も上がっていた…。
これでは、施主に「すみません、赤字になるので追加で500万円ください」とは(よほどの契約でない限り)言えません。
結果、工務店は「やればやるほど赤字」という、悪夢のような状況に陥っているのです。
② 職人が消える「2024年問題」とその影響
二つ目の要因が、建設業界の働き方を根本から揺るがしている「2024年問題」です。
2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。これは働く人の環境を良くするための大切なルールですが、もともと高齢化と人手不足が深刻だった業界にとっては、ボディブローのように効いています。
施行から1年半が経過した今、現場では「残業ができない分、工期が延びる」「若手の職人がますます集まらない」「結果的に人件費が高騰する」という三重苦に陥っているケースが少なくありません。
これは会社経営で言えば、優秀な人材を確保するための採用費や給料(人件費)がどんどん上がっているのに、お客様に提供する商品の価格にはなかなか転嫁できない、という状況によく似ています。
売上は変わらないのにコストだけが増え続けていくのですから、経営体力のない工務店が先に悲鳴を上げてしまうのは、想像に難くないでしょう。
③ 業界特有の「多重下請け構造」という闇
そして三つ目が、業界に根強く残る「多重下請け構造」です。
注文住宅の世界も、元請けの会社(ハウスメーカーや工務店)から、基礎工事、大工工事、電気工事…と、専門業者へ仕事が発注されていくピラミッドのような構造になっています。
この構造自体が悪いわけではありませんが、問題は、資材高騰や人件費上昇といったコストアップのしわ寄せが、ピラミッドの下に行けば行くほど厳しくなる点です。
元請けからの発注金額が据え置かれれば、下請けの工務店はそのコスト増を自社で吸収するしかありません。
まるで巨大なジェンガのように、上のブロック(元請け)が少しコストカットをしただけで、一番下のブロック(下請け工務店)が一気に崩れ落ちてしまうような、非常に不安定なバランスの上で成り立っているのです。
これら3つの要因は、どれか一つではなく、すべてが複雑に絡み合って工務店の経営を圧迫しています。
だからこそ、「あの工務店は大丈夫」という性善説だけでは、もはや通用しない時代になっているのです。
追い打ちをかける更なる問題【ゼロゼロ融資の返済本格化(体力の限界)】
どめの一撃が、これです。
「ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)」という言葉を、コロナ禍で耳にしたかもしれません。
多くの中小企業が、この融資のおかげでパンデミックを何とか生き延びました。
ですが、その返済が、2024年頃から本格的に始まっています。
先ほど述べた「資材高騰」と「人手不足」で、利益がほとんど出ていない(あるいは赤字の)状態で、借金の返済だけがスタートしてしまったのです。
これでは、どんなに真面目に経営してきた工務店でも、倒産リスクと無縁ではいられません。
「うちの工務店は真面目だから」
「担当の〇〇さんが誠実だから」
残念ながら、その「誠実さ」は、この巨大な嵐(倒産の背景)の前では、何の防波堤にもならないのです。
では、もし万が一、あなたの信じた工務店がこの嵐に飲み込まれてしまったら…?
次の章で、施主であるあなたを襲う「地獄のリアル」を、時系列に沿って解説します。
「家もお金も失う…」工務店倒産で施主を襲う3つの地獄
建設業の倒産件数の推移
前の章で解説した工務店を取り巻く厳しい背景。
「大変な時代なんだな」と他人事のように思うかもしれませんが、もし、その矛先があなたの契約した工務店に向いたら…?
夢のマイホーム計画は一転、悪夢へと変わります。
工務店が倒産した時、施主を襲うのは、言葉通り「家もお金も失う」地獄のような現実です。
具体的に起こる悲劇を3つの側面に分けて解説します。
① ローンだけが残り、追加費用は数百万…終わらない資金繰り
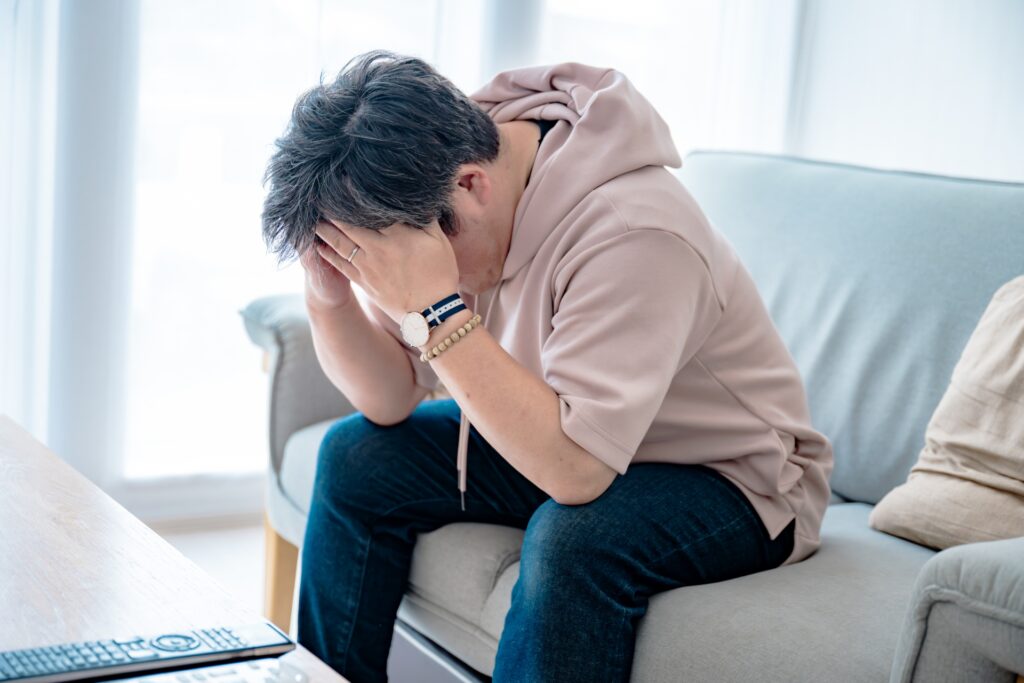
まず施主を襲うのが、強烈な金銭的なダメージです。
多くの注文住宅の契約では、契約時、着工時、上棟時など、工事の進み具合に応じて代金を支払います。しかし、多くの場合、工事の進捗よりも多めの金額を前払いしているのが実情です。
もし工務店が倒産すれば、すでに支払ったお金(着工金や中間金)は、ほぼ1円も戻ってきません。
しかし銀行は待ってくれませんから、住宅ローンの返済だけは容赦なく始まります。つまり、「家は骨組みのままなのに、毎月ローンだけが引き落とされる」という、悪夢としか言いようのない状況に陥るのです。
さらに地獄は続きます。
工事を引き継いでくれる別の工務店を探す必要がありますが、その費用は割高になることがほとんど。
現場の調査費用や、場合によっては一度作った部分の解体・補修費用など、数百万単位の追加費用を請求されるケースも珍しくありません。まさに、泣きっ面に蜂の状態です。
② 工事はストップ、次の担い手も見つからない八方塞がり
次に訪れるのが、精神と時間を削られる「八方塞がり」の状態です。
倒産と同時に、あなたの家の工事は完全にストップします。
弁護士(破産管財人)が介入して財産状況などを整理し始めるため、施主といえども勝手には何もできません。この手続きだけでも、数ヶ月単位で時間が過ぎていきます。
その間、当然ながら次の工務店を探さなければなりません。
しかし、他社が建てかけた中途半端な物件を引き継ぐのは、責任の所在が曖昧になるため、多くの工務店が嫌がります。
「前の業者の施工に問題があったらどうするんだ?」と断られ続け、何十社も電話をかけ続けた…という話も、決して珍しくないのです。
完成の目処が立たないまま、仮住まいの家賃やローン返済は続き、時間だけが過ぎていく。
この焦りと不安は、経験した人でなければわからない、本当に過酷なものです。
③ ある日突然、現場から資材が消える衝撃の事態
そして、施主の心を最も打ちのめすのが、信じがたい裏切りとも言えるこの事態です。
それは、現場に運び込まれていた資材や、すでに取り付けられていたはずの設備が、ある日突然ごっそりと消えるというものです。
「泥棒!?」と思うかもしれませんが、そうではありません。
倒産した工務店に商品を納入していた下請けの業者(例えば、サッシ屋さんやキッチンメーカーなど)が、代金を回収できない腹いせに「自分たちの商品を回収していく」という実力行使に出ることがあるのです。
昨日までそこにあった窓枠や、設置されたばかりのシステムキッチンが、無残にも取り外されている…。
そんな光景を目の当たりにした施主の絶望は、計り知れません。法的に誰の所有物かという難しい問題もあり、施主はなすすべもなく立ち尽くすしかないケースがほとんどです。
これらは決して大げさな話ではなく、実際に日本中で起こっている「マイホームの失敗」のリアルな姿なのです。

「そんなの、ドラマの中の話でしょ?」
こんなふうにおっしゃる方も多いですが、現実の問題としてこのような被害に苦しんでおられる方がたくさんいらっしゃいます。
それでも半信半疑の方は、一度YouTubeなどで「工務店 倒産 施主」や「欠陥住宅 施主」と検索してみてください。以下のような動画がたくさんUPされています。
では、このような最悪の事態を避けるために、私たちは契約前に何を確認すればいいのでしょうか。次の章で、具体的なチェックリストを見ていきましょう。
【契約前の最終警告】倒産の危険サインを見抜け!違和感チェックリスト


前の章で解説した悲劇は、ある日突然、何の予兆もなくやってくるわけではありません。
それは、お金の流れや担当者の言動に現れる、小さな「違和感」です。
家づくりという高揚感の中で見過ごしてしまいがちな、しかし、あなたの未来を守るためには絶対に見逃してはならない危険なサイン。
ここでは、多くの被害者や専門家が指摘するポイントを、契約前の最終チェックリストとしてまとめました。
□ 見積もりが異常に安い、または「一式」ばかりで不透明
相見積もりを取った際、一社だけが数十万〜百万円単位で安い見積もりを出してきたら、それは「喜び」ではなく「警戒」のサインかもしれません。
なぜなら、それは
赤字覚悟で契約を取り、その契約金を別の現場の支払いに充てる「自転車操業」の典型的な手口
である可能性があるからです。
「とにかく今、現金が欲しい」という、会社の悲鳴とも考えられます。
また、見積書の内訳が「〇〇工事一式」と大雑把な場合も要注意です。
後から「これは含まれていませんでした」と高額な追加費用を請求されたり、見えない部分で建材のグレードを落とされたりするリスクも潜んでいます。
□ 打ち合わせの議事録がなく、言った言わないのトラブルが頻発
打ち合わせのたびに議事録を作成し、施主と共有するのは、誠実な会社であれば当然のプロセスです。
これが徹底されていない場合、もちろん単純にルーズな会社の可能性もありますが、経営が苦しい会社ほど、議事録作成のような「直接利益を生まないが重要な業務」を省略しがちです。
また、社員の入れ替わりが激しく、担当者間の引き継ぎが全くできていないという、社内が混乱しているサインかもしれません。「前の担当者はこう言いました」が通用しない状況は、非常に危険です。
□ 担当者が常に疲弊し、一人で何役もこなしている
あなたの担当者は、いつも忙しそうで、なんだか疲れていませんか?
営業から設計、現場監督まで一人の担当者が兼任している場合、その人はスーパーマンに見えるかもしれません。
しかし、それは
深刻な人手不足により、社員一人ひとりがキャパシティを超えた業務を抱えている裏返しです。
このような状況では、当然ミスや確認漏れが頻発し、工期の遅延にもつながります。
そして何より、社員を大切にできない会社が、顧客の家を大切にできるでしょうか。その疲弊した担当者の姿は、会社の経営状態そのものを映している鏡かもしれないのです。
□ 工事の進捗を無視した不自然な前払いを要求してくる
これは、数あるサインの中でも最も危険度の高い警告です。
例えば、「まだ基礎工事も始まっていないのに、『人気のキッチンを確保するために』と言って、中間金の支払いを急かしてくる」「契約書に定められたタイミングより早く、次の支払いを催促してくる」といったケースです。
これは、会社の運転資金が底をつきかけ、あなたの支払うお金を、別の現場の支払いや経費の穴埋めに使おうとしている可能性が極めて高いサインです。
この要求に応じれば、あなたの支払ったお金は、あなたの家のためには使われず、そのまま消えてしまうリスクがあります。
これらのサインが一つでも当てはまったら、すぐに契約するのではなく、一度立ち止まって冷静に考える勇気を持ってください。
そして次の章で解説する「最強の自己防衛策」で、その会社の健全性を徹底的に裏付け調査するのです。
知るだけで未来が変わる!資産を守る最強の自己防衛策


前の章のチェックリストを見て、「もしかして、うちも…?」と不安になった方もいるかもしれません。でも、ここからが本番です。
危険なサインに気づくだけでなく、契約前に客観的なデータに基づいて「本当に信頼できる会社か」を自ら見抜く方法が存在します。
「担当者を疑うようで気が引ける…」と感じる必要は全くありません。
これは、あなたが心から安心して大切な家づくりを任せるための、そして最高のパートナーと出会うための、いわば「お守り」のような知識です。
ここからは【情報収集】【契約】【着工後】の3つのステップに分けて、誰にでも実践できる最強の自己防衛策を伝授します。
STEP1【情報収集】会社の健全性をデータで裏付ける
担当者の人柄やデザインの良さといった「感覚」に加えて、会社の経営状態という「客観的な事実」を把握することが、失敗しない工務店選びの鉄則です。
「住宅完成保証制度」への加入は、強力な安心材料になる
まず、工務店選びの大きな判断材料となるのが「住宅完成保証制度」への加入の有無です。
加入している工務店は、第三者機関の審査をクリアしている証でもあり、それだけで一定の信頼性があると言えるでしょう。もし検討している工務店が加入しているなら、それは大きなプラスポイントです。
しかし、たとえ加入している場合でも、この制度を過信してはいけないという点は覚えておいてください。
多くの場合、保証には上限額(工事費用の20%以内、かつ上限1,100万円など)が定められています。
例えば3,000万円の家を契約し、1,500万円を支払った時点で倒産した場合、保証額の上限を超えた損失分や、新しい工務店に支払う割増費用などで、結局は数百万単位の追加費用(自己負担)が発生する可能性が十分にあります。
あくまで「加入していれば、より安心できるお守り」と捉え、制度としては完全ではないですが、保証会社の審査をクリアした一応財務状況は安心できそうな状態、くらいで考えてきましょう。
完成保証に加入していても「時間」と「精神的コスト」は一切保証されない
さらに絶望的なのは、お金以外の「コスト」は一切保証対象外であることです。
- 引き継ぎ先を探すための、何十社にもわたる交渉
- 倒産した工務店とのやり取り、債権者集会への出席
- 工事が中断している間の、仮住まいの家賃
- 弁護士への相談費用
- そして何より、家族全員が被る「精神的な苦痛」
これらにかかる膨大な「時間」と「お金」、そして「心の消耗」は、誰も補償してくれません。
保証制度は、あくまで「最低限の建物」を完成させるためのものであり、あなたの失われた日常を取り戻してくれるものではないのです。
「完成保証に入っているから大丈夫」
その安心感が、いかに脆い砂上の楼閣であったか、お分かりいただけたでしょうか。
「お守り」は、気休めにはなっても、あなたの大切な資産を守る「盾」にはなりません。
STEP2【契約】不利な契約を結ばない防御術
情報収集をクリアし、信頼できる会社だと確信できたら、いよいよ契約です。ここでも命綱となる2つのポイントを押さえましょう。
- 支払い方法は「出来高払い」を交渉する
一般的な支払い(契約時10%・着工時30%・上棟時30%・完成時30%など)は、工務店側の資金繰りの都合が大きく、施主にとってはリスクが高い方法です。
可能であれば、工事の進捗に合わせて支払う「出来高払い」にできないか交渉してみましょう。それが難しくても、支払いの回数を細かく分けるなど、「工事の進み具合以上に、前払いするお金を極力減らす」意識が大切です。 - 契約書は専門家とダブルチェック!
契約書は非常に重要です。最低でも「工事が遅れた場合の遅延損害金」と「契約解除の条件」の2点は必ず自分の目で確認してください。
もし少しでも不安があれば、数万円の費用はかかりますが、第三者の建築士や弁護士に契約書をチェックしてもらう「契約書チェックサービス」などを利用するのも、安心を買うという意味で非常に有効な手段です。
STEP3【着工後】最高のパートナーと家を完成させるために


契約後も、完全に安心しきってはいけません。家が建つその日まで、2つのことを心がけましょう。
- 現場の「空気」に勝る情報なし!こまめな現場訪問の重要性
できるだけ頻繁に現場に足を運びましょう。職人さんたちへの感謝を伝え、コミュニケーションを取ることで、現場の雰囲気が良くなります。
それだけでなく、現場が綺麗に整頓されているか、資材は順調に搬入されているかなど、現場の「空気」から会社の状態をうかがい知ることもできます。 - 最終関門!「所有権登記」を速やかに行い、権利を確定させる
建物が完成し、引き渡しを受けたら、速やかに「建物の所有権保存登記」を行いましょう。これにより、その建物が法的にあなたの所有物であることが国に登録され、第三者に対して権利を主張できるようになります。
通常は司法書士に依頼しますが、引き渡し後、間を置かずに行うことが重要です。(※ほとんどの場合は「引渡し」=「住宅ローン融資実行」となるので、その際に保存登記なども同時に行うため問題ありません)
「人柄」や「保証」で選ぶのはギャンブル。資産を守る唯一の道は「経営・資産状況」の把握


ここまでの話をまとめましょう。
- 「担当者の人柄」 …残念ながら、会社の経営体力とは無関係です。
- 「現場がキレイ」 …大切な要素ですが、倒産しない直接の証拠にはなりません。
- 「完成保証制度」 …万が一の際の「足切り」にはなっても、「安心の盾」にはならない、気休めのお守りです。
もうお分かりですね。
私たちが家づくりという何千万円もの契約をする上で、これまで「決め手」だと思っていたこれらの要素は、すべて「倒産しないこと」の直接の証明にはならないのです。
極端な話、「人柄」や「保証」だけで工務店を選ぶのは、中古車を買うときに「営業マンの人柄」だけで決めるようなものです。
あなたが本当に知りたいのは、「その車のエンジンは壊れていないか?(=経営状況)」「車体はサビていないか?(=資産状況)」のはず。
それを見ずに契約するのは、ただの「ギャンブル」です。



マイホームという、家族の未来を乗せる買い物で、ギャンブルをするわけにはいきませんよね
私たちが本当に知るべき、唯一の答え。
それは、その工務店の「今の経営状況(お金はちゃんと回っているか?)」と「資産状況(いざという時の体力は十分か?)」という【揺るぎない数字の事実】です。
人柄のような曖昧なものではなく、客観的なデータこそが、あなたと家族の資産を守る唯一の盾となるのです。
「なるほど、会社の数字が大事なのはわかった」
「じゃあ、次の打ち合わせで『決算書、見せてもらえますか?』って聞いてみよう」
…もし、あなたがそう考えたなら、絶対に待ってください。
その行動が、あなたの家づくりを最悪の方向に導く「危険な一手」になるかもしれない理由を、次の章でお話しします。
「決算書、見せてもらえますか?」が危険な理由


家という何千万円もの契約をするのですから、「会社の経営状況を見せてほしい」と要求するのは、施主として当然の権利だと思うかもしれません。
しかし、FPとして数多くの工務店との取引経験から言うと、この「決算書見せてください」アタックは、ほぼ100%失敗するか、仮に成功しても意味がないのです。
危険な理由1:そもそも見せてくれない(関係悪化リスク)
まず、ほとんどの工務店は、赤裸々な経営データである決算書を、契約前の一般客に見せることはありません。
それは、あなたが病院に行って、いきなり「そこの患者さんのカルテ、全部見せてください」と言うのと同じくらい、非常識と受け取られかねない行為です。
もし運良く見せてくれたとしても、内心では「この客は、うちを信用していないのか」「面倒くさい客だ」というネガティブな印象を持たれてしまいます。
家づくりは、契約してからが本当のスタート。
何ヶ月、時には1年以上も続く共同作業のパートナーと、スタートラインに立つ前から関係を悪化させるのは、致命的な悪手と言えるでしょう。
仮に見せてくれるとしてもほぼ契約が決まりそうな【契約直前】くらいでしょうか。
危険な理由2:見せてもらっても「読めない」(暗号文と同じ)
そして、これが最も重要な理由です。
仮に、工務店の社長が「いいですよ、どうぞ」と快く分厚い決算書の束を渡してくれたとしましょう。
あなたは、その数字の羅列から、何を読み取ればいいか分かりますか?
- 「自己資本比率」が何%あれば安全?
- 「流動比率」って何?
- 「営業キャッシュフロー」がマイナスだったら、即アウト?
おそらく、チンプンカンプンですよね。
そうです。ご指摘の通り、「判断基準」がわからなければ、【決算書は暗号文】と同じなのです。
素人がそれを眺めて「ふむふむ、黒字ですね」なんて言っても、それは何の安心材料にもなりません。会社は、黒字でも倒産する(黒字倒産)からです。
「じゃあ、どうしろっていうんだ!」
「会社に聞いてもダメ。見てもわからない。もう、運任せしかないのか…?」
いいえ、諦めるのはまだ早いです。
実は、あります。
工務店にバレずに、合法的に、かつ「判断基準」がわからなくても「危険度」をあぶり出せる、工務店のコンサルなどを行う財務の専門家が実践している調査術が。
次の章で、その「答え」をお話しします。
【限定公開】「財務のプロ」の視点で暴く「倒産リスク調査術」のすべて


「担当者の人柄」や「完成保証」というお守りに、あなたの大切な資産と家族の未来を預けるのは、もうやめにしませんか?
「でも、専門家に調査を頼むお金なんてない…」
その必要もありません。
それは、私たちFP(ファイナンシャルプランナー)や経営コンサルタントが、企業の「財務(お金の流れ)」を見るときに実践している「プロの視点」そのものです。
そして、その「判断基準」も、難しい会計知識は一切不要です。



そのための「財務のプロの視点」を、今回、1冊の【完全版】マニュアルとして体系化しました。
それが、『9割の施主が知らない 「潰れる工務店」の予兆! 契約金500万円を失う前に 元住宅ローン会社役員のFPが教える工務店倒産を見抜く全知識』です。
この記事では紙幅の都合上、その具体的な手順を明かすことはできませんが、このマニュアルであなたが手に入れられる「未来」の一部をご紹介します。
- 工務店にバレずに「経営・資産状況」がわかる“ある情報”に合法的にアクセスする全手順
(もう「決算書見せてください」と関係を悪化させる必要はありません) - 決算書は不要!「財務のプロ」が注目する“たった3つ”の危険な数値を見抜く方法
(膨大な数字の羅列から、本当にヤバいサインだけをピンポイントで抜き出します) - 【マニュアル限定特典】難しい会計用語一切なし!『小学生でもわかる』倒産危険度〇×診断シート
(ご指示の通り、このシートを埋めるだけで、誰でも安全性が判定可能。あなたの「判断基準」になります) - 万が一の際にも資産を守る、契約書の『魔法の一文』とは
(倒産後でもあなたの資産が差し押さえられないよう、契約書に加えるべき“お守り”ではない“本物の盾”です)
このマニュアルは、経営状況の詳細な調査方法や判断基準、打ち合わせの中から倒産のリスクを見抜くためのチェックリストなど「財務のプロの実践知」そのものです。
「家は骨組みのまま、ローンだけが残った…」
そんな最悪の事態を回避し、心から安心して家づくりを楽しむための「最強の防衛策」を、この一冊に詰め込みました。
価格は、今後9,980円での販売を予定しています。
しかし、この倒産ラッシュの危機的状況を受け、不安を抱えてお気に入りの工務店での住宅建築に悩んでいるたくさんの方にお役に立ちたい一心から、この記事を読んでくださった方限定で、発売開始72時間のみ、4,980円でご提供します。
考えてみてください。
答えは、もう出ているはずです。
あなたの家づくりを「悪夢」にしないための、賢明なご判断をお待ちしています。
よくある質問とその回答
- Q1. もう契約済み、あるいは着工後なのですが、今からできる対策はありますか?
-
もっとも不安な状況ですね。契約後・着工後にできることは限られますが、諦めてはいけません。まずは契約書を再確認し、工事の進捗と支払い額のバランス(工事が遅れているのに、支払いが先行しすぎていないか)をチェックしてください。
その上で、マニュアルで解説している「財務状況の調査術」を実行し、現状のリスクレベルを把握することは、万が一の事態に備える上で非常に重要です。 - Q2.やはり大手ハウスメーカーの方が、倒産の心配はありませんか?
-
「大手だから絶対に安心」とは言い切れません。確かに体力のある会社は多いですが、過去には上場企業や大手ハウスメーカーが経営危機に陥った事例も存在します。2009年には全国に支店を構えていた富士ハウスが約640億円もの負債を抱えて倒産した事例もあります。
会社の規模の大小という「イメージ」で判断するのではなく、マニュアルで解説しているような客観的な「数字の事実」で経営の健全性をチェックする視点は、相手が工務店であれハウスメーカーであれ、等しく重要です。 - Q3.会話の中で「危ない工務店」を見抜く、魔法の質問はありませんか?
-
本文でも触れた通り、「人柄」で見抜くのは非常に困難です。しかし、ヒントはあります。例えば「最近の資材高騰や人手不足、経営への影響は正直どうですか?」とストレートに聞いた時、曖昧に言葉を濁したり、「うちは全く問題ないです」と根拠なく楽観論を述べたりする会社は、少し注意が必要かもしれません。とはいえ、それも印象論。最終的には客観的な数字の裏付けが不可欠です。
- Q4. 倒産のサインに気づいた場合、どこに相談すればいいですか?
-
契約前であれば、その会社との契約を見送ることが最善の策です。もし契約後や着工後に不安を感じた場合は、一人で悩まず専門家に相談してください。
具体的な相談先としては、弁護士や、国土交通大臣指定の住宅専門相談窓口である「住まいるダイヤル」、各都道府県の「建設工事紛争審査会」などがあります。早期の相談が被害を最小限に食い止める鍵となります。
- Q5. マニュアルを購入すれば、100%倒産を回避できますか?
-
将来を100%予測することは、残念ながら誰にもできません。このマニュアルは「倒産を100%予言する」ものではなく、「倒産リスクが極めて高い会社を“見抜く”確率を限りなく100%に近づける」ための、最強の“防衛術”です。
何千万円もの買い物を「運任せ」にするリスクと、数千円で「プロの視点」を手に入れる投資。どちらが賢明か、ご判断いただければ幸いです。
まとめ
建設業界は今、資材高騰や人手不足で、倒産が急増している厳しい時代です。他人事と思わず「自分の身にも起こりうる」という意識を持つことが、大切な資産と家族を守る自己防衛の第一歩になります。
見積もりが異常に安い、打ち合わせの議事録がない、担当者が常に疲弊している…。これらは会社の危険信号です。家づくりの高揚感に流されず、一度立ち止まって冷静に判断する勇気を持ちましょう。
もし倒産した場合、支払った手付金や中間金はほぼ戻りません。手元には「未完成の家」と「巨額のローン返済」だけが残ります。工事再開には更なる追加費用も発生し、自己破産に至るケースもあります。
住宅完成保証制度への加入は大きな安心材料ですが、万能ではありません。保証には上限があり、自己負担が発生する可能性も理解しておきましょう。必ず他のチェック方法と組み合わせて判断することが重要です。
何千万円もの買い物を「運任せ」のギャンブルにしてはいけません。「財務のプロ」が実践する調査術と判断基準を自ら学び、契約前にリスクを把握することが、家族の未来を守る唯一で最強の防衛策となります。