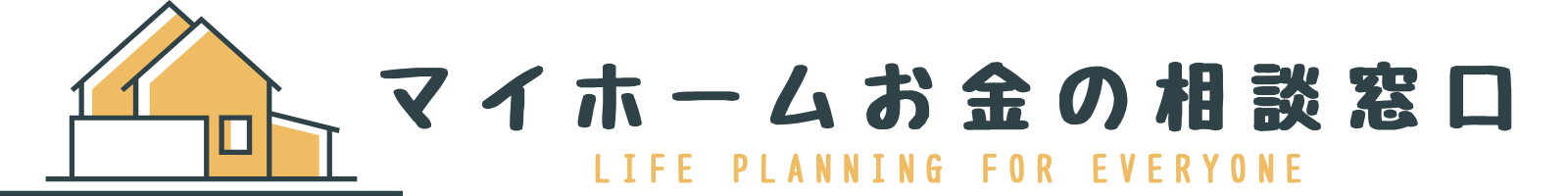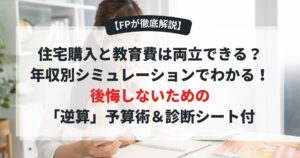【FPが徹底解説】住宅購入と教育費は両立できる?年収別シミュレーションでわかる!後悔しないための「逆算」予算術&診断シート付
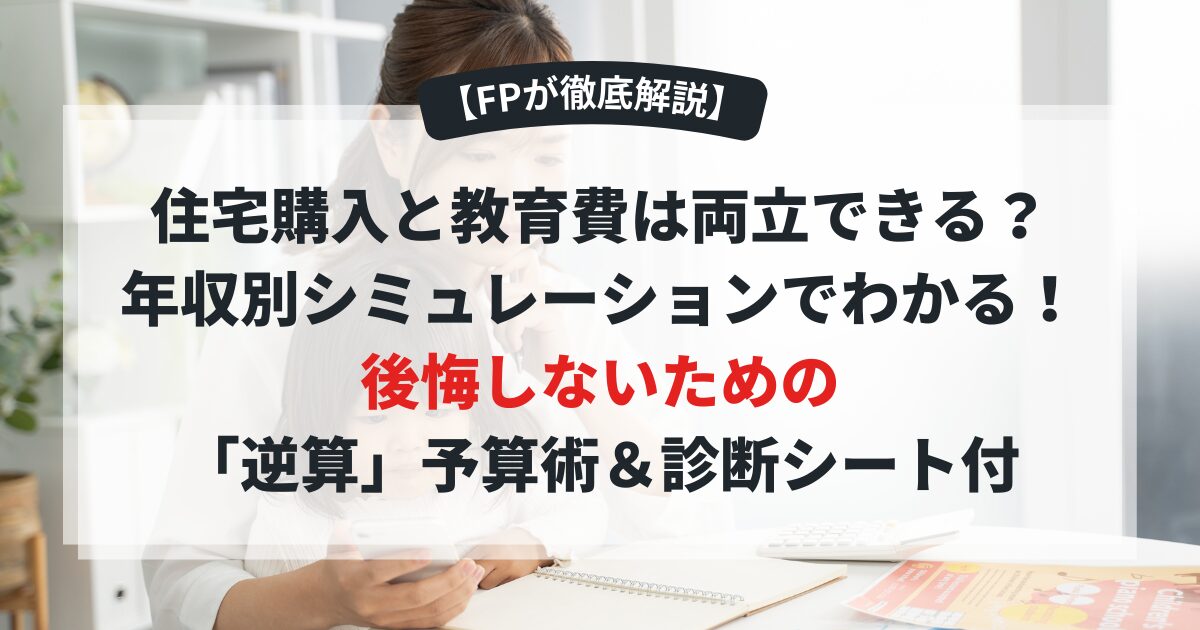

「そろそろマイホームが欲しいな…」
素敵な家の広告が目に入るたび夢が膨らむ一方で、



「うちの収入で、この先ずっと住宅ローンを返せる?」
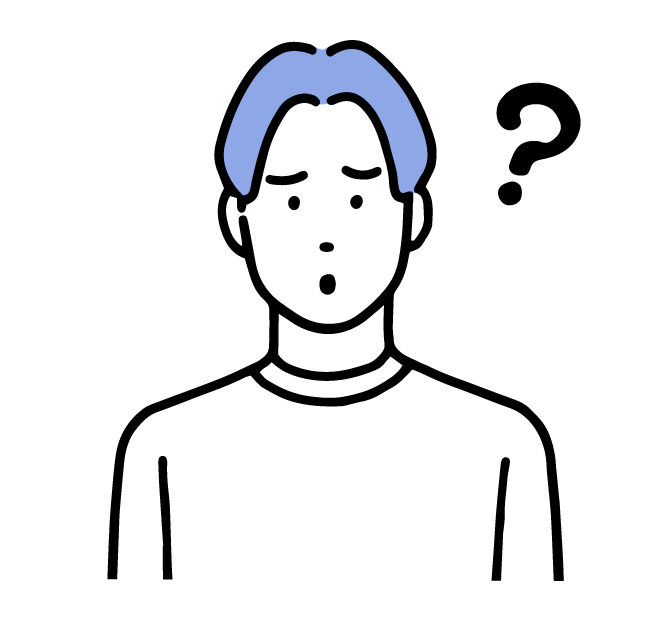
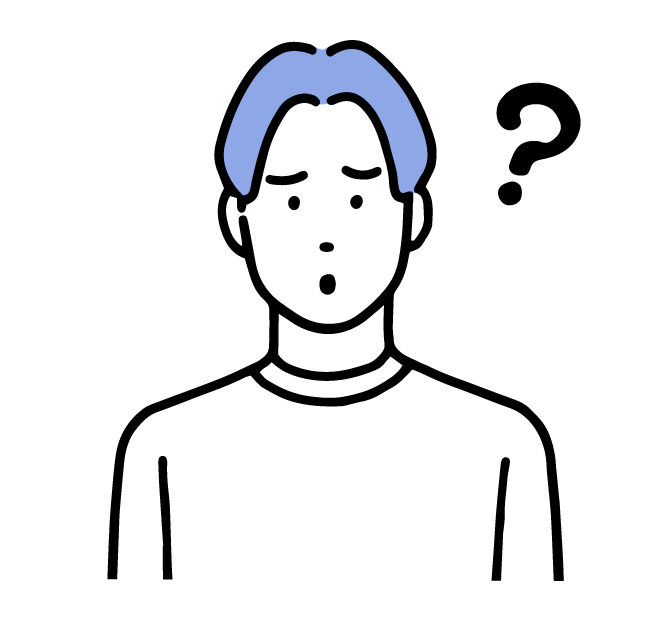
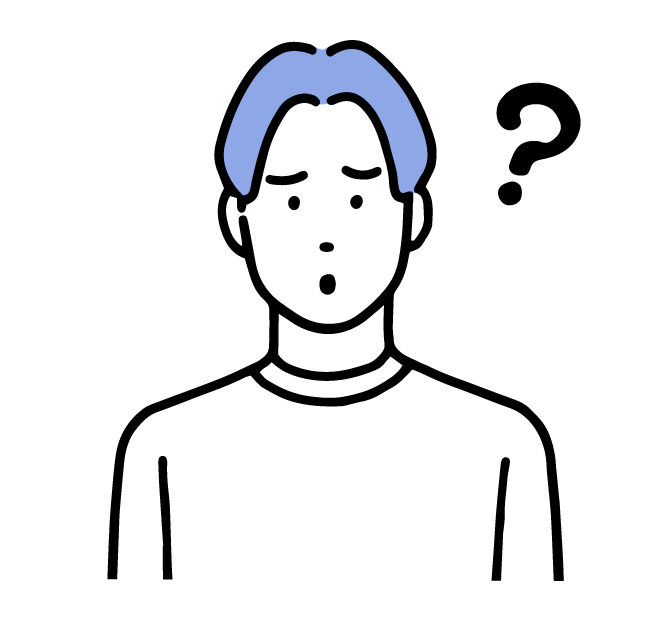
「一番お金がかかる子どもの大学費用と重なったら…?」
と、急に現実的な不安が押し寄せる…。そのお気持ち、痛いほどわかります。
でも、もう大丈夫です。その漠然とした不安は、「正しい計画の立て方」を知らないことが原因なだけ。
これまで多くのご家庭を見てきましたが、実はほとんどの方が「年収から借りられる額」で予算を考え、将来の教育費で苦しんでいます。
この記事では、単なる考え方だけでなく、世帯年収600万円、800万円、1000万円の3つの家庭をモデルにした超リアルな予算シミュレーションを大公開。
さらに、記事の最後には、ご家庭ですぐに使える『おうち作戦会議シート』もご用意しました。
人生という名のRPGで、いきなりラスボス(教育費のピーク)に備えずに、目先の武器(マイホーム)に全財産をつぎ込むようなことはしたくないですものね。
この記事を読み終える頃には、まるで霧が晴れるように「我が家が安心して買える家の値段」がくっきりと見え、自信を持ってパートナーと話し合い、楽しみながらマイホーム計画を進められるようになっているはずです。
住宅購入と教育費の両立は「逆算」でうまくいく!
多くの家庭が抱える「住宅ローンと教育費」の悩み
結論からお伝えします。住宅購入の夢と、子どもの将来のための教育費、この二つを両立させることは十分に可能です。
そして、その成功の鍵を握るのが、これまでの考え方を180度変える「逆算思考」にあります。
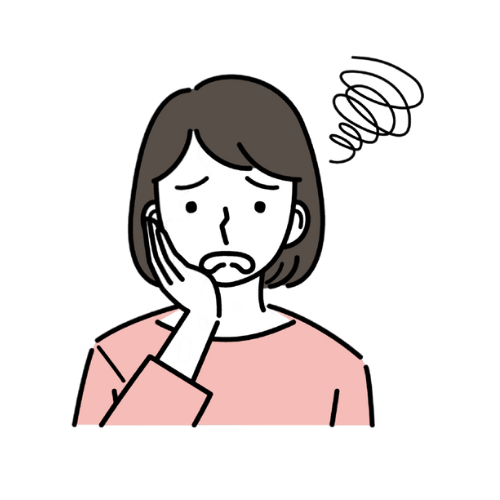
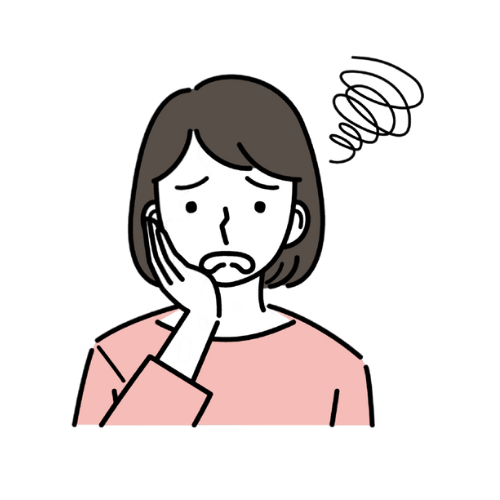
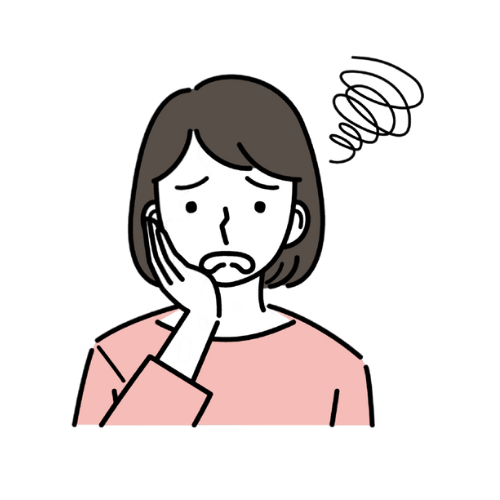
「家を買ったせいで、子どもの塾代を切り詰めなきゃ…」



「本当は留学させてあげたいけど、住宅ローンがあるから無理だね、と諦めさせてしまった…」
このような「たられば」の後悔をしないために、まず知っておいてほしいことがあります。
それは、あなたが抱えている悩みは、決して特別なものではないということです。
30〜40代の子育て世帯にとって、「住宅購入」と「教育費」は、家計における二大巨頭。
どちらも譲れないからこそ、多くの方が「どうすればうまく両立できるんだろう?」と同じ壁にぶつかっているのです。
年収から予算を決める”積み上げ式”の落とし穴
ではなぜ、計画的に進めたはずなのに、後から家計が苦しくなるご家庭が出てきてしまうのでしょうか。
その最大の原因が、「年収から借りられる上限額」を基準に住宅予算を決めてしまう「積み上げ式」の考え方です。
銀行のローンシミュレーションで「お客様の年収ですと、最大5,000万円までお借り入れ可能です」なんて言われると、「お、そんなに借りられるなら、ちょっとグレードの高いあの物件も夢じゃないかも!」と心が躍りますよね。
しかし、これが大きな落とし穴。
言うなれば、体力ゲージ(家計の余力)を考えずに、いきなり最強の必殺技(フルローン)を使おうとしているようなものです。
今はまだ子どもが小さく家計に余裕があっても、10年後、15年後には教育費が今の数倍に膨れ上がります。
その時に、住宅ローンという固定費が重くのしかかり、身動きが取れなくなってしまうのです。
「借りられる額」と「安心して返せる額」は、全くの別物。この違いを理解することが、後悔しない家づくりの第一歩です。
成功の鍵は「未来の教育費」から考える逆算思考
そこで登場するのが「逆算思考」です。
これは、まず「将来、子どものために絶対これだけは確保しておきたい教育費」と「自分たちの老後資金」という、未来の「聖域」を先に決めてしまう考え方です。
- 未来のゴール(教育費・老後資金)を明確にする
- そこから現在地(現在の収入・貯蓄)を振り返る
- ゴール達成のために必要なお金を差し引いて、残った分を「住宅に安心して使える予算」とする
つまり、家計の総量から「聖域」を先に確保し、残った範囲内で家を選んでいくのです。
この方法なら、将来教育費がピークを迎えても、慌てることなく、心から「この家を買ってよかった」と思えるはず。
少し遠回りに感じるかもしれませんが、この「急がば回れ」こそが、住宅購入と教育費の両立を成功させる唯一の道なのです。
まずは敵を知る!子どもの教育費、リアルな総額はいくら?
先ほど「逆算が大事」とお伝えしましたが、では一体「何から」逆算すればいいのでしょうか。その答えが、家計における最大のラスボスとも言える「教育費」です。
まずはこの敵の正体を知ることから始めましょう。この数字を見て「うわっ…」と思ったあなた、正常です。安心してください(笑)。でも、事前に知っておけば、必ず対策は立てられます。
【2025年最新版】幼稚園から大学卒業までにかかる費用一覧
結論として、子ども1人あたりにかかる教育費は、すべて国公立でも約1,000万円、すべて私立の場合は約2,500万円以上が一つの目安となります。
これは文部科学省や日本政策金融公庫などの最新データ(※2025年9月時点)を基にした概算ですが、進路によってこれだけの差が生まれるのです。
具体的に、代表的な進路パターンで見てみましょう。
| 進路パターン | 幼稚園 (3年) | 小学校 (6年) | 中学校 (3年) | 高校 (3年) | 大学 (4年) | 合計 |
| ①すべて国公立 | 約70万円 | 約210万円 | 約160万円 | 約150万円 | 約480万円 | 約1,070万円 |
| ②高校まで公立、大学は私立文系 | 約70万円 | 約210万円 | 約160万円 | 約150万円 | 約690万円 | 約1,280万円 |
| ③高校まで公立、大学は私立理系 | 約70万円 | 約210万円 | 約160万円 | 約150万円 | 約820万円 | 約1,410万円 |
| ④すべて私立(大学は文系) | 約160万円 | 約960万円 | 約430万円 | 約300万円 | 約690万円 | 約2,540万円 |
※上記は学費のほか、給食費、教材費、通学費などを含んだ目安の金額です。
※大学費用は入学金を含みますが、自宅外通学の場合の仕送り費などは含みません。
進路パターン別 教育費総額の比較
いかがでしょうか。お子さまが2人いれば単純にこの2倍、3人いれば3倍です。
どの進路を選ぶかによって、高級車1台分、あるいは都心にマンションがもう一つ買えてしまうほどの金額が動くことがお分かりいただけるかと思います。
このリアルな数字を直視することが、住宅購入の予算を考える上で極めて重要になります。
見落としがち!塾・習い事・留学など「オプション教育費」
さらに注意したいのが、先ほどの表には含まれていない「オプションの教育費」です。
- 塾・予備校代:小学生から通う子も多く、中学・高校受験ともなれば年間50万~100万円かかることも。
- 習い事:ピアノ、スイミング、英会話、プログラミング…一つ月額1万円でも、年間12万円。複数やれば大きな出費に。
- 留学費用:短期留学でも数十万円、長期なら数百万円単位で必要になります。
- その他:教材費、パソコン購入費、受験費用、お小遣いなど。



我が家は息子がずっと野球をやっていたのですが、高校からは道具、ユニフォーム、遠征費用など想定外にお金がかかりました・・・
これらは、いわばRPGで主人公に装備させる「武器」や「防具」のようなもの。どこまでこだわるかはご家庭次第ですが、ゼロというわけにはいきませんよね。「みんなが行っているから」と塾に通わせ始めると、予想外の出費に慌てることになりかねません。
教育費が家計を圧迫する「魔の7年間」とは
そして、これらの教育費が最も牙をむくのが、高校3年間と大学4年間を合わせた「魔の7年間」です。
特に、大学入学時には入学金や前期授業料などで、初年度だけで100万~150万円以上のお金が一気に必要になるケースも珍しくありません。
この時期は、ちょうど住宅ローンの返済期間とガッツリ重なるご家庭がほとんどです。働き盛りとはいえ、収入が右肩上がりに増え続けるとは限りません。
そんな中、「住宅ローンの返済」と「ピーク時の教育費」という二大巨頭が同時に襲いかかってくるのです。
この「魔の7年間」を乗り越えられるかどうか。それが、教育費を考慮した住宅予算を立てる上での最大のポイントと言えるでしょう。
我が家の「安全な住宅予算」を出す逆算3ステップ


教育費という大きな支出の輪郭が見えたところで、いよいよ、あなたの家庭の「本当に安心して買える住宅予算」の土台を固める具体的な計算に入ります。
ここでの目的は、①購入時に出せるお金 と ②購入後の家計の安全性 を明確にすることです。
ステップ1:貯蓄目標のゴールを「大学費用」に設定する
まず、教育費の準備についてです。総額で1,000万円以上というデータを見ると圧倒されてしまいますが、この全額を事前に貯蓄として準備する必要はありません。
多くのご家庭では、幼稚園から高校までの費用は、毎月の給料など日々の家計(キャッシュフロー)の中から支払っていくのが現実的です。
そこで、私たちが貯蓄の目標として明確に設定すべきなのは、教育費の中でも最も短期間で大きな負担となる「大学の入学金と在学費用」です。
これを「子どもが18歳になるまで」に準備することを第一目標としましょう。
このゴール設定なら、グッと現実味が増すのではないでしょうか。これが、まず確保すべき一つ目の「聖域」となります。
ステップ2:【購入時点】で使える「自己資金」を把握する
次に、現時点で、住宅購入にいくら使えるのかを明確にします。住宅は「今」買うものですから、将来の貯蓄をあてにするわけにはいきません。
自己資金の上限 = 現在の貯蓄 – 生活防衛資金
生活防衛資金とは、病気や失業など万が一に備えるお金で、生活費の半年~1年分が目安です。
現在の貯蓄が500万円、生活防衛資金が300万円なら、自己資金の上限は200万円となります。
この金額が、あなたが「頭金」と「諸費用」に使える現実的な上限額です。
ステップ3:【将来】の安全性をチェックする「生涯のゆとり資金」を計算する
自己資金がわかったら、いよいよ住宅ローンの検討に入ります。
しかしその前に、「そのローンを組んだとして、本当に将来、大学費用や老後資金を準備できるのか?」という安全性のチェックを行います。そのための指標が「生涯のゆとり資金」です。
生涯のゆとり資金 = (今後の年間貯蓄額 × 定年までの年数) + (現在の貯蓄 – 購入時に使う自己資金)
この計算で出た金額が、あなたの家庭が守るべき聖域の合計額(大学費用ゴール + 老後資金ゴール)を上回っていれば「合格」です。
もし下回ってしまったとしても、落ち込む必要はありません。
「この予算で家を買うなら、もう少し節約して年間貯蓄額を増やそう」
「妻がパートを始めて収入を増やそう」といった、具体的な対策を考えるための重要な指標になるのです。
年収別に徹底比較!我が家のモデルケースはどれ?
お疲れ様でした!ここからはお待ちかねの実践編です。3つのモデル家族にご登場いただき、実際に住宅予算がいくらになるのかを見ていきましょう。
ご自身の家庭状況に最も近いケースを参考に、「我が家の場合はどうなるかな?」と想像しながら読み進めてみてくださいね。
【シミュレーションの共通ルール】
- 自己資金を計算:「現在の貯蓄」から生活防衛資金(ここでは貯蓄額の半分と仮定)を引いて、頭金+諸費用に使える上限を決めます。
- ローン借入額を計算:手取り月収の20%を上限とします(金利0.8%, 35年)。
- 住宅購入総予算を決定:上記①と②を合計します。
- 将来の安全性をチェック:そのローンを返済しながら、定年までに「大学費用」と「老後資金」を準備できるか検証します。
Case1:世帯年収600万円(夫:正社員、妻:専業主婦、子1人)
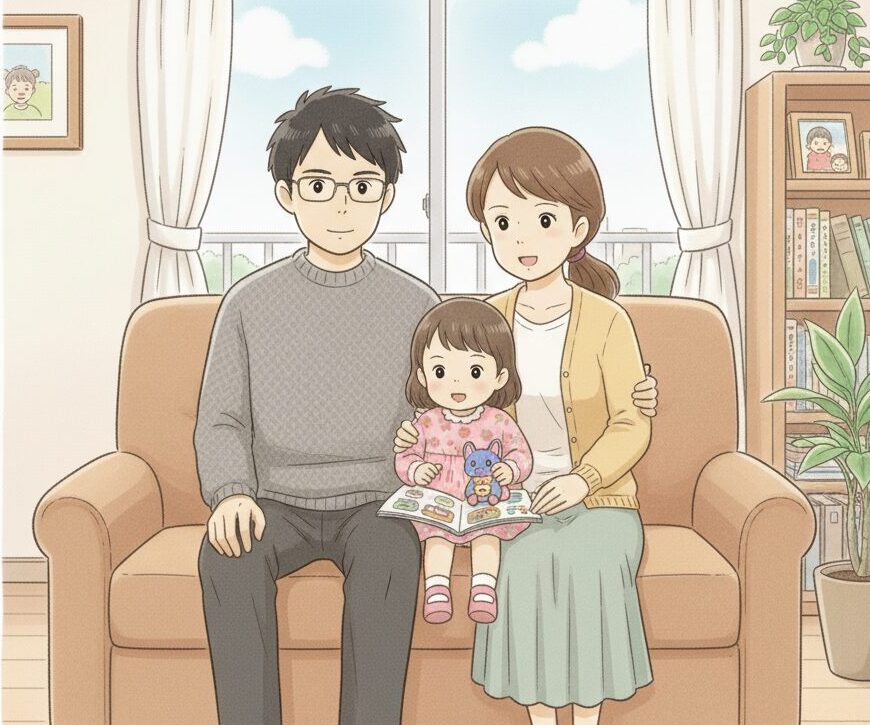
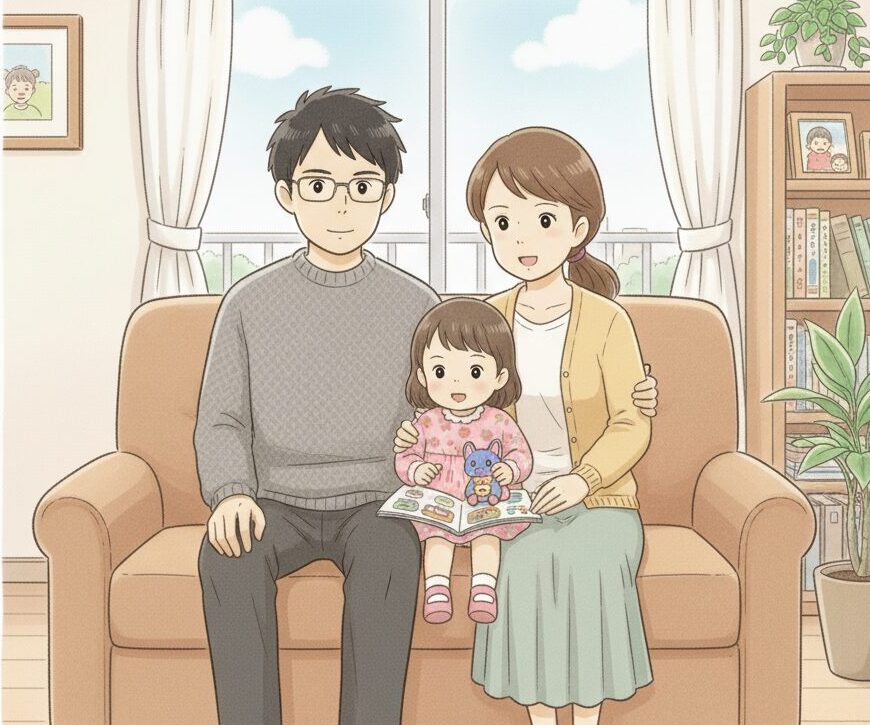
| 項目 | 詳細 |
| 現在の貯蓄 | 400万円 |
| 自己資金の上限 | 400万円 – 生活防衛資金200万円 = 200万円 |
| ローン借入額 | 月々8万円の返済で約2,880万円 |
| 住宅購入総予算 | 約2,800万円(諸費用約196万円を自己資金で賄う) |
- 目標額:大学費用500万+老後資金2000万=2,500万円
- 将来の貯蓄予測:今後の年間貯蓄を50万円と仮定。定年(65歳)までの33年間で計算。(年間貯蓄50万 × 33年)+手元に残る貯蓄200万=1,850万円
- 結論:目標に対し約650万円不足します。「妻が働き始める」など家計改善策とセットで考える必要があります。
Case2:世帯年収800万円(夫:正社員、妻:パート、子2人)


| 項目 | 詳細 |
| 現在の貯蓄額 | 800万円 |
| 自己資金の上限 | 800万円 – 生活防衛資金400万円 = 400万円 |
| ローン借入額 | 月々約10.4万円の返済で約3,750万円 |
| 住宅購入総予算 | 約4,000万円(諸費用280万円+頭金120万円を自己資金で賄う) |
- 目標額:大学費用1000万+老後資金2000万=3,000万円
- 将来の貯蓄予測:今後の年間貯蓄を125万円と仮定。定年(65歳)までの30年間で計算。(年間貯蓄125万 × 30年)+手元に残る貯蓄400万=4,150万円
- 結論:試算上は約1,150万円の余裕が生まれます。安心して進められる計画と判断できます。
Case3:世帯年収1000万円(共働き、子2人)


| 項目 | 詳細 |
| 現在の貯蓄 | 1,500万円 |
| 自己資金の上限 | 1,500万円 – 生活防衛資金750万円 = 750万円 |
| ローン借入額 | 月々約12.4万円の返済で約4,480万円 |
| 住宅購入総予算 | 約5,000万円(諸費用350万円+頭金530万円を自己資金で賄う) |
- 目標額:大学費用1000万+老後資金2000万=3,000万円
- 将来の貯蓄予測:今後の年間貯蓄を180万円と仮定。定年(65歳)までの27年間で計算。(年間貯蓄180万 × 27年)+手元に残る貯蓄750万=5,610万円
- 結論:2,600万円以上の大幅な余裕があり、教育費の選択肢を広げる、早めの繰り上げ返済を目指すなど、多様な選択肢を検討できる盤石な計画です。
予算が決まれば怖くない!住宅購入で後悔しない3つの最終チェック


さて、ご自身の家庭の予算が見えてきましたね!ゴールが見えれば、もう何も怖くありません。
最後に、その大切な予算を最大限に活かし、後悔しないための3つの最終チェックポイントを確認しましょう。ここをしっかり押さえることで、計画の精度がぐっと上がります。
ポイント1:頭金は「貯蓄の25%」が目安?入れすぎのリスクも解説
「頭金をたくさん入れると、その分ローンが減って利息も少なくなってお得!」
これは真実ですが、頭金の入れすぎは禁物です。特に、教育費の準備がこれから本格化する子育て世帯は注意が必要です。
なぜなら、住宅購入後も人生にはまとまったお金が必要になる場面が次々と訪れるからです。
- 子どもの進学費用、塾の夏期講習
- 急な病気やケガによる医療費
- 車の買い替え、家電の故障
- 予測不能な失業や収入減
せっかく頭金を300万円多く入れたのに、翌年、子どもの歯の矯正で100万円が必要になり、結局金利の高い教育ローンを組むことになった…これでは本末転倒ですよね。
住宅ローンは、歴史的に見ても非常に低い金利で借りられる特殊なローンです。
手元の現金をすべて頭金につぎ込むのではなく、いざという時のための「生活防衛資金」とは別に、ある程度の「待機資金」を残しておくことが、精神的な安定にも繋がります。
目安としては、貯蓄総額の25%~30%程度を頭金の上限と考えるのが一つの手です。
ポイント2:物件価格の5〜8%!「諸費用」と「維持費」も予算内か?
住宅購入にかかるお金は、物件の価格だけではありません。見落とされがちですが、非常に重要なのが「諸費用」と「維持費」です。
■購入時にかかる「諸費用」
これは、物件の売買契約から引き渡しまでにかかる手数料や税金のことです。具体的には、以下のようなものがあります。
- 仲介手数料
- 印紙税(売買契約書に貼る印紙代)
- 登録免許税(土地や建物の所有権を登記する税金)
- 不動産取得税
- ローン保証料、事務手数料
- 火災保険料、地震保険料
これらの合計は、物件種別にもよりますが新築で物件価格の3~5%、中古で6~8%程度が目安。
例えば3,000万円の中古物件なら、180万~240万円が別途必要になる計算です。この諸費用を自己資金から出すのか、ローンに組み込むのかを事前に計画しておく必要があります。
■入居後にかかる「維持費」
マイホームは、賃貸と違って住み始めてからも自分でお金をかけてメンテナンスしていく必要があります。
- 固定資産税、都市計画税(毎年)
- 火災保険、地震保険の更新料
- マンションの場合:管理費、修繕積立金(毎月)
- 戸建ての場合:数年ごとの外壁塗装や屋根の修繕費用
これらの維持費も、シミュレーションの段階で月々の支出としてあらかじめ組み込んでおくことが、入居後の「こんなはずじゃなかった…」を防ぐ秘訣です。
ポイント3:変動金利 vs 固定金利、あなたに合うのはどっち?
住宅ローンを選ぶ際、誰もが悩むのが「変動金利」と「固定金利」のどちらを選ぶか。これは、あなたの性格や家計の状況によって最適解が変わります。
■変動金利
- メリット:固定金利より金利が低い。当初の返済額を抑えられる。
- デメリット:将来、金利が上昇して返済額が増えるリスクがある。
- 向いている人:
- 金利上昇にも対応できる共働き世帯など、家計に余力がある人
- 将来、繰り上げ返済を積極的に考えている人
- 「リスクを取ってでも、総返済額を抑えたい」と考える合理的なタイプ
■固定金利(全期間固定)
- メリット:返済額が最後まで変わらない絶対的な安心感。将来の計画が立てやすい。
- デメリット:変動金利より金利が高い。
- 向いている人:
- 金利のニュースを見てハラハラしたくない、心配性なタイプ
- 子どもの教育費がかかる時期に、返済額を絶対に増やしたくない人
- 家計管理をシンプルにしたい人
究極的には「安さの変動か、安心の固定か」という選択です。これはもう性格の問題に近いかもしれません。
まるで、遊園地で「スリルを求めて絶叫マシン」に乗るか、「平和が一番、メリーゴーランド」を選ぶか、みたいな(笑)。ご夫婦で価値観をしっかり話し合って、納得のいく選択をしてください。
まずは夫婦でやってみよう!未来が見える「おうち作戦会議」シート


さて、ここまで読み進めてくださったあなたなら、もう大丈夫。住宅購入と教育費の両立に向けた知識は、ばっちり身につきました。
しかし、一番大切なのは、この知識を「我が家の計画」に落とし込むことです。
どんなに優れた地図も、眺めているだけでは目的地にはたどり着けませんよね。
さあ、今週末にでも、ご夫婦で「おうち作戦会議」を開いてみませんか? FPへの相談は、それからでも決して遅くありません。
FP相談の前に!家庭でやるべき3つのこと
専門家に相談すれば安心、と思いがちですが、その前に夫婦で価値観をすり合わせておくことが、満足度の高い家づくりへの一番の近道です。
なぜなら、FPは客観的な数字を整理するプロですが、あなたの家族の「どんな暮らしがしたいか」という想いまでは決められないからです。
夫婦の意見がバラバラのまま相談に行くと、「夫は駅近のタワマンがいいと言い、妻は郊外の庭付き戸建てがいいと言います。予算はどうすれば?」とFPを困らせてしまうことに…。
そうならないために、事前に以下の3つを話し合っておきましょう。
- お互いの価値観を知る
「どんな暮らしが理想?」「子どもの教育で何を大切にしたい?」といった、お金の前提となる根本的な価値観を共有します。 - 数字の共通認識を持つ
この記事で解説した「教育費のゴール」や「住宅に使える貯蓄の上限額」を、ぜひ夫婦で一緒に計算してみてください。同じ数字を見ることで、会話がスムーズになります。 - 家の条件に優先順位をつける
「駅からの距離は譲れないけど、築年数は少し古くてもOK」など、お互いの希望の優先順位を明確にしておきましょう。
ダウンロード不要!書き出すだけの簡単ライフプランシート項目
「何から話せばいいかわからない…」という方のために、作戦会議で役立つシートの項目をご用意しました。紙とペンさえあれば、今すぐ始められます。ぜひ、お二人でこの質問に答えてみてください。
【未来が見える!おうち作戦会議シート】
《ステップ1:未来の”夢”を描こう》
Q1. 10年後、どんな家族になっていたい? 理想の暮らしを自由に書いてみよう!
Q2. 子どもには、どんな経験をさせてあげたい?(進路、習い事、留学、旅行など)
Q3. パパ・ママ自身の夢や、これからやりたいことは?(趣味、キャリア、夫婦での旅行など)
《ステップ2:”お金”の計画を立てよう》
Q4. 子どもの大学費用、18歳までにいくら貯める?(目標:____万円)
Q5. 私たちの老後資金、最終的にいくらを目指す?(目標:____万円)
Q6. 我が家の「住宅に使える自己資金(頭金+諸費用)」の上限はいくら?(上限額:____万円)
Q7. 無理なく返せる毎月のローン額はいくら?(毎月____万円まで)
Q8. 将来の安全性チェックの結果はどうだった?(安全? or 対策が必要?)
《ステップ3:「マイホーム」の希望を整理しよう》
Q9. 住宅購入の総予算の上限はいくらにする?(総予算:____万円)
Q10. 【絶対に譲れない条件】:
Q11. 【できれば叶えたい条件】:
Q12. 【妥協できる条件】:
※A4用紙で印刷してお使いになりたい方はこちらからダウンロード可能です!
夫婦で価値観を共有し、同じ未来を描くコツ
お金の話は、ともすると口論の種になりがちです。そうならないために、作戦会議を成功させるちょっとしたコツをお伝えします。
- 相手を否定しない
「でも」「だって」は禁句です。「なるほど、あなたはそう考えているんだね」と、まずは一度、相手の意見をまるごと受け止めてみましょう。 - 楽しい雰囲気で
平日の夜、疲れている時ではなく、休日のカフェや、少し美味しいものを食べながらなど、リラックスできる環境で行うのがおすすめです。「作戦会議」という名前も、ゲーム感覚で楽しむための工夫です。 - 一度で決めようとしない
意見が合わなくても焦る必要はありません。「今日はここまでにして、また来週話そうか」と、時間をかけることを前提にしましょう。
夫婦は、家族という名の会社の共同経営者。会社のビジョン(夢)を共有し、財務(お金)を確認し、具体的な事業計画(家の希望)を立てる。そう考えれば、この作戦会議、ちょっとワクワクしてきませんか?
よくある質問(FAQ)
- Q1. 住宅ローンと教育ローン、もし重なってしまったらどうすればいい?
-
住宅ローン返済中に教育ローンを組む必要が出た場合、まずは慌てずに家計全体を見直しましょう。国の教育ローンは金利が比較的低いですが、それでも返済額が増えるのは事実です。
一時的に家計が厳しい場合は、金融機関に住宅ローンの返済期間延長(リスケジュール)を相談するのも一つの手です。ただし、返済総額は増えるため、あくまで最終手段と考え、まずは固定費の見直しや収入を増やす方法を検討することが大切です。 - Q2. 子どもがまだ小さいのですが、いつから計画を始めるべき?
-
この記事を読んでくださっている「今」が最高のタイミングです。子どもの年齢が低ければ低いほど、大学進学までの準備期間を長く確保できます。
例えば、月々2万円を貯蓄する場合、18年あれば約432万円になりますが、10年では240万円です。早く始めるほど、月々の負担を軽く、そして着実に目標額を達成できます。まずはご夫婦で話し合うことから始めてみてください。 - Q3. 夫婦で年収が違う場合、どうやって予算を考えればいいですか?
-
基本の考え方は同じですが、世帯年収を合算してシミュレーションしましょう。住宅ローンを組む際は、収入合算やペアローンという選択肢もあります。
ペアローンは二人でそれぞれローンを組むため借入額を増やせますが、お互いに団信(団体信用生命保険)に加入できるメリットも。ただし、将来の働き方が変わる可能性も考慮し、どちらか一人の収入が減っても返済を続けられるか、という視点を持つことが重要です。 - Q4. 逆算したら予算がかなり低く…希望の家は諦めるしかない?
-
希望の予算に届かなかったとしても、夢を諦める必要は全くありません。まずは、物件を探すエリアを少し広げてみたり、新築だけでなく中古物件をリノベーションする、という選択肢を検討してみましょう。
また、今は希望額に届かなくても、5年後に再度計画を見直せば、貯蓄が増えてより高い予算の家が購入可能になっているかもしれません。焦らず、長い目で見て最適なタイミングを探ることが大切です。 - Q5. 奨学金やiDeCo、新NISAなど、活用できる制度はありますか?
-
はい、積極的に活用すべきです。奨学金はあくまで借金ですが、本当に必要な時には心強い制度です。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISA(少額投資非課税制度)は、税金の優遇を受けながら効率的に資産形成ができるため、老後資金や教育費の準備に非常に有効です。
特に新NISAは、いつでも引き出せるため大学費用の準備にも向いています。住宅購入の計画と並行して、これらの制度の活用もぜひ検討してください。
まとめ
最後に、この記事でお伝えした最も重要なポイントを5つにまとめました。この5つさえ覚えておけば、将来にわたって安心な家計を築けるはずです。
住宅予算は「年収から借りられる額」で考えてはいけません。将来必ず必要になる「教育費」と「老後資金」というゴールから逆算し、残った範囲で安全に買える家の値段を決めること。
この考え方が、後悔しないための絶対的なルールです。
子どもの教育費は、総額で1,000万円以上かかる可能性があります。特に負担が集中するのが、住宅ローンの返済と重なる「魔の7年間」です。この時期を乗り切れるかどうかを基準に予算を考えることで、将来の家計破綻リスクを回避できます。
まずは現時点で住宅に使える自己資金の上限を現実的に把握すること。その上で、将来の収支を予測し、ローン返済と聖域(教育費・老後資金)の確保が両立できるか安全性をチェックするのが重要です。将来の貯蓄をあてにした計画は立ててはいけません。
銀行が提示する「融資可能額」は、あなたの将来の教育費まで考慮してくれません。大切なのは、自分たちの家計にとって「毎月、そして何十年も、無理なく安心して返せる額」はいくらなのか、という基準を自分たちで持つことです。
どんなに優れた知識や計算式も、夫婦の価値観の共有がなければ絵に描いた餅です。どんな暮らしがしたいか、何を大切にしたいか。この記事をきっかけに、ぜひ「おうち作戦会議」を開いてみてください。それが、家族の幸せな未来を作る第一歩です。