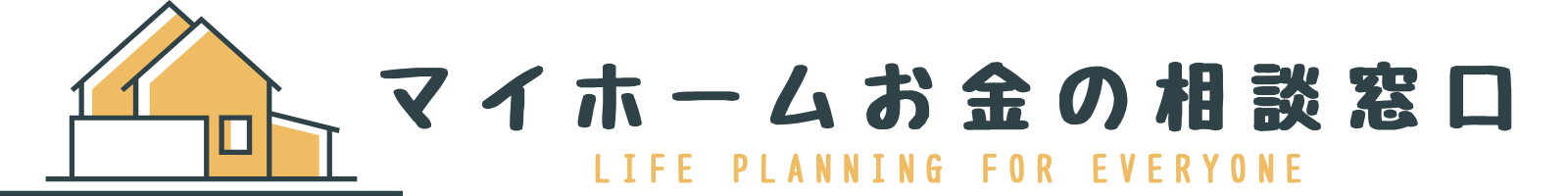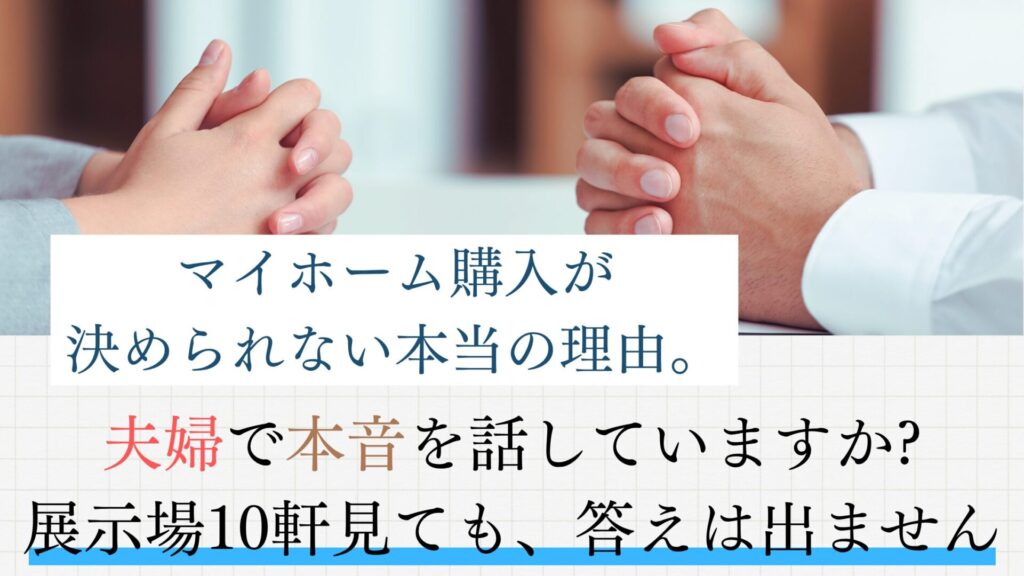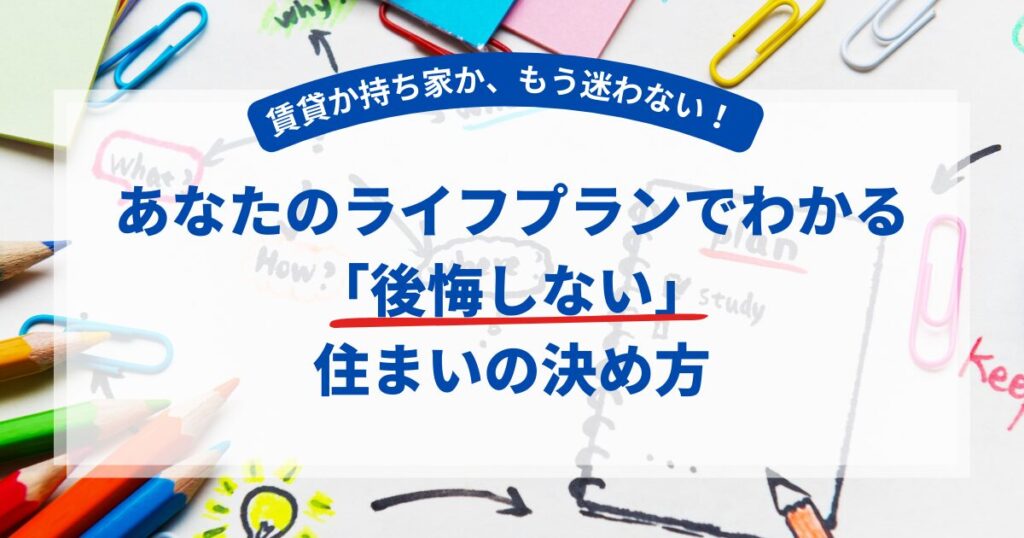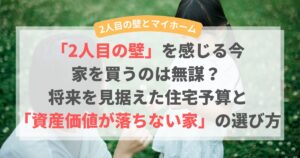「2人目の壁」を感じる今、家を買うのは無謀? 将来を見据えた住宅予算と「資産価値が落ちない家」の選び方
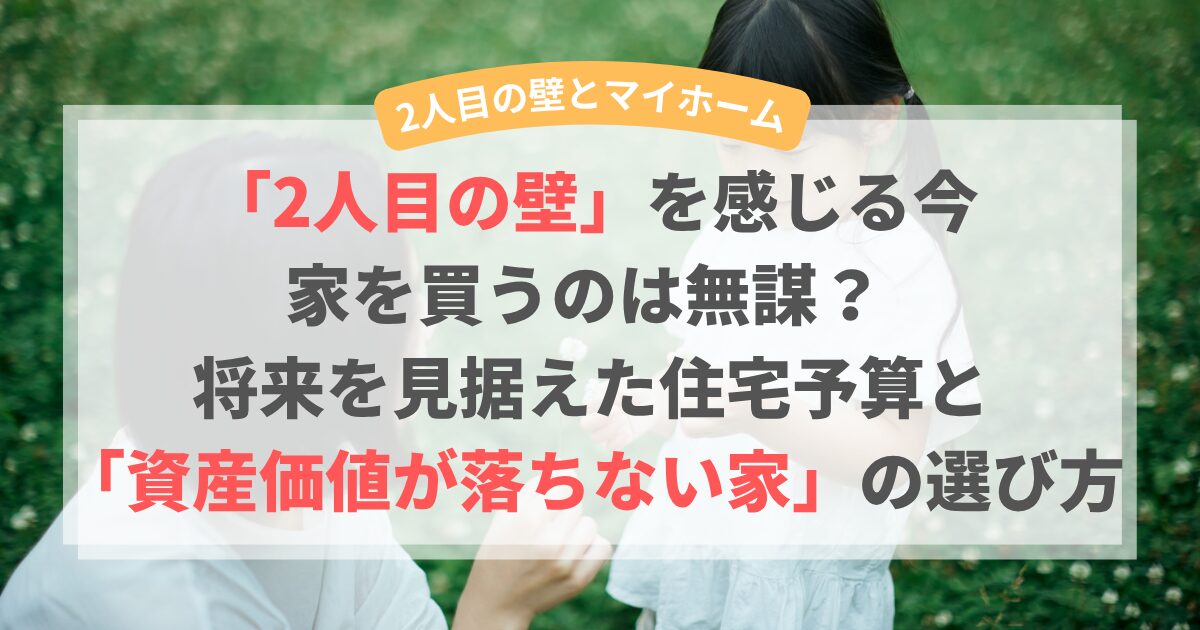
「子どもの『やりたい!』は、できる限り叶えてあげたい。将来のために、教育費だけは絶対に妥協したくないな…」
その一方で、
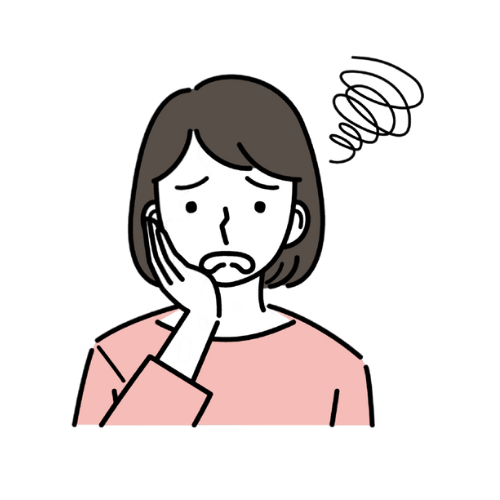
「このまま家賃を払い続けるのも、何だかもったいない気がする…」



「周りもマイホームを持ち始めたし、うちもそろそろ考え時かな?」
子育て世代のあなたなら、この二つの気持ちの間で、心が揺れ動いているのではないでしょうか。
そのお気持ち、痛いほどわかります。
特に、もし今マイホームという大きな決断をしてしまったら、「将来、2人目は経済的に難しいかも…」なんて、子どもの未来の可能性にまで影響してしまうのでは?と考えると、なかなか一歩が踏み出せなくなりますよね。
ご安心ください。その悩みは、あなただけが抱える特別なものではありません。
先日、明治安田生命が発表した最新の調査で、0歳〜6歳の子どもを持つ親の実に83.3%が「子育て費用に負担を感じている」と回答しました。
子育て費用、8割以上が「負担」を実感
さらに、「2人目を望む」と答えた人の割合は、調査開始以来、過去最低を記録したのです。
この記事では、こうした子育て世帯のリアルな声を紐解きながら、あなたの漠然とした不安の正体を明らかにします。
そして、



「教育費」という聖域を絶対に守りながら、後悔しないマイホーム購入のタイミングと予算を導き出すための、具体的な方法を徹底解説します!
読み終える頃には、不安が「これなら我が家も計画できる!」という確かな希望に変わっているはずです。
子育てもマイホーム購入も夫婦で向き合い、まずは本音で話すことから。「会話」ではなくただの「確認」になっていませんか?
はじめに:あなたの悩みは「みんなの悩み」最新データが示す子育て世帯のリアル
まず、心の片隅に置いていただきたい大切なことがあります。
それは、「2人目のことを考えると、家の買い時が分からなくなる…」というその悩みは、決してあなた一人だけのものではないということです。
なぜなら、それは現代の日本で子育てをする多くの家庭が直面している、極めてリアルで共通の課題だからです。
かつてのように「子どもは2人以上いて当たり前」「35年ローンで家を買うのが夢」という「昭和の常識」は、もはや通用しなくなりました。
物価は上がるのに給料は上がりにくい、共働きが必須なのに子育てのサポートは十分とは言えない…。
そんな厳しい現実の中で、私たちは「子どもの未来」と「自分たちの暮らし」という両天秤の間で、必死にベストな選択を探しているのです。
その証拠に、先ほど触れた明治安田生命の調査は、まさに私たちの心の声を映し出す鏡のような結果でした。
多くの家庭が子育て費用に頭を悩ませ、「2人目の壁」を実感しているという事実は、「うちだけが特別うまくいっていないんじゃないか…」という孤独な不安を和らげてくれるのではないでしょうか。
そう、あなたのその悩みは、時代の変化の中で真剣に家族の未来を考えている証拠なのです。
だからこそ、この記事では「こうすべきだ」という一方的な答えを提示するつもりはありません。
客観的なデータとFPとしての知識を羅針盤として、あなたとご家族が心から納得できる「我が家だけの正解」を見つける旅に、最後まで寄り添わせてください。
【2025年最新調査】子育て世帯のお金と本音、衝撃のデータとは?


先ほど少し触れた明治安田生命のアンケート調査。この結果を深掘りすると、現代の子育て世帯が抱える「お金」と「本音」が、驚くほどリアルに浮かび上がってきます。
特に注目すべきは、「2人目の壁」「教育費への聖域」「共働き妻のジレンマ」という3つのキーワードです。
これらのデータは、単なる数字の羅列ではありません。マイホームを考える上で無視できない、家族の未来設計に直結する重要なシグナルだからです。
自分たちの感覚が世の中とズレていないか、確認する意味でも一緒に見ていきましょう。
データ①:「2人目を望む人」は過去最少に。背景にある深刻な経済不安
まず衝撃的なのが、「2人目を望む」と答えた人の割合が33.3%と、2018年の調査開始以来、過去最低を記録したという事実です。
「2人目は欲しいけれど、経済的に難しい…」と感じる人の理由を見てみると、「将来の収入面への不安」(45.5%)、「生活費がかかる」(34.6%)といった金銭的な要因が上位を占めています。
「2人目の壁」経済的な理由トップ2
これは、「愛情や希望だけでは、子どもの未来を描ききれない」という、現代社会の切実な現実を物語っています。
マイホーム計画においても、「子どもが1人か2人か」で必要な広さも予算も大きく変わるため、この経済的な不安がいかに大きな影響を与えているかが分かります。
データ②:8割以上が「費用に負担感」。でも「教育費」だけは削れない親心
次に、0歳〜6歳の子どもを持つ親の83.3%が「子育て費用に負担を感じている」と回答しています。
家計が厳しい中でも、親が「聖域」として守りたいと考えているのが「教育」です。
アンケートでは、「子どもの将来のために習い事をさせたい」と考える親が大多数を占め、実際に月平均で4.1万円もの費用をかけている実態が明らかになりました。
まるで、飲み会は我慢できても、推しのライブの遠征費は削れないファンの心理のようですが、これは親心そのもの。
住宅ローンを考える上でも、この「教育費という聖域」をいかに守り抜くかが、後悔しないための最重要課題となります。
データ③:「もっと働きたいのに…」共働き妻の7割が抱えるジレンマ
最後に、共働き世帯の妻が抱えるジレンマです。調査では、仕事量をセーブしている妻の実に7割以上が「本当はもっと働きたい」と考えていることが分かりました。
その理由としては、「子育ての時間確保」や「育児との両立」が上位に挙がっており、キャリアと育児の両立の難しさが浮き彫りになっています。
仕事をセーブする妻の7割以上が「もっと働きたい」
これは、住宅ローンの資金計画において、妻の収入をどう見込むかという非常にデリケートな問題に直結します。
「本当はもっと家計に貢献できるポテンシャルがあるのに、それが叶わない」という葛藤。
このモヤモヤを解消するような住まい選びや資金計画が、家族全体の幸福度を上げる鍵になると言えるでしょう。
【本題】家族計画に悩む今、家を買うのは正解?FPの答えは「条件付きYES」
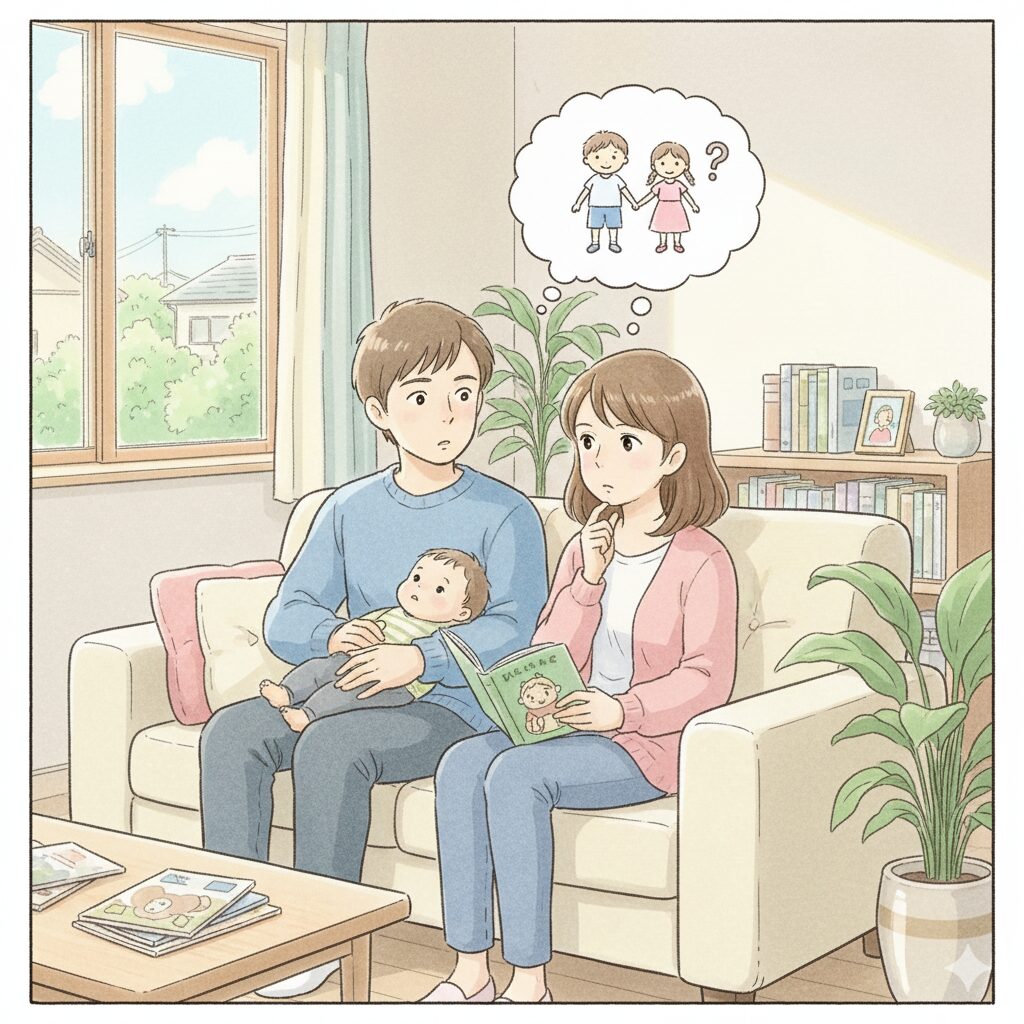
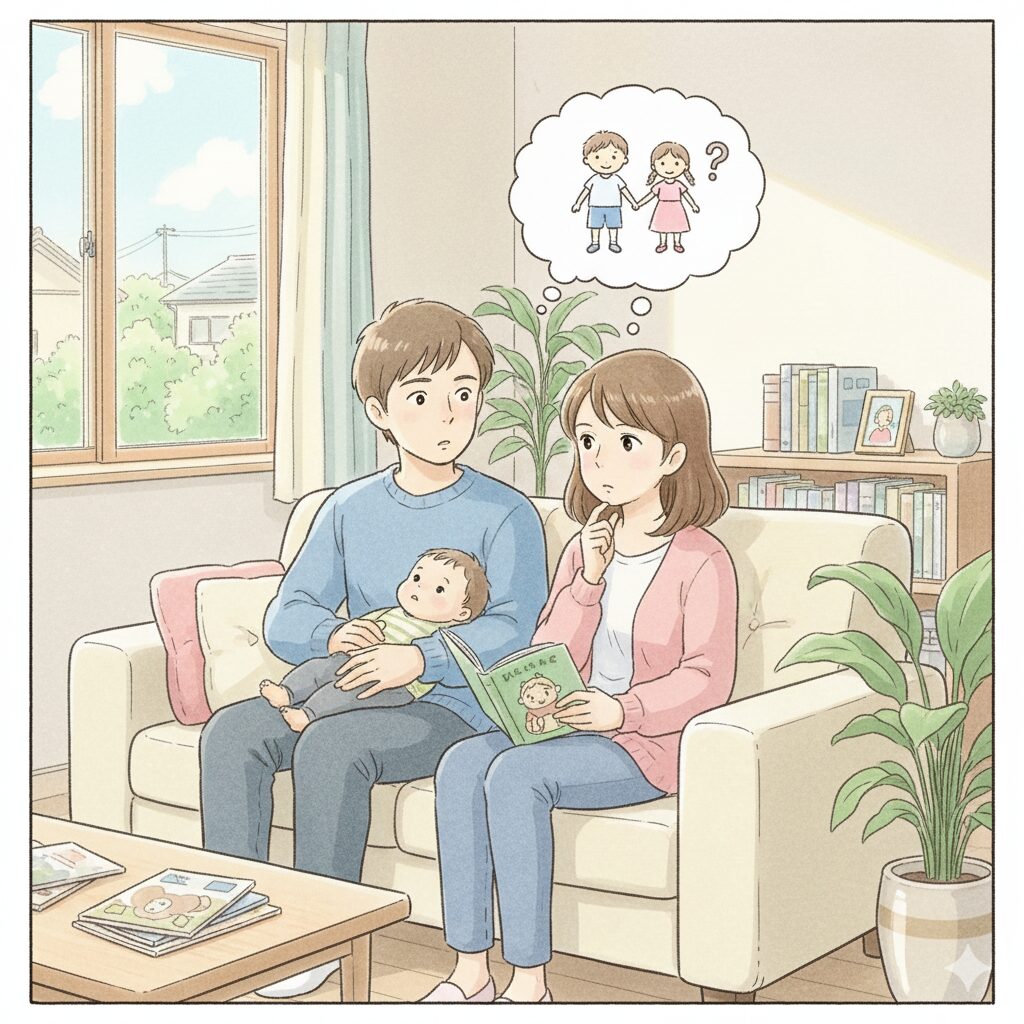
さて、ここからが本題です。様々なデータを見てきましたが、結局のところ、家族計画が不確定な今、家を買うのは正解なのでしょうか?
15年で1,200組以上のマイホーム購入相談を受けてきた私の答えは、
「将来のリスクを理解した上で、『変化に対応できる家』を『長期的な資産価値』という視点で選ぶなら、YES」です。
なぜなら、「待つ」ことにも「今すぐ買う」ことにも、それぞれ無視できないリスクとメリットが存在するからです。
どちらか一方が絶対的に正しいということはなく、両者のリスクを天秤にかけ、その両方をヘッジできるような「第3の選択肢」を取ることが、最も賢明な判断だと考えるからです。
【ケース1】家族計画が固まるまで「待つ」という選択肢の光と影
まず、「2人目が生まれるかどうかわかるまで、とりあえず賃貸で様子を見る」という選択。これは一見、非常に合理的で安全な策に思えます。
光(メリット):最大のメリットは、家族構成に合わせた最適な間取りと予算を、後から確定できる安心感です。子どもが2人になれば3LDK、1人なら2LDK…といったように、未来の結果を見てから動けるので、家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに家を合わせることができます。
影(デメリット):しかし、その「待ち時間」にもコストがかかります。具体的には
①家賃という「消えるお金」を払い続けること
②住宅ローン金利が今より上昇している可能性がある
③年齢が上がることでローン返済期間が短くなり、月々の返済額が重くなる
という3つのデメリットです。
特に金利は、わずか1%違うだけで総返済額が数百万円変わることもあり、決して無視できないリスクです。
【ケース2】子どもが1人の今「買う」という選択肢の賢さとリスク
では、逆に「えいやっ!」と今すぐ買ってしまうのはどうでしょうか。
賢さ(メリット):最大のメリットは、若いうちから資産形成をスタートできる点です。払い続ける家賃が、自分の資産(家)に変わっていく感覚は大きな魅力でしょう。また、現在の比較的良好な金利条件でローンを組める可能性や、広い家でのびのびと子育てができるという精神的な満足感も得られます。
リスク(デメリット):言わずもがな、最大のリスクは「2人目が生まれたら、部屋数が足りず手狭になってしまった…」という後悔の可能性です。せっかく買ったマイホームが、数年でストレスの原因になってしまうのは、何としても避けたい事態です。
FPの結論:2つのリスクを回避する「ハイブリッド戦略」
お分かりでしょうか?「待つ」のは機会損失のリスク、「買う」のはミスマッチのリスク。どちらも一長一短なのです。
だからこそ、私が推奨するのは、この2つのリスクを同時に回避するハイブリッドな戦略。
それが、冒頭で述べた「『変化に対応できる家』を『長期的な資産価値』という視点で、今、計画的に選ぶ」という考え方なのです。
次の章では、この戦略を具体的にどう実行していくのか、その方法を詳しく解説していきます。
賃貸か持ち家か?ライフプランで考える後悔しない住まいの決め方はこちら
教育費は聖域!家族の未来を守る「ライフプラン逆算」住宅予算術


「教育費の聖域」を確保するための具体的な逆算予算術はこちら
将来の家族構成が不確定な中で後悔しないための予算術。
それは、多くの人がやりがちな「年収から借りられる額」で考えるのではなく、「守りたい未来(教育費)から逆算して、家に使えるお金を決める」という全く逆のアプローチです。
なぜなら、先に「教育費」という聖域を絶対不可侵の予算として確保してしまえば、たとえ将来子どもが2人になっても、焦ったり教育レベルを妥協したりする必要がなくなるからです。
もちろん、これから提示する教育費の目安は非常に大きな金額に感じられるかもしれません。
しかし、これは将来の家族構成を想定したライフプランニングを行うことで、具体的な達成目標に変わります。
家計の最優先事項を最初に守ることで、精神的な安心感と、計画の柔軟性が生まれるのです。
では、具体的にどうやって予算を立てるのか。ここでは、あなたの価値観に合わせて選べる2つのプランをご提案します。
プランA【堅実派】:予算はMAXで!「子ども2人分の教育費」を先に確保する
これは、「何があっても子どもの教育費で悩みたくない」という方向けの、最も安全で堅実なプランです。
- 考え方:まず、子ども1人あたりにかかる大学までの教育費(一般的に1,000万円〜1,500万円が目安)を2人分、つまり2,000万円〜3,000万円を「聖域」として確保する目標を立てます。
- ポイント:もちろん、これは今すぐ用意する現金ではありません。この壮大な目標も、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と一緒にライフプランニングを行うことで、「子どもが大学に入るまでの約18年間で、月々いくら積み立てれば達成できるか」という具体的なアクションプランに分解することができます。
- 住宅予算の決め方:その積立計画を立てた上で、残りの家計の余力から「無理なく返済できる住宅ローンの上限額」を算出します。これが「子どもが2人になっても絶対に家計が破綻しない盤石な予算」となります。
プランB【バランス派】:「子ども1.5人分の教育費」を確保し、少し家に予算を回す考え方
こちらは、「教育費の安心感も欲しいけど、家の快適さや立地も少し優先したい」という方向けの、柔軟なプランです。
- 考え方:確保する教育費の目標を「1.5人分」、つまり1,500万円〜2,250万円に設定します。これは、「1人分は満額確保し、2人目が生まれた場合は、一部を奨学金で補ったり、その時の家計の見直しで対応する」という少しリスクを取る考え方です。
- 住宅予算の決め方:プランAよりも目標額が少ないため、月々の積立額も抑えられ、その分、住宅に回せる予算は少し上がります。
これにより、希望のエリアにもう少し近づけたり、設備のグレードを上げたり、といった選択肢が生まれる可能性があります。
【共通ルール】結果的に子どもが1人なら、浮いた予算は未来への最強の投資に!
どちらのプランを選んだ場合でも、もし結果的にご家庭が「子どもは1人」という未来を選択した場合、どうなるでしょうか?
その時、確保していた教育費の余剰分(プランAなら1人分、プランBなら0.5人分)は、繰り上げ返済に回してローンを早期完済する原資にしたり、新NISAなどを活用して老後資金をさらに豊かにする「未来への最強の投資資金」に変わるのです。
つまり、この逆算予算術は、どちらに転んでもあなたの家族の未来を力強く守ってくれる、攻守最強の戦略と言えるのです。
10年後、後悔しない家の選び方【未来を見据えた3つの新常識】


盤石な予算計画が立てられたら、次はいよいよ「どんな家を選ぶか」です。
家族構成が不確定な中で後悔しないための家の選び方には、3つの新常識があります。それは
- 「広さより、可変性」
- 「憧れより、資産価値」
- 「背伸びより、身の丈」
です。
これからの日本は、本格的な人口減少社会に突入します。
かつての「郊外に庭付きの一戸建て」という画一的な夢の形は、将来「売りたくても売れない負の資産」に変わるリスクをはらんでいます。
10年後、20年後も「この家を選んで本当に良かった」と心から思うためには、今の価値観だけでなく、未来の変化を見据えた視点が不可欠だからです。
新常識①:「広さ」より「可変性」
まず一つ目は、部屋の数や㎡数といった単純な「広さ」に固執しないことです。特に、子どもの人数が不確定な段階では、将来のあらゆる可能性に対応できる「可変性」が重要になります。
例えば、新築時に「今は広い一つの子ども部屋として使い、将来きょうだいができたら、真ん中に壁を作って2部屋に分けられる」といった設計を選ぶのが賢い選択です。
これなら、子どもが1人でも2人でも、無駄なく空間を活用できます。
そして、少しドライに聞こえるかもしれませんが、「子どもが家にいる子育て期間は、長い人生で見れば意外と短い」と割り切る覚悟も大切です。
子どもが巣立った後、夫婦2人には広すぎる家は、掃除も管理も大変な負担になりかねません。
ライフステージの変化に合わせて、家も柔軟に形を変えられる。そんな発想が、将来の暮らしの快適さを左右します。
新常識②:「憧れ」より「資産価値」
二つ目は、最も重要なポイントです。それは、デザインや憧れだけで家を選ぶのではなく、「資産価値が落ちにくい家」という視点を持つことです。
ここで一つ、衝撃的なデータをご紹介します。
国土交通省の将来推計によると、2050年には日本の総人口が約1億人を下回り、居住地域の約6割で人口が現在の半分以下になると予測されています。
2050年、居住地域の6割で人口が半減するという衝撃
これが何を意味するか?ズバリ、これからの時代、「大きな家」や「不便な立地の家」は買い手がつかず、売れなくなる可能性が非常に高いということです。
たとえご自身が永住するつもりでも、将来、転勤や介護などで住み替えが必要になる可能性は誰にでもあります。
その時に「売れない」「貸せない」とならないよう、人口動態データなども参考にしながら、将来的に需要が見込める「立地」を最優先で選ぶこと。
これが、あなたの大切な資産を守る上で、最強の防衛策になります。
新常識③:「背伸び」より「身の丈」
そして最後の三つ目は、予算計画の再確認です。
素晴らしい物件に出会うと、誰しもテンションが上がって「これくらいのオーバーなら、何とかなるかも…」と、つい背伸びしたくなるものです。
しかし、そこで一度立ち止まり、前の章で立てた「プランA」または「プランB」の予算を絶対に超えないという鉄の意志を持ってください。
教育費という聖域を守り、家族の未来を守るために設定した、いわば「防衛ライン」です。



理想の家は、あくまで「幸せな暮らし」を実現するための手段であって、目的ではありません!
無理のない資金計画という土台があってこそ、家族の笑顔は守られるのです。
よくある質問とその回答(FAQ)
- Q1. 子ども1人用の家を買った後、2人目が生まれて手狭になったらどうすれば?
-
もし資産価値の高い立地を選べていれば、慌てる必要はありません。選択肢は主に2つ。一つは、今の家を売却、あるいは賃貸に出して、新しい広い家に「住み替える」ことです。
もう一つは、今の家を「リフォーム」して部屋数を増やす方法です。どちらの選択肢も、購入時に資産価値を重視したからこそ取れる、前向きな戦略と言えます。
- Q2. 2人を想定して広い家を買った結果1人だった場合、ローン返済が不安です。
-
ご安心ください。そもそも「ライフプラン逆算予算術」で、教育費の聖域を確保した上で無理のないローンを組んでいるはずなので、家計が破綻することはありません。
余った一部屋は、趣味の部屋やホームオフィス、ゲストルームとして活用すれば、暮らしの質が豊かになります。浮いた教育費で繰り上げ返済を進めれば、老後の安心にも繋がります。
- Q3. 将来の資産価値を考えると、戸建てよりマンションの方が有利ですか?
-
一概にどちらが有利とは言えません。重要なのは建物の種類よりも「立地」です。一般的にマンションは駅近など利便性の高い場所に多いため、資産価値を維持しやすい傾向はあります。
しかし、戸建てでも人気のエリアで、土地の価値がしっかりしていれば十分に資産性は保てます。ご自身のライフスタイルや、管理の手間なども含めて総合的に判断しましょう。
- Q4. 人口が減るなら、中古物件を買ってリノベーションする方が賢い選択ですか?
-
はい、非常に賢明な選択肢の一つです。人口減少社会においては、新築の供給が少ない良い立地の物件を、中古で手に入れるという戦略はますます重要になります。
ただし、建物の耐震性や断熱性など、見えない部分の性能は必ず専門家(ホームインスペクター)に確認してもらうことが、後悔しないための絶対条件です。
- Q5. 予算を立てる際、妻の収入はどのように考えれば安全ですか?
-
最も安全なのは、基本のローン返済は夫の収入だけで賄えるように計画し、妻の収入は教育費の積立や繰り上げ返済、家族旅行などの「ゆとり費」と考える方法です。
もし妻の収入を合算してローンを組む場合でも、育児などで働き方が変わる可能性を考慮し、現在の収入の5割~7割程度で見ておくと、将来の不測の事態にも対応しやすくなります。
まとめ
最後に、この記事でお伝えした最も重要なポイントを5つにまとめました。この5か条が、あなたの家族を未来のリスクから守り、後悔しないマイホーム購入を実現するための羅針盤となるはずです。
「2人目の壁」の悩みはあなた一人ではない。最新データが示す通り、多くの家庭が同じ葛藤を抱えていることを知り、まずは安心して計画を始めよう。
年収からではなく「教育費」という聖域を先に確保する逆算思考で予算を立てる。これが将来、家族構成がどう変わっても家計を守る最強の防衛策になる。
「広さ」よりも、将来の家族構成の変化に対応できる「可変性」を重視する。子育て期間は有限、という割り切りも時には大切。
人口減少社会では「資産価値」が落ちにくい立地選びが全て。10年後、20年後に「売れない・貸せない」というリスクを回避しよう。
漠然としたお金の不安は、専門家と共に具体的な「ライフプラン」に落とし込むことで解消できる。一人で抱え込まず、プロの力を賢く活用しよう。